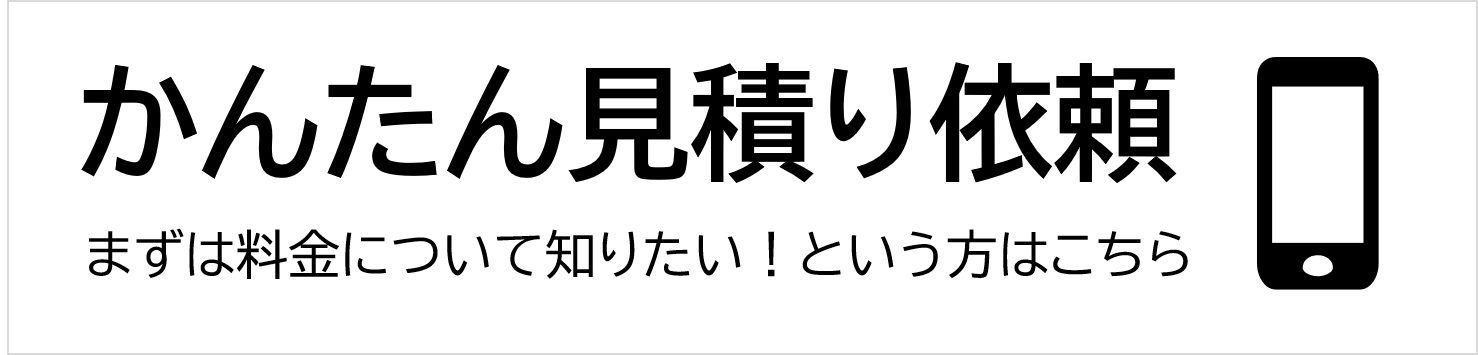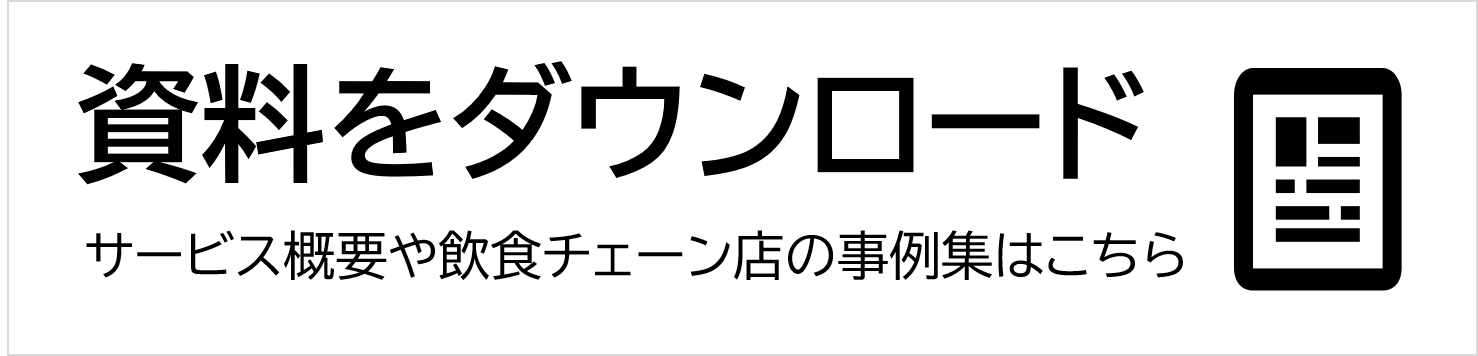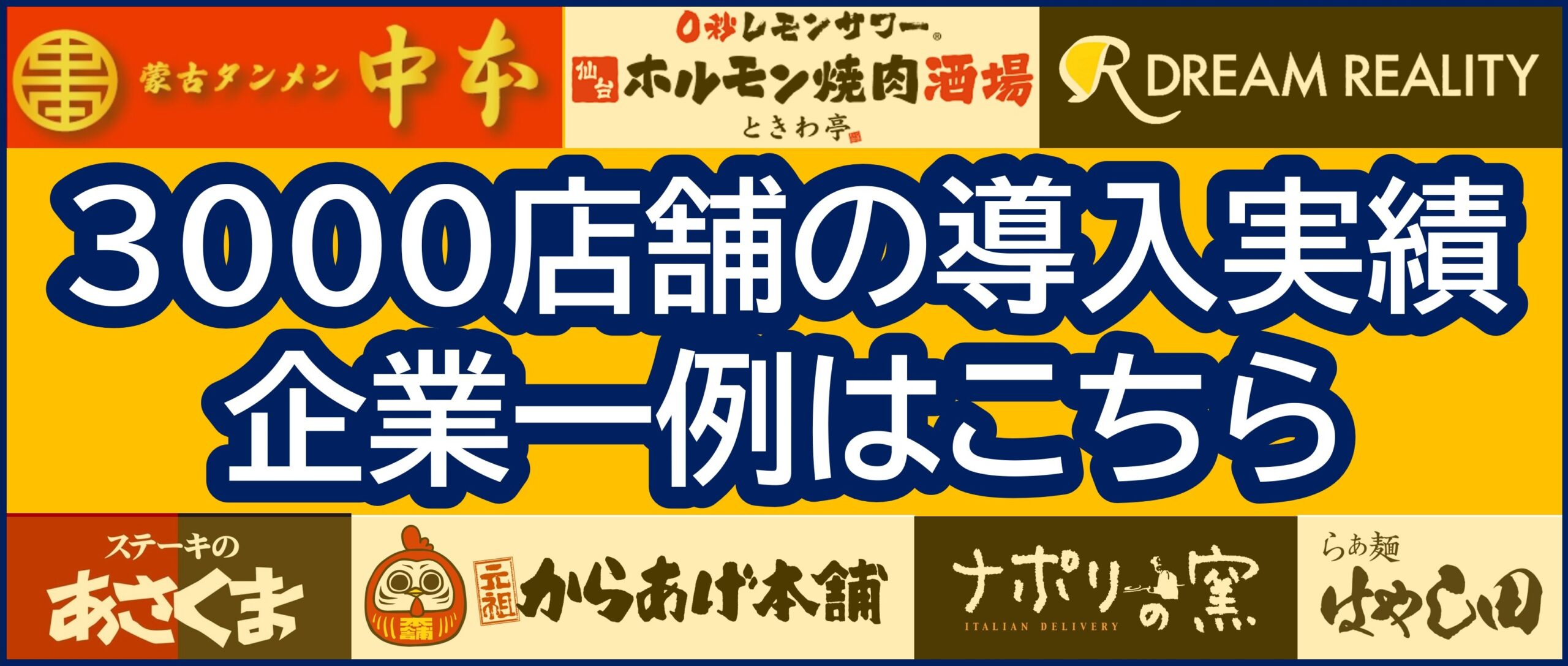【飲食店の賃上げ】傾向と対策2026_人件費高騰を乗り切る実践ガイド
2026年を迎えるにあたり、飲食店経営者の多くが「賃上げ」という新たな課題に直面しています。
コロナ禍からの回復と共に、インバウンド需要が再び高まりつつある状況で、人手不足のプレッシャーが増す一方です。
この記事では、飲食店が賃上げを効果的に実施しつつ、経営を持続可能にするための戦略を解説します。
飲食店の主要チェーンの事例を交えながら、賃上げを単なるコストではなく、優秀な人材を確保し、サービス向上を図るチャンスと捉える方法を紹介します。
また、値上げや業務効率化、助成金の活用といった原資確保策や、福利厚生を活用した「第3の賃上げ」についても詳述。賃上げを通じた経営改善のアクションプランを考察し、読者が抱える悩みに共感しながら、具体的な解決策を提供します。
飲食店が賃上げを「攻めの経営」に変えるためのヒントを、ぜひ本記事で見つけてください。
目次
1:飲食店を取り巻く経営環境と賃上げの背景【2026年版】
本章では、飲食店を取り巻く経営環境と賃上げの背景についてお伝えします。
1-1:コロナ禍からの回復と新たな課題
2020年以降、コロナ禍により飲食業界はかつてない打撃を受けました。営業制限、外出自粛、消費者心理の冷え込みにより、多くの飲食店が一時閉店や業態転換を迫られました。しかし、2024年頃から徐々に需要が回復し、2026年現在では新規顧客の獲得や売上回復に成功している店舗も増えています。
たとえば、テイクアウトやデリバリーといった非接触型サービスの定着に加え、感染症対策を徹底した“安心・安全な店づくり”を打ち出す店舗が支持されるようになりました。地方の観光地では国内旅行者の回帰傾向が顕著であり、観光地周辺の飲食店はファミリー層や団体客の戻りに伴い売上を伸ばしています。
しかし、そうした明るい兆しの一方で、食材・光熱費・家賃などの固定費がコロナ前よりも高騰している現実があります。特に輸入食材は円安や物流コストの増加の影響を大きく受けており、店舗経営にとって“固定費の上昇+人件費の増加”という二重のプレッシャーがのしかかっています。
つまり、回復の兆しが見えてきた今だからこそ、安定経営のための再設計が求められているのです。
1-2:インバウンド需要の回復と店舗への影響
2023年以降、日本へのインバウンド観光客は急速に回復しました。政府のビザ緩和政策や円安の影響も相まって、2025年には訪日外国人客数がコロナ前の水準に近づく勢いを見せています。都市部ではアジア圏からの観光客が街を歩く光景が日常に戻りつつあり、観光地や駅周辺の飲食店にとっては大きな追い風となっています。
このインバウンド回復は、単なる“集客の増加”にとどまらず、店舗経営における課題解決の糸口にもなり得ます。
たとえば:
↓
・多言語対応メニューの導入
・クレジットカードやQR決済などキャッシュレス化の促進
・ハラルやベジタリアン対応メニューの開発
・外国人観光客向けSNSキャンペーンの実施
といった取り組みは、既存の業務体制を見直す良いきっかけとなり、効率化・差別化につながります。
さらに、インバウンド需要の恩恵で売上が安定すれば、賃上げの原資確保にも好影響を及ぼします。特に“スタッフの語学力向上”や“インバウンド向け接客教育”は、従業員満足度の向上とスキルアップ支援の両面で効果を発揮し、賃上げの意義を現場に伝える手段としても有効です。
1-3:飲食業界における人手不足と賃上げプレッシャー
2026年の飲食業界最大の課題のひとつが、深刻な人手不足です。少子高齢化により若年層の労働力が減少し、アルバイト・パートの採用が困難になっています。特に都市部の飲食店では、時給1,200円台でも応募が集まらず、1,400円以上を提示する店舗も珍しくありません。
こうした状況下で、他業種との人材獲得競争も激化しています。物流業界、コンビニ、宿泊業なども人材不足を背景に賃金を引き上げており、飲食店も賃上げに踏み切らなければ採用が追いつかない時代に突入しています。
実際に、ある調査によれば、2022年の飲食業平均時給は前年比約3%の上昇。2025年春闘では、非製造業平均を上回る水準の賃上げ率が記録され、**“金額ベースの賃上げ”**が主流になりつつあります。
ただし、単純に時給を上げればよいというわけではありません。採用は一時的に成功しても、従業員の定着がなければ意味がありません。そのため、賃上げと並行して働きやすさ・働きがいを実感できる環境づくりが、今後の飲食店経営のカギを握るのです。
2:賃上げの最新動向と業界トレンド

2-1:2025年の注目結果と金額トレンド
2025年では、過去最大級とも言われる賃上げが相次ぎました。とくに飲食業界を含む非製造業では、「定率」ではなく「定額」での賃金引き上げが主流となり、“1人あたり月1万円以上”のベースアップを実施する企業も増えています。
この背景には、物価上昇の影響により、実質賃金が目減りしている労働者側の切実なニーズがあります。定率の昇給だけでは生活が追いつかないため、企業側も“金額でわかりやすい賃上げ”を打ち出さざるを得ない状況になっているのです。
また、政府も賃上げを強力に後押ししており、補助金制度や減税措置、社会保険料の負担軽減策などが実施されています。中小企業にとってはこうした支援をうまく活用し、従業員の生活を守る姿勢を打ち出すことが、結果として採用競争における強みにもなります。
2025年に引き続き、2026年も飲食業界は「人手不足解消=賃金改善」の図式が色濃く、一定以上の賃上げなしでは採用や定着が難しい時代に突入しています。
2-2:非製造業を上回る賃上げ率と飲食業の存在感
かつては「低賃金業界」と見られていた飲食業界ですが、近年では他のサービス業を上回る勢いで賃上げが進んでいます。実際、2025年春闘においては、非製造業の平均賃上げ率が4.2%を超え、その中でも飲食・宿泊業が牽引役のひとつとなりました。
飲食業界がこれほど積極的に賃上げに取り組む背景には、以下のような要因があります。
↓
・採用難の深刻化(求人広告を出しても応募が来ない)
・競合業態との人材争奪戦(物流・小売・医療介護など)
・顧客満足度とスタッフ満足度の連動性
・業務効率化や値上げによる原資確保が進んできたこと
かつての飲食業界は「人が辞めるのが当たり前」「現場が回ればOK」という風潮も一部にありました。しかし今は、「人が辞めない店が勝ち残る」という考え方が主流になりつつあり、賃金改善はその前提条件です。
2-3:主要チェーンの事例紹介(すき家・松屋・王将など)
大手飲食チェーンの動きも、業界全体の流れを加速させています。以下に代表的な事例を紹介します。
すき家(ゼンショーHD)
→2025年に正規従業員1,000名以上の時給を平均11%以上引き上げ。定着とモチベーション向上を狙う。
松屋フーズ
→新卒の初任給を1.5万円UP。その他の賃金改定などを含めると最大で10%以上も賃上げ。
餃子の王将
→組合要求を上回る8.2%の賃上げを実施。大卒の新卒初任給も30万円代に突入。
すかいらーくグループ
→基本給と定期的な昇給を合わせて平均約6.5%の賃上げ。
こうした大手の取り組みは、“時給を上げれば応募が来る”という成果を現場で証明した成功例でもあります。そしてこの流れは、地方の中小飲食店にも波及しており、「今やらなければ置いていかれる」という空気が業界全体に広がっています。
3:飲食店が賃上げに取り組む目的と期待される効果
本章では、飲食店が賃上げに取り組む目的と期待される効果についてお伝えします。
3-1:優秀な人材確保と応募数の確保
飲食業界において、人手不足は慢性的な課題です。特に都心部では、アルバイトや正社員の採用競争が激しく、求人広告を出しても応募がゼロという事例も少なくありません。そんな中で、最も即効性がある手段の一つが賃上げです。
実際、同一エリア内で時給1,100円と1,300円の求人があれば、後者に応募が集中するのは当然です。人材確保の段階では、応募数=母集団の質を高めることが最優先事項となり、賃金水準がその決定打になります。
さらに最近では、給与だけでなく福利厚生の充実も重視される傾向が強くなっています。たとえば、以下のような制度は人材確保の武器になります。
・家族手当(扶養者への支援金)
・食事補助(勤務時のまかない無料)
・社員割引制度
・交通費支給や遠方手当
・昇給や評価制度の明文化
これらの制度は金銭的な魅力だけでなく、「この会社はスタッフを大切にしている」という好印象を与えることができます。特に“家庭を持つ求職者”にとって、家族を支えるサポートがあるかどうかは、応募先を選ぶ重要な判断基準となります。
3-2:従業員満足度・定着率の向上
せっかく採用に成功しても、すぐに辞めてしまっては意味がありません。特に新人教育にかかるコストや現場への負担を考えると、“定着率”は採用以上に重要な経営指標です。
そのためには、従業員が「ここで働き続けたい」と思える環境づくりが欠かせません。そして、賃上げはその第一歩です。
賃上げを実施することで得られる効果には、次のようなものがあります。
・生活の安定感:特に物価が上昇している現代では、数百円の昇給でも家計に与える影響は大きく、安心感につながります。
・会社への信頼感:頑張りを評価してくれる会社に対して、従業員は自然と帰属意識を持つようになります。
・将来への希望:キャリアアップやスキルアップに応じて報酬が上がる仕組みがあると、モチベーションが継続します。
さらに、定期的な面談やフィードバックの場を設けることで、「評価されている」「期待されている」という感覚が生まれ、離職防止につながります。
また、福利厚生の充実も従業員満足度に大きく影響します。たとえば
↓
・有給休暇の取りやすさ
・シフトの柔軟性
・急な休みにも対応できるサポート体制
・職場内コミュニケーションの活性化
こうした施策の積み重ねが、「続けたいと思える職場」へと進化させるカギとなるのです。
3-3:サービス向上と店舗収益への好循環
賃上げは単なるコスト増ではありません。正しく行えば“収益向上”というリターンを生む投資となります。
たとえば、以下のような好循環が期待できます。
↓
・賃上げにより従業員のモチベーションがアップ
・モチベーションが高まれば、笑顔・声かけ・気遣いなど接客の質が向上
・サービスレベルが上がれば、顧客満足度が向上
・満足したお客様がリピーターとなり、口コミ・紹介を増やす
・売上が安定し、さらなる賃上げや教育投資の原資を確保
これは、飲食店にとって理想的な成長サイクルです。
さらに、従業員の定着により教育コスト・採用コストが削減され、経費全体の最適化にもつながります。これは長期的に見れば、コスト削減策としても有効です。
加えて、国や自治体の助成金・補助金制度を活用すれば、賃上げにかかる負担を軽減することも可能です。たとえば「キャリアアップ助成金」は、正社員登用や賃金改善に対して支給される制度で、多くの中小飲食店でも利用が進んでいます。
4:賃上げに対応するための3つの原資確保策

4-1:値上げによる価格転嫁と高付加価値メニュー戦略
飲食店が賃上げを実現するには、その原資や財源をどこから確保するかが最大のポイントです。最も基本的な方法のひとつが、商品価格の見直し=値上げです。
近年は、原材料費や光熱費、人件費などのコストが全体的に上昇しており、価格転嫁をせずに経営を維持するのは困難です。ただし、単純に値上げをすれば良いというわけではなく、顧客離れを防ぐために**“納得感のある価格改定”**が求められます。
そのために有効なのが、高付加価値メニューの導入です。たとえば
↓
・限定素材を使用した季節限定メニュー
・SNS映えを意識した盛り付けや演出
・家族で楽しめる特別セット
・特別感のある“記念日向けコース”
これらは価格を高めに設定しやすく、単価アップを通じて収益改善に貢献します。さらに「ちょっと高くても価値がある」と思ってもらえれば、値上げに対する心理的ハードルを下げることができます。
また、値上げを実施する際は次の点も大切です。
↓
・事前に張り紙やメニュー表で理由を説明する
・付加価値(味・量・演出・サービス)を強化する
・クーポンや特典などで“お得感”を同時に演出する
「顧客が納得してくれる値上げ」を成功させることが、結果的に賃上げの財源を生み出すことにつながるのです。
4-2:業務効率化・デジタル化による人件費削減
賃上げを実現するもう一つの道は、業務の無駄を削減して利益率を高めることです。特に人件費に直結するオペレーションの見直しは、即効性のある対策です。
たとえば以下のような業務効率化が注目されています。
・セルフオーダーシステム(タブレット・QRコード注文)
→注文取りの手間を減らし、配膳や調理に集中できる
・在庫管理や予約管理の自動化ツール
→発注ミスやダブルブッキングを防ぎ、ロスを削減
・シフト管理アプリ・AIスケジューリング
→最適な人員配置を実現し、過不足を防止
これらはすべて、人的工数を減らす=時給総額を抑えつつ店舗を回すことに直結します。
さらに、デジタル化には「従業員の負担軽減」「人為的ミスの減少」「売上分析や販促施策の高度化」などの副次的な効果も期待できます。
なお、こうしたITツールの導入には初期費用がかかりますが、補助金制度を活用すればコストを大きく抑えることが可能です。次の章で紹介する各種助成金・補助金も、業務効率化投資の強い味方となります。
4-3:国・自治体の助成金を活用して原資を確保
賃上げにともなうコスト増加をカバーするために、国や自治体の補助制度をフル活用することは非常に有効です。実際、賃上げやキャリア支援に使える助成金制度は数多く存在します。
代表的な制度は以下のとおりです。
・キャリアアップ助成金(厚労省)
→非正規社員を正社員に転換した際や、昇給を実施した場合に支給
・業務改善助成金
→生産性向上のための設備導入や業務改善と賃上げをセットで行った場合に支給
・小規模事業者持続化補助金(中小企業庁)
→販促や業務改善を目的とした取り組みに対して支給
・地方自治体独自の支援制度
→東京都などでは、専門家派遣や設備補助、IT導入支援なども展開中
助成金活用のポイントは次の3点です。
①最新情報の把握(制度改廃が多いため、商工会や公式サイトの確認が必須)
②目的に合った制度を選ぶこと(賃上げ目的/人材定着目的/IT導入目的 など)
③申請書類を専門家にサポートしてもらうこと(社労士や中小企業診断士の支援で受給率が大幅アップ)
助成金は「使わないと損」といっても過言ではありません。資金面での不安を補い、攻めの賃上げ・経営改善を後押ししてくれる強力なツールです。
5:持続可能な賃上げを実現するための経営改善アクション
本章では、持続可能な賃上げを実現するための経営改善アクションについてお伝えします。
5-1:従業員育成とキャリア支援制度の整備
賃上げを一時的な対応で終わらせないためには、「従業員の成長と成果が賃金に結びつく仕組みづくり」が欠かせません。たとえば、アルバイトから正社員への登用制度、職位に応じた等級制度、資格取得による昇給ルールなどを明文化することで、従業員は自身のキャリアビジョンを描きやすくなります。
具体的な支援策としては以下のようなものが挙げられます。
↓
・研修プログラムの整備(OJT/リーダー研修など)
・社内資格やスキル認定制度の導入
・業務マニュアルをベースとした「段階的なスキル到達表」の作成
・定期評価とフィードバック面談の実施
こうした仕組みが整っている職場では、従業員の離職率が低く、結果として採用・育成コストの削減にもつながります。また、「頑張った分だけ給与が上がる」という納得感のある制度は、モチベーション維持にも直結します。
5-2:粗利人時生産性の向上を意識した運営
「賃金を上げる=利益が減る」と思われがちですが、経営視点で考えるべき指標は**“人件費率”ではなく“粗利人時生産性”**です。これは、1時間あたりにスタッフが生み出す粗利(売上-原価)を示すもので、以下の式で表されます:
粗利人時生産性(円)=粗利益 ÷ 総労働時間
たとえば、スタッフ1人が1時間で3,000円分の粗利を生み出しているとすれば、時給1,200円でも十分に賃上げは可能ということになります。つまり、「時給」だけを切り取るのではなく、いかに効率よく稼働できているかを見極めることが重要です。
粗利人時生産性を上げるためには
↓
・業務の簡略化/役割の明確化
・ピークタイムとアイドルタイムの人員調整
・高単価メニューの販売強化
・教育による接客・販売スキル向上
などの施策を通じて、限られた人員でより多くの価値を生み出す体制を整えることが求められます。
5-3:多角的なKPI設計と評価制度の導入
持続的な賃上げには、給与水準の基準が明確であり、従業員が納得感を持てる評価制度が必要不可欠です。特に「感覚的な昇給」や「年功序列」に頼っていると、優秀な人材ほど離れていく傾向があります。
そこで導入したいのが、数値で見えるKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を活用した評価制度です。
KPIの例としては
↓
・月間売上や客単価の目標達成率
・レジミスやクレーム件数の削減率
・アンケートでの接客満足度
・後輩育成の貢献度(OJT評価)
・チームワークや協調性(定性評価)
定量と定性のKPIをバランスよく組み合わせ、評価の透明性を高めることで、**「自分の頑張りがどう給与に反映されるのか」**が明確になります。
また、評価制度を導入することで、スタッフとの面談機会も自然に増え、信頼関係の構築・定着率向上にもつながります。
このように、賃上げは単なる「コスト」ではなく、人材定着・業務効率化・売上拡大の起点として捉えることで、持続可能な成長戦略となります。
6:「第3の賃上げ」=福利厚生を活用した従業員支援策

6-1:非課税枠を活用した福利厚生ポイント
近年注目されているのが、「給与以外の報酬」である福利厚生制度の拡充による支援策です。これは「第3の賃上げ」とも呼ばれ、金銭的な価値を持ちながらも、直接的な給与として扱わないことで税・社会保険料の負担を抑えられるというメリットがあります。
たとえば、「企業が従業員に福利厚生費として支給する一部サービス(例:福利厚生倶楽部やチケットレストランなど)」は、ある程度の金額まで非課税で提供可能です。この仕組みを活用することで、従業員の可処分所得を実質的に増やすことができ、間接的な賃上げ効果を得ることが可能です。
具体的な活用例
↓
・提携飲食店やコンビニなどで使える食事補助チケット
・通勤手当やガソリン代補助
・医療・育児・介護関連の補助制度
・スポーツジムや映画館の利用補助
・社員旅行やレクリエーション費用
これらを導入することで、従業員は“実質的に得をしている”という満足感を得られ、会社への信頼感・定着率アップに貢献します。
6-2:福利厚生チケットやアプリ連携制度の導入
中小飲食店では「福利厚生=大企業だけのもの」と思われがちですが、最近では小規模事業者でも導入可能な低コストのサービスが充実しています。
その代表が、**「福利厚生チケット制度」や「モバイルアプリとの連携型福利厚生」**です。
福利厚生チケット導入のポイント
↓
・使い勝手の良さ:紙・電子どちらも対応可能。食事・交通・育児など多様な用途に対応。
・柔軟な選択肢:従業員のライフスタイルに合わせた項目を選べる。
・スマホ完結型も可:残高確認や利用履歴もアプリ上で簡単にできるため、利便性が高い。
導入にあたっては、初期費用や運用コストを抑えられるプランもあるため、コスト対効果が非常に高い福利厚生施策として注目されています。
また、これらの制度を導入する際は、社内説明やQ&Aの場を設けて、従業員に制度の価値を理解してもらうことが定着のカギです。使い方がよくわからないまま放置されてしまうと、本来の効果が出ません。ポスター掲示やスタッフミーティングを通じて、継続的な周知を行いましょう。
6-3:給与以外の“満足”を高めて離職を防ぐ
若年層を中心に「給与だけで会社を選ばない」という価値観が広がっています。むしろ、以下のような働きやすさ・働きがいの部分が重視される時代です。
・プライベートとの両立ができるシフト制度
・スタッフ同士の関係性や職場の雰囲気
・自分のライフスタイルに合わせた福利厚生制度
・健康やメンタルをサポートしてくれる体制
こうした価値観に応えるためには、給与以外にも“働く意味”を見出せる環境づくりが不可欠です。
たとえば、こんな声が現場で実際に上がっています。
↓
「時給より、ちゃんとシフトを希望通りに入れてもらえる方がありがたい」
「家族の行事があるときに休めるだけで、すごく働きやすい」
「食事補助や交通費があるから、実質的な収入は他より多いと感じる」
このように、金銭以外の“満足”を提供することで、結果的に給与以上の働きがい・定着率向上につながるのです。
7:設備・機器投資によるコスト最適化と省人化

7-1:厨房機器の選定で作業効率と光熱費を削減
飲食店の運営において、厨房機器のパフォーマンスは収益に直結します。特に人手不足の中で少人数で店舗を回すためには、省人化・省エネが可能な厨房機器の導入がカギとなります。
たとえば、以下のような最新機器は、業務効率とコスト削減を同時に実現できます:
・自動フライヤーや自動茹で麺機
→温度・時間を自動管理し、仕上がりにブレがなく誰でも作業可能に。
・急速冷凍機・スチームコンベクションオーブン
→食材のロスを減らし、調理の手間を短縮。
・省エネ型冷蔵庫・冷凍庫
→電気代の抑制だけでなく、庫内管理の効率もアップ。
これらの導入により、作業時間が短縮され、スタッフの労働負荷を軽減できます。特に新人や非熟練スタッフでも対応しやすくなるため、教育コストの削減と品質の安定化というメリットも得られます。
また、厨房機器における**デジタル管理機能(温度や調理プロセスの自動制御など)**は、スタッフの判断ミスを減らし、事故防止やフードロス削減にも効果的です。
初期投資こそ必要ですが、中長期的には人件費・光熱費・食品ロスの削減効果で元が取れる可能性が高く、実質的な「利益向上施策」となります。
7-2:調理器具の活用とメンテナンスによるコスト最適化
大型機器の導入が難しい店舗や、限られた予算の中でもできるコスト改善策として、「調理器具の見直し」も有効です。
たとえば:
・複数の工程を一つでこなせる多機能調理器具の活用
→作業効率が上がり、洗い物の手間も軽減。
・高耐久性素材の採用(テフロン加工・セラミック製など)
→買い替え頻度が下がり、コストダウンにつながる。
・IHやガスの切り替えによる熱効率の改善
→光熱費が安定する。
さらに、日常的なメンテナンスや点検を習慣化することで、機器の寿命を延ばし、突発的な修理費や営業停止リスクを避けることができます。定期的なメンテナンスには以下のような効果があります。
↓
・故障リスクの早期発見と予防
・衛生状態の維持
・火災や事故リスクの低下
・機器のパフォーマンス維持と省エネ効果の継続
省人化が求められる今だからこそ、「調理機器を味方につける」ことが賃上げを支える土台となるのです。
また、こうした厨房環境の改善は、スタッフの働きやすさや安全性の向上にも直結し、結果的に離職率の低下にも寄与します。
設備・機器投資は、ただのコストではなく「働き方改革」「人件費最適化」「売上維持」のための戦略的な手段です。補助金・助成金の対象になることも多いため、賃上げ施策の一環として積極的に取り組む価値のある分野と言えるでしょう。
8:まとめ|2026年、賃上げを「攻めの経営」に変える発想を
2026年、飲食業界はこれまで以上に大きな転換点を迎えています。
最低賃金の上昇、物価高、採用難…。一見するとどれも“経営を苦しめる要因”に思えるかもしれません。しかし、こうした環境変化は、経営のあり方を見直し、成長へと転じる絶好のチャンスでもあります。
本記事で紹介してきたように、持続可能な賃上げを実現するには、「給与を上げる」だけではなく、経営そのものの設計をアップデートすることが不可欠です。
✔ 賃上げ成功のカギは、3つのバランスにあります。
↓
・給与の引き上げ(生活を支える)
・成長支援の整備(キャリアを支える)
・労働環境の改善(心を支える)
この3本柱がそろって初めて、従業員は長く働きたいと思い、顧客に良いサービスを提供し、それが店舗の収益と原資を生み出すという好循環が成立します。
また、助成金や補助制度を活用することで、賃上げによる経営リスクを軽減する手段も多数用意されています。決して“余裕のある店舗だけができる施策”ではなく、知識と工夫で実行可能な現実的な対策なのです。
賃上げを「仕方なく行うコスト」ではなく、「成長のための戦略」として捉えることができるかどうか。そこに、2026年以降の飲食店経営の明暗が分かれる分岐点があります。
最後に|変化に適応できる店舗こそが“選ばれる店”になる
物価が上がり、働き手が減り、顧客ニーズが多様化していく時代。
そんな中でも、柔軟に対応し続ける店には、必ず人が集まり、利益が残ります。
そしてその根幹を支えるのは、“人”=従業員です。
彼らのやる気と定着が、サービスの質となり、ブランド価値となり、やがて売上・利益を押し上げていきます。
だからこそ、賃上げは“守りの防衛策”ではなく、攻めの未来投資として、前向きに取り組む価値があるのです。