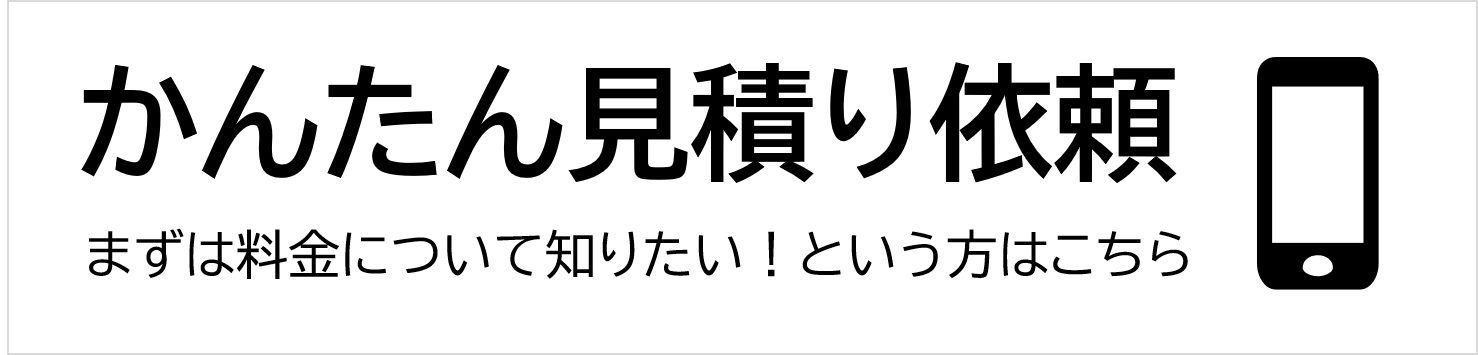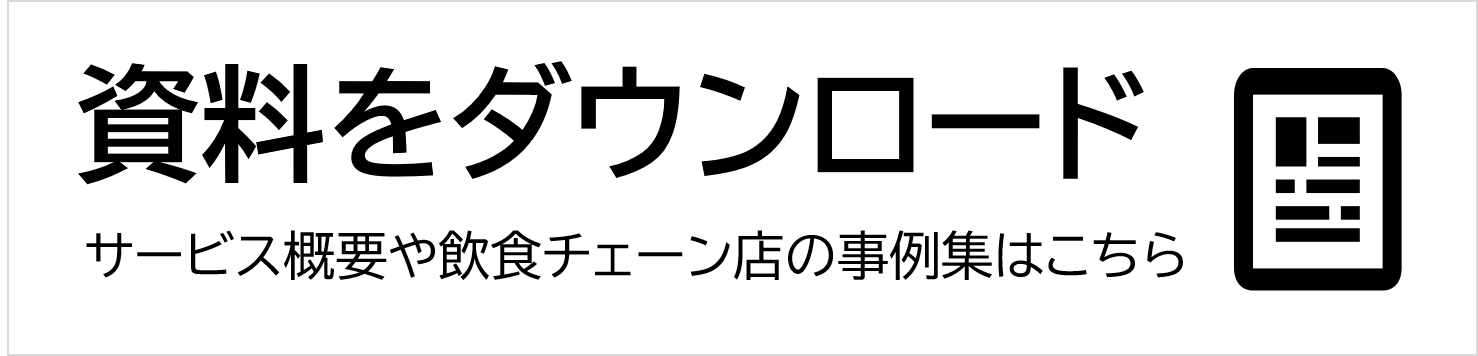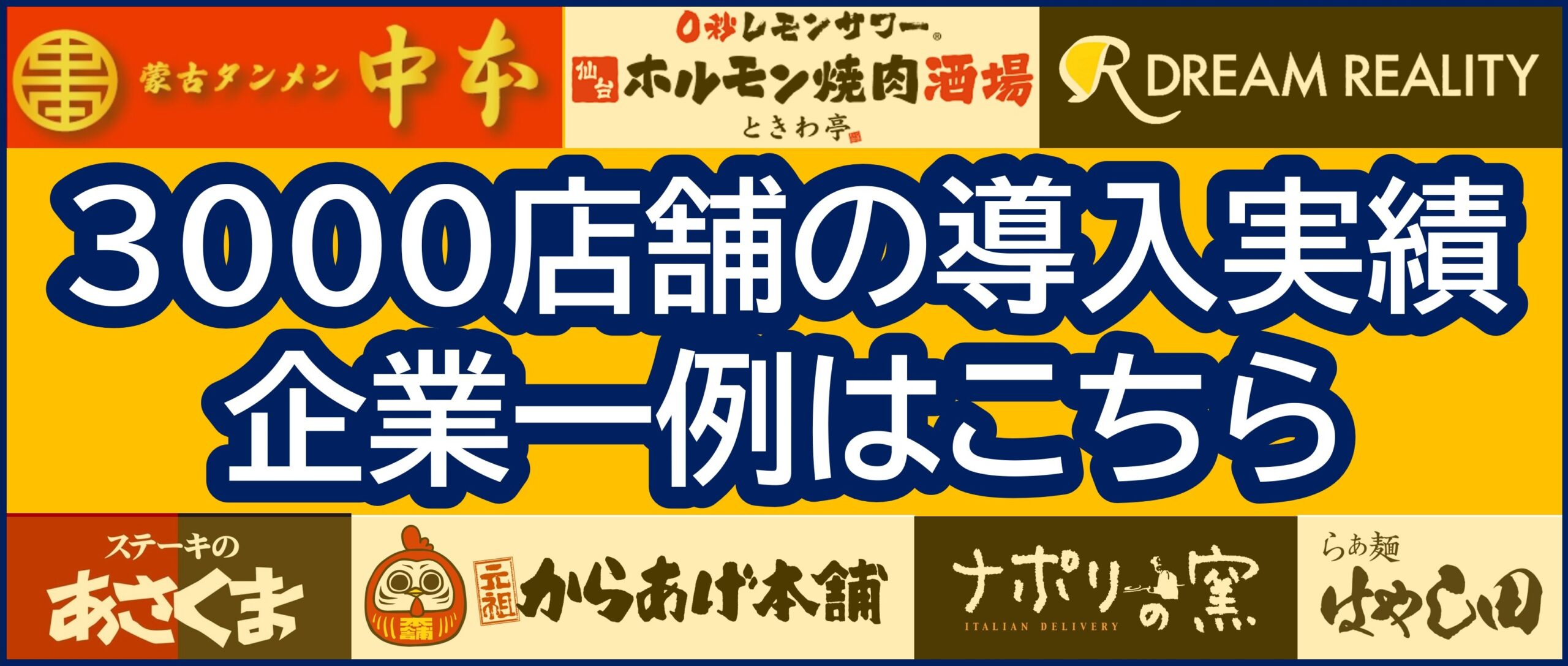飲食店の物価高はいつまで続く?影響・原因・値上げ対策を完全ガイド
近年の物価高が続く中で、経営に不安を感じている飲食店経営者の方も多いのではないでしょうか。
食品や調味料、エネルギー価格の高騰が止まらず、2026年以降もその影響は続く見通しです。
この記事では、物価高の具体的な原因や飲食店への影響、そして今すぐ取り組むべき対策を詳しく解説します。
原材料費や人件費の上昇によるコスト管理の難しさに対し、どのように対応すべきかを探ることで、飲食店経営の安定化を図る手助けとなるでしょう。
物価高で値上げが避けられない状況でも、顧客の信頼を失わずに売上を維持するための具体的な戦略も紹介しています。
物価高を乗り越え、経営を成功に導くための実践的なガイドとして、ぜひご活用ください。
飲食店の未来をより明るいものにするために、今こそ行動を起こしましょう。
目次
1:飲食店の物価高はいつまで続く?【結論:2026年も継続見込み】
「この物価高、いつまで続くんだろう…」「我慢していれば、そのうち前の仕入れ価格に戻るのでは?」
そんな不安や期待を抱きながら、毎月の請求書を眺めている方も多いと思います。
結論から言うと、2025年末時点では“すぐに元通り”になる可能性はかなり低いと考えた方が現実的です。
むしろ、今起きているのは一時的なショックではなく、外食産業全体の“原価の基準が上がってしまった”という構造変化に近い状態です。
ただし、悲観一色で考える必要はありません。
何がどれくらい上がっているのかを整理し、数字の見方と対策を身につければ、
**「物価高の中でも利益を残せる店」「むしろ競合との差を広げられる店」**になることは十分可能です。
本記事では、
・物価高の正体(原因と背景)
・飲食店の原価、人件費、損益分岐点に何が起きているのか
・今すぐできるコスト対策と値上げの考え方
・2026年以降を生き抜く経営の視点
までを順番に整理していきます。
まずは、「なんとなく大変」というモヤモヤを、「何が、どれくらい上がっているのか」という輪郭のある認識に変えるところから始めましょう。
1-1:食品・調味料・エネルギー価格の推移
ここ数年で、仕入れの請求書の印象は大きく変わりました。
肉、魚、乳製品、小麦粉、油、冷凍食品、そして醤油や味噌、料理酒といった調味料まで、外食のベースとなるほぼすべてが値上がりしています。
たとえばイメージとして:
・以前は1缶3,000円で仕入れていた揚げ油が、今は4,000円台になっている
・冷凍ポテトや輸入牛肉が、数年前と比べて割高になっている
といった変化が、少しずつ・しかし確実に積み重なっています。
さらに厄介なのが、食品だけでなくエネルギーコストも上がっていることです。
厨房機器を動かすガス代、空調や冷蔵庫・冷凍庫を動かす電気代。
どれも「止めるわけにはいかない」コストでありながら、請求額はじわじわと膨らんでいます。
その結果、同じ売上でも、数年前に比べて利益が残りにくい構造へと変わってしまいました。
単純に「もっと頑張って売ろう」で解決しないのは、こうした“見えにくいところからの値上げ”が重なっているからです。
1-2:2026年以降の見通し(原材料・輸入環境)
では、この状況が今後どうなるのか。
多くの飲食店にとって重要なのは、「一時的なら耐えよう」「もとに戻るなら値上げはギリギリまで我慢しよう」と考えてよい局面なのかどうかです。
残念ながら、世界全体で見ても、
・原材料の高騰(穀物・油脂・飼料など)
・戦争や地政学リスクによる供給の不安定化
・異常気象や不作による収穫量の乱高下
・国際物流の混乱と運賃の高止まり
・円安傾向による輸入コストの増加
といった「値上がり要因」は、短期で解消される見込みが薄い状況です。
特に、小麦粉や油、加工食品、ワインや輸入肉など、輸入依存度の高い食材は、海外情勢と為替という二重の影響を受け続けます。
そのため「急激に値下がりして、数年前の仕入れ水準に戻る」というシナリオは、かなり楽観的だと言わざるを得ません。
現実的には、“やや高くなった状態で上下を繰り返しながら、高止まりする”というイメージに近いでしょう。
この前提に立つと、「いつか元に戻るはず」と期待して価格を据え置き続けるのは、かなり危険です。
中長期で見れば、“以前の原価に戻ることを前提にした値付け”は、破綻のリスクを抱えた戦略になってしまいます。
1-3:値上げラッシュが続く構造的な理由
ここまで見てきたように、物価高の背景にあるのは、一つ二つの要因ではありません。
ポイントは、これは 「一時的なショック」ではなく、「構造的なコスト増」 だということです。
・原材料費の上昇
・ガスや電気料金の上昇
・物流費の上昇(燃料・人件費・人手不足)
・人件費や最低賃金の上昇
・社会保険料や各種システム利用料の増加
といったものが複合的に重なり、メーカー・問屋・小売・外食と、サプライチェーン全体のコストが押し上げられています。
「仕入れ先の値上げに困っている」という感覚は、実はその最終段階で起きている症状にすぎません。
メーカーもコスト増に耐えきれず値上げを行い、
その負担が卸や小売を通じて、最終的には飲食店の仕入れ価格に転嫁されている──
そんな連鎖構造の中に、私たちはいます。
だからこそ、「一度だけ思い切って値上げすれば、あとは元通り」という発想は通用しにくくなっています。
**「コストがじわじわ上がり続けることを前提にした経営設計」**が必要な時代に入った、と捉えるべきでしょう。
2:物価高の原因と背景【なぜここまで上がるのか】

次に、「なぜここまで物価が上がっているのか?」を整理していきます。
感覚的には「とにかく何もかも高くなった」という印象かもしれませんが、
原因を分解して見ていくと、どこに手を打てるか/どこはどうにもならないか が見えやすくなります。
ここでは、飲食店に特に影響の大きい4つの要素に絞って解説します。
2-1:原材料価格・食材費の高騰
まずは、原材料そのものの値上がりです。
小麦、油、肉、魚、乳製品──
どれも世界中で需要が高まり、気候変動や戦争、輸送の混乱などの影響を受けています。
たとえば、
・飼料価格の高騰で、畜産物全般の価格が上がる
・漁獲量の変動や燃料費の上昇で、水産物の仕入れ価格が安定しない
・小麦粉や油は、世界市場の価格と為替の影響をダイレクトに受ける
といった形です。
輸入食材はもちろん、国産品であっても、肥料・飼料・燃料といった“裏側のコスト”が上がっているため、結果的にほぼすべての食材に値上がり圧力がかかっているといっても過言ではありません。
そしてこの高騰は、特定のメニューだけにとどまらず、「全体の原価率をじわじわ押し上げる」 形で効いてきます。
2-2:エネルギーコスト(光熱費)・物流費の上昇
次に効いてくるのが、エネルギーと物流です。
飲食店は、電気・ガス・水道を使わずには営業できません。
特に、調理用のガス、空調や冷蔵・冷凍設備の電気代は、売上に比例せず一定以上かかる“固定的な負担”です。
一方で、物流の現場でも燃料費や人件費が上がり続けています。
トラックドライバー不足も深刻で、「人もいない・燃料も高い」というダブルパンチが、運賃の上昇となって現れます。
その結果、『同じ食材を、同じ量だけ仕入れているのに、「中身」と「運ぶコスト」の両方が高くなっている』という状態になっています。
遠方から運ぶ食材ほど、物流コストの影響は大きくなります。
このことは後ほど触れる「地元食材・共同購入」といった対策にもつながっていきます。
2-3:人件費・最低賃金の上昇
物価高と並行して、飲食店を悩ませているのが人件費の上昇です。
最低賃金はここ数年、毎年のように引き上げられています。
さらに、どの業界でも人手不足が深刻化しており、都市部を中心に「賃金を上げないと人が来ない」状態が続いています。
その結果、
・アルバイト時給を上げざるを得ない
・採用広告費がかかる
・人が定着せず、教育コストがかさむ
といった形で、人件費全体がじわじわと重くなっているのが実情です。
ここで勘違いしたくないのは、「給与アップ=悪」ではないということです。
飲食業界全体のイメージを上げ、長く働ける業種にしていくためにも、一定の賃金水準は不可欠です。
ただし、原価やメニュー価格を見直さずに人件費だけが上がっていけば、店の体力が持たなくなります。
「給与はきちんと払う。その代わり、原価・価格・オペレーションを見直して利益を守る」
このバランス感覚が必要な時代だと言えます。
2-4:CPI(消費者物価指数)から見る飲食業界
感覚的には「なんでも高くなった」と感じていても、「本当にそんなに上がっているのか?」と疑いたくなることもあるかもしれません。
そこで参考になるのが、総務省などが公表している**消費者物価指数(CPI)**です。
難しいことは抜きにして言えば、「モノやサービスの価格が、全体としてどれくらい上がっているか」を示す指標です。
この中で「食料」「外食」「エネルギー」といった項目を見ると、
全体の物価に比べて、これらの分野がより高い上昇率を記録していることがわかります。
つまり、『飲食店の仕入れや運営に関わる項目は、「他の分野よりも上がりやすい」領域に入っている』ということです。
3:物価高が飲食店に与える影響【経営へのインパクト】
原因が見えてきたところで、次に整理したいのが「その結果、店には何が起きているのか」です。
多くのオーナーが口をそろえて言うのは、
「売上はそこまで落ちていないのに、前ほどお金が残らない」という実感です。
ここからは、物価高が 原価率・FLコスト・損益分岐点・倒産リスク にどう影響しているのかを見ていきます。
3-1:原価率悪化とFLコストの上昇
まず、真っ先に打撃を受けるのが原価率です。
食材の仕入れ価格が数%上がるだけでも、年間の粗利益で見れば 数十万〜数百万円の差 になることも珍しくありません。
これに人件費の上昇が重なると、食材費+人件費=FLコスト は一気に重くなります。
FLコストは、飲食店の利益構造を決める“心臓部”のような数字です。
ここが高止まりすると、
・毎日忙しく営業しているのに利益が出ない
・売上が増えても、なぜか手元に現金が残らない
という状態に陥ります。
「これまでと同じやり方・同じ価格設定」を続けているだけで、自然にFLコストが悪化してしまう のが、今の物価高時代の怖いところです。
3-2:損益分岐点(トントンライン)の上昇
原価や人件費、固定費が上昇すると、損益分岐点(=トントンになる売上ライン) も同時に上がります。
以前であれば、「1日売上10万円あれば黒字」だった店が、今では「同じ条件でも、1日12〜13万円売らないと黒字にならない」という状況になっているかもしれません。
しかし、現場の感覚としては、
・以前と同じように店を開け
・以前と同じように忙しく働き
・以前と同じくらいの売上があるのに「昔ほど残らない」
という形で現れるため、売上目標を見直さないまま営業を続けてしまう ケースが非常に多くなります。
この「目標売上の基準」が、現実の損益分岐点よりも低いままだと、知らないうちに「赤字ライン」を目標にして働いていることになりかねません。
3-3:赤字店舗の増加と倒産リスク
こうした状況が続くとどうなるか。
最近のニュースや調査でも、中小の飲食店を中心に倒産件数が増加しているというデータが出ています。
もちろん、原因は物価高だけではありませんが、「じわじわと利益を削られ続けた結果、資金がもたなくなる」 ケースは確実に増えています。
怖いのは、これが「ある日突然の大赤字」という形ではなく、
・少しずつ利益が減る
・キャッシュが少しずつ減る
・気づいたときには、もう打てる手が限られている
というパターンになりやすいことです。
仕入れ業者との支払い条件が悪化したり、金融機関との関係がぎくしゃくしたりといった“外から見えないところ”で、少しずつ首が締まっていくイメージに近いかもしれません。
だからこそ、この記事の後半で扱う「数字の見方」「コスト改善」「値上げ戦略」 を、早い段階で実行できるかどうかが大きな分かれ目になります。
3-4:中小飲食店の“二極化”と淘汰
物価高の中で、飲食店の世界は少しずつ二極化しています。
一方のグループは、
・数字を定期的に確認し
・原価、人件費、価格を見直し
・リピート対策やデジタルツールを活用している店
もう一方のグループは、
・「なんとかなるだろう」と現状維持にとどまり
・値上げを先送りし
・数字を見ないまま、目の前の忙しさだけに対応している店
です。
前者は、たとえ物価高の影響を受けても、早い段階で対策を打つことで、“生き残る側”“むしろ強くなる側” に回っていきます。
後者は、我慢を続けた結果、気づいたときには体力が尽きてしまう──というリスクを抱えています。
ここまで読んでくださっているあなたは、間違いなく前者になれる素地を持っています。
このあと続く、
・FLコストや損益分岐点の具体的な見方
・今すぐできる物価高対策
・客離れを防ぐ値上げのやり方
・2026年以降を見据えた経営の視点
を、あなたの店に置き換えながら読み進めていただければと思います。
4:数字で押さえる!FLコスト管理と損益分岐点【経営者の必須基礎】

飲食店経営を語るうえで、「数字が苦手だから…」と避けてしまう方は少なくありません。しかし、物価高が続く今こそ、数字に向き合うことが“生き残る店”になるための分岐点です。
特に重要なのが FLコスト(食材+人件費) と 損益分岐点(トントンになる売上ライン) の2つです。この章では、経営に必須の数字の見方を分かりやすく整理します。
4-1:FLコストとは?理想の目安と現状とのギャップ
FLコストとは、「食材費(Food)」と「人件費(Labor)」を合算した数値のこと。多くの飲食店では、総売上に対して 55〜60%前後 を目安に運営されています。
しかし、最近の物価高・最低賃金上昇・人手不足を背景に、「気づけば FL が65%を超えていた」という店が増えています。
FLコストは数%上がるだけでも、月次・年次の利益を大きく削ります。例えば、月商300万円の店でFLが3%悪化すると、年間で100万円以上の利益が失われる計算になります。
まずは、紙でもスマホでもExcelでも構いません。以下の計算を一度やってみてください。
FLコスト = 食材費+人件費 ÷ 売上 × 100
この数字を毎月確認するだけでも、利益の“漏れ”を早期に発見できます。
数字を見ない経営は、スピードメーターなしで車を運転しているようなもの。物価高の時代には、少し危険すぎます。
4-2:損益分岐点の考え方と計算ステップ
損益分岐点とは、「黒字か赤字かの境界線」です。
人間で言えば“健康診断の基準値”のようなもの。
この仕組みは決して難しくありません。要点は次の2つだけです。
↓
・固定費(家賃・人件費の一部・水道光熱費の基本料金など)
・変動費(食材費・消耗品など、売上に比例して増減する費用)
損益分岐点の計算は、次のように求められます
↓
損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ 限界利益率
(限界利益率 = 1 − 変動費率)
例えば、あなたの店の「1ヶ月あたりトントンになる売上」が280万円 → 310万円に上がっているとしたら…それは物価高がじわじわと店の体力を奪っている確実なサインです。
多くの経営者は「忙しく働いているのに、なぜか利益が残らない」という違和感を抱えています。その原因の多くは、この損益分岐点の上昇にあります。
4-3:赤字を防ぐための日々のチェックポイント
数字を把握するのは、一度だけでは意味がありません。赤字を防ぐには “定期的な健康診断” が必要です。
最低限、次の数字だけは毎月チェックしてください。
・売上
・食材原価率
・人件費率
・FLコスト
・損益分岐点との差
これだけで「どこの数字が悪化しているか」が一目でわかるようになります。
さらに、POSや会計ソフトを使えば自動化できますし、あなたのように公式アプリを導入している店なら、会員データや時間帯別売上を把握することで、より正確な運営判断が可能になります。
『数字を見れるようになる=お金を守れるようになる』
これは飲食店経営における大きな武器です。
5:飲食店が今すぐできる物価高対策【原価・価格・人件費・販促】
ここからは、数字を踏まえたうえで“具体的に何をすべきか”を解説していきます。
物価高の時代でも伸びている飲食店には、共通したポイントがあります。それは、難しいことより “すぐできること”から手を付けている ことです。
1つずつ積み上げることで、1〜2ヶ月後には確実に利益の改善が体感できます。
5-1:食材・仕入れコストの見直し
物価高の影響が最も直撃するのが「仕入れコスト」です。
ただし、仕入れは見直せば即効性があります。
・複数業者に見積を取り直す
・ 地元市場・農家・卸との直接取引を検討する
・ 共同購入や業態仲間とまとめ買いをする
・ 在庫管理を見直し、廃棄ロスを減らす
特に在庫管理の改善は効果が大きく、「1日1,500円の廃棄削減 → 年間50万円の改善」は珍しくありません。
物価高対策は“買い方の見直し”から始まります。
5-2:原価率改善とメニュー再設計
次に取り組むべきは、メニューの見直しです。
多くの店は、気づけば「原価の高いメニュー」や「ほとんど出ないメニュー」を抱えたままになっています。これが利益を圧迫する最大の要因の一つです。
・売れないメニューは思い切って削除
・原価の安い食材で“看板商品”を作る
・旬の食材を活かしてコストダウン
・セットメニューで粗利率を底上げ
など、“利益が残る構成”へと再設計することが重要です。
売上よりも粗利。メニュー改善は、店の利益体質を作る最大の武器です。
5-3:商品価格の調整と値上げ戦略
物価高の時代において、「値上げ」は経営を守るための必須手段です。
ですが、ただ上げればいいわけではありません。
成功する値上げにはいくつかの共通点があります。
・一律ではなく、上昇幅の大きい食材から優先して調整
・心理的価格や端数処理を考慮(980円 → 1,080円 など)
・値上げ理由を丁寧に伝え、納得感を生む
・値上げと同時に“体験価値”を高める
特に最後の「体験価値を高める」は、非常に効果的です。
盛り付け、接客、スピード、メニュー表の改善。これらは原価を増やさずに満足度を上げられるため、値上げ後の顧客離れを防ぐ強力な武器になります。
5-4:人件費率の改善と働きやすい職場づくり
人件費の上昇は避けられない時代に入っています。
だからこそ、“削る”のではなく “生産性を上げる” 方向で対策を行うべきです。
・動線・仕込み・オペレーションを見直し、ムダをなくす
・多能工化で、少人数でも回せる体制をつくる
・シフト管理アプリでコストを最適化
・働きやすさを整えて定着率を上げる
「働きやすさ」は人件費対策に直結します。
定着率が上がれば、採用コスト・教育コストが減り、結果的に人件費は安定します。
5-5:販促活動の強化と新たな収益源の開拓
原価高騰の今こそ、最も力を入れるべきは“既存客の再来店”です。
・SNSでの情報発信
・公式アプリやLINEでクーポン・ニュースを届ける
・季節限定メニューやフェアで話題をつくる
・コース料理・飲み放題で客単価を上げる
さらに、テイクアウト・デリバリー・通販・仕出し・サブスクなど“店内に依存しない収益源”を持つことで、物価高の波を受けにくい経営が可能になります。
5-6:デジタルツール活用で“省人化+見える化”
今の飲食店にとって、デジタル化は“贅沢”ではなく“生き残るための必須戦略”です。
・POSで売れ筋・死に筋を可視化
・在庫管理アプリで廃棄ロスを削減
・予約管理システムでドタキャン削減・来店予測
・シフト管理アプリで人件費の最適化
・公式アプリで既存客のLTVを最大化
6:値上げで客離れを防ぐための具体ポイント【事例付き】

物価高が続く今、飲食店にとって「値上げ」は避けられないテーマになりました。しかし、値上げをしたお店のすべてが客離れしているわけではありません。むしろ、正しく伝え、正しいタイミングで、正しい形で値上げした店ほど、理解され、応援され、結果的に売上を伸ばしています。
大切なのは「値上げそのもの」ではなく、「どう伝え、どう体験として提供するか」 です。この章では、客離れを最小限に抑え、むしろ“支持される値上げ”を実現するためのポイントを解説します。
6-1:値上げ時に押さえるべき3つのポイント
ポイント① 理由を正直かつ丁寧に伝えること
お客様もニュースや日々の買い物を通して「物価高」を肌で感じています。しかし、原材料や光熱費、人件費がどれほど上がっているかまでは知りません。
「小麦は前年比◯%上昇」「電気代が過去最高水準」「物流費・人件費の上昇」など、具体的な背景を“短く・丁寧に”伝えるだけで納得感は大きく変わります。
大切なのは言い訳ではなく、「品質を維持するために必要な判断でした」という姿勢です。誠実な説明は、信頼につながります。
ポイント② 値上げのタイミングは“戦略”で決まる
同じ値上げでも、タイミングによってお客様の印象は大きく変わります。
人が「変化を受け入れやすい瞬間」を選ぶことで、自然な値上げに見せることができます。例えば、新メニューを導入したタイミングや、メニューリニューアル時、周年イベントと合わせたタイミングは、値上げを比較的受け入れてもらいやすいタイミングです。
逆に、明らかにお客様が減っている時期に値上げすると、「苦しいから値上げしたんだな」と捉えられ、店の弱さが透けてしまい逆効果です。
『値上げ=飲食体験のアップデート』として伝えることが成功の鍵です。
ポイント③ 値上げと同時に“プラスの変化”を届ける
お客様の心理として、値上げにはどうしてもマイナスの印象が伴います。その印象を打ち消すのが「プラスの変化」です。
・盛り付けが少し美しくなる
・提供スピードが速くなる
・接客が丁寧になる
・お皿やグラスが新しくなる
・メニュー表が見やすくなる
こうした“小さな改善”でも、お客様は敏感に気づきます。
「値上げしたけど、前より満足度が高い」と感じてもらえれば、お客さま離れは起きません。
値上げは、サービス品質をもう一段引き上げるためのきっかけでもあるのです。
6-2:ロイヤルティプログラムで“納得感”を生む仕組みをつくる
値上げ後の客離れを防ぐための最も効果的な方法が、“ロイヤルティプログラム(会員制度・ポイント制度)” の整備です。
お客様にとって重要なのは「価格」そのものではなく、“この店は自分を大切にしてくれているか” という感情です。
たとえば、公式アプリ・ポイントカード・LINE会員などで、
・来店ポイント
・誕生日メッセージ
・アプリ会員限定の特典
・値上げ時のフォロークーポン
・来店回数に応じた優待
などの仕組みがあると、お客様は「値上げ後も通う理由」を見出しやすくなります。

特に私たちが提供する飲食店公式アプリ開発サービス「レストランスター」は、
・誕生日メッセージ
・再来店クーポン
・既存客へのプッシュ通知
・会員データに基づくLTV向上施策
など、「値上げの理解を促しながら再来店を促す」という価値を提供できます。
値上げに不安な飲食店こそ、こうした仕組みを整えることで、価格以上の“満足価値”をお客様に届けられるようになります。
詳しくは資料をダウンロードしていただくか、お気軽にお問合せください。
必要事項をご記入ください。
すぐに下記の詳細資料がダウンロードできます。
プライバシーポリシーをご確認、ご同意の上、「同意して送信」ボタンを押してください。
※アクティブ・メディア株式会社から最新のお知らせなどお送りすることがあります。
![]() システム概要の資料:飲食店公式アプリ作成サービス
システム概要の資料:飲食店公式アプリ作成サービス
レストラン★スター

ダウンロード
- 内容
-
- 機能①事前販売・決済の機能
- 機能②ポイントカードをDX
- 機能③リピート販促を自動化
- 機能④アンケートでQSC改善
- 機能⑤投げ銭でES向上
- 運用サポートが私たちの強み etc.
![]() 販促事例の資料:アプリのQSCアンケートを活用した販促
販促事例の資料:アプリのQSCアンケートを活用した販促

ダウンロード
- 内容
-
- QSCアンケート機能の特徴
- 紙のアンケート・覆面調査との比較
- 成功事例(日本酒原価酒蔵様)
- アンケート機能の活用例
- 分析データの活用例 etc.
![]() アプリ導入インタビュー・事例集
アプリ導入インタビュー・事例集
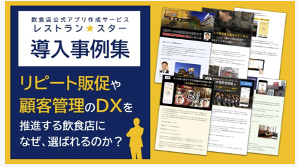
ダウンロード
- 内容
-
- 屋台屋 博多劇場 様
- INGS(CONA、焼売のジョー) 様
- ステーキのあさくま様
- 0秒レモンサワーⓇときわ亭様
- 日本酒原価酒蔵 様
- スター食堂 様
- 金剛園 様 etc.
7:2026年以降を生き抜く飲食店経営戦略
物価高は今だけの問題ではありません。
2026年以降も続く“新しい経営環境”です。
だからこそ大切なのは、短期的な節約ではなく、中長期で利益の出る店づくりに舵を切ることです。この章では、これからの飲食店が持つべき視点と、実際に取り組むべき戦略をまとめます。
7-1:これから求められるのは「視点の転換」
多くの経営者が抱いている最大の誤解が、「物価が落ち着けば、原価も戻るのでは?」という期待です。
しかし現実には、世界的なエネルギー高や物流の逼迫、人件費の上昇など、構造的な値上がり要因はすぐには解消しません。
つまり、“低原価に戻る未来”を前提に経営を考えるのは危険 です。
これから求められるのは、“高原価でも利益の出る店づくり” という発想に変えること。
そのためには、
・LTV(顧客生涯価値)
・会員数
・再来店率
・スタッフ定着率
・デジタル化による生産性
など、短期の売上よりも「無形資産」を重視する経営へ移行することが欠かせません。
7-2:物価高は“ピンチ”ではなく“チャンス”になる
物価高は確かに厳しい環境ですが、一方で“淘汰のスピードが早まる”局面でもあります。
対策を早く打てた店舗ほど、地域でのポジションを確固たるものにできます。
実際に、最近の成功店には共通点があります。
・専門性を高め、安さで競わない
・地域密着型でファン化に成功している
・デジタル活用で再来店率が高い
・メニュー価値や体験価値を磨いている
物価高の時期にこそ、“価値で選ばれる店”へシフトするチャンスがあるのです。
値上げは悪ではなく、店を長く続け、品質を守り、お客様に良い体験を提供し続けるための“投資”です。
7-3:今日から始めるアクションリスト
最後に、明日からでも実践できる一歩を整理します。
すべてやる必要はありません。まずは一つだけで十分です。
・自店のFLコストと損益分岐点を計算する
・原価の高いメニューを洗い出す
・一つだけでいいので仕入れ先を比較する
・スタッフと「働きやすさ」と「ムダ削減」について話し合う
・既存客向けに簡単なキャンペーンを企画する
・値上げ説明文を一度作っておく
・公式アプリやポイント制度の活用を検討する
行動を始めた店から、未来が変わります。
物価高は確かに厳しい環境ですが、“数字・仕組み・顧客価値” をしっかり整えた店は必ず生き残れます。
そして今の取り組みは、「物価高に振り回される店」から「物価高でも選ばれる店」へ変わる第一歩になります。
本記事の内容があなたの飲食店経営のヒントに少しでもしていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。