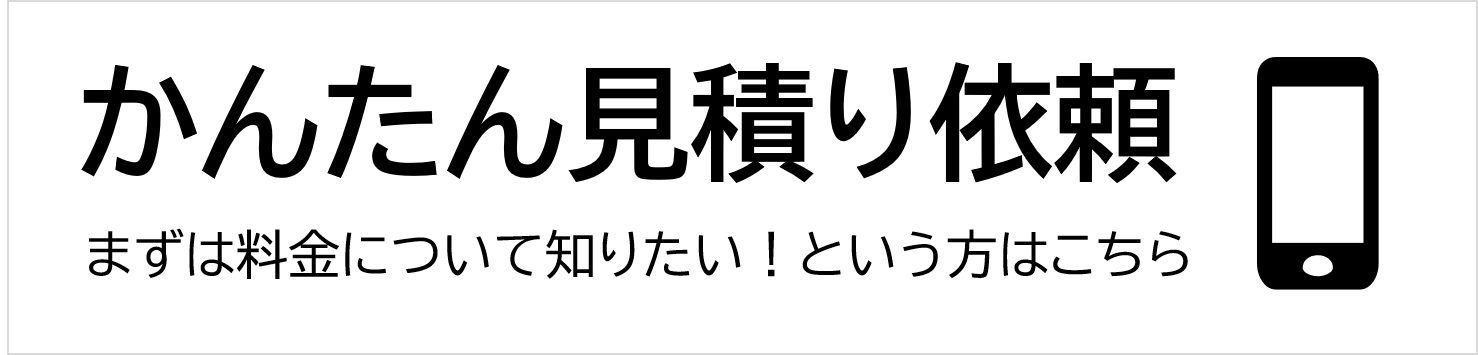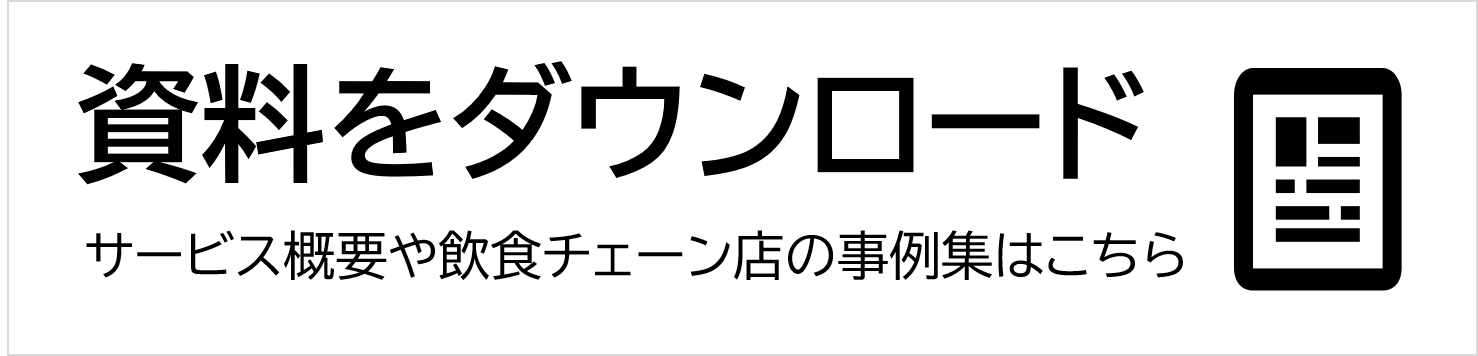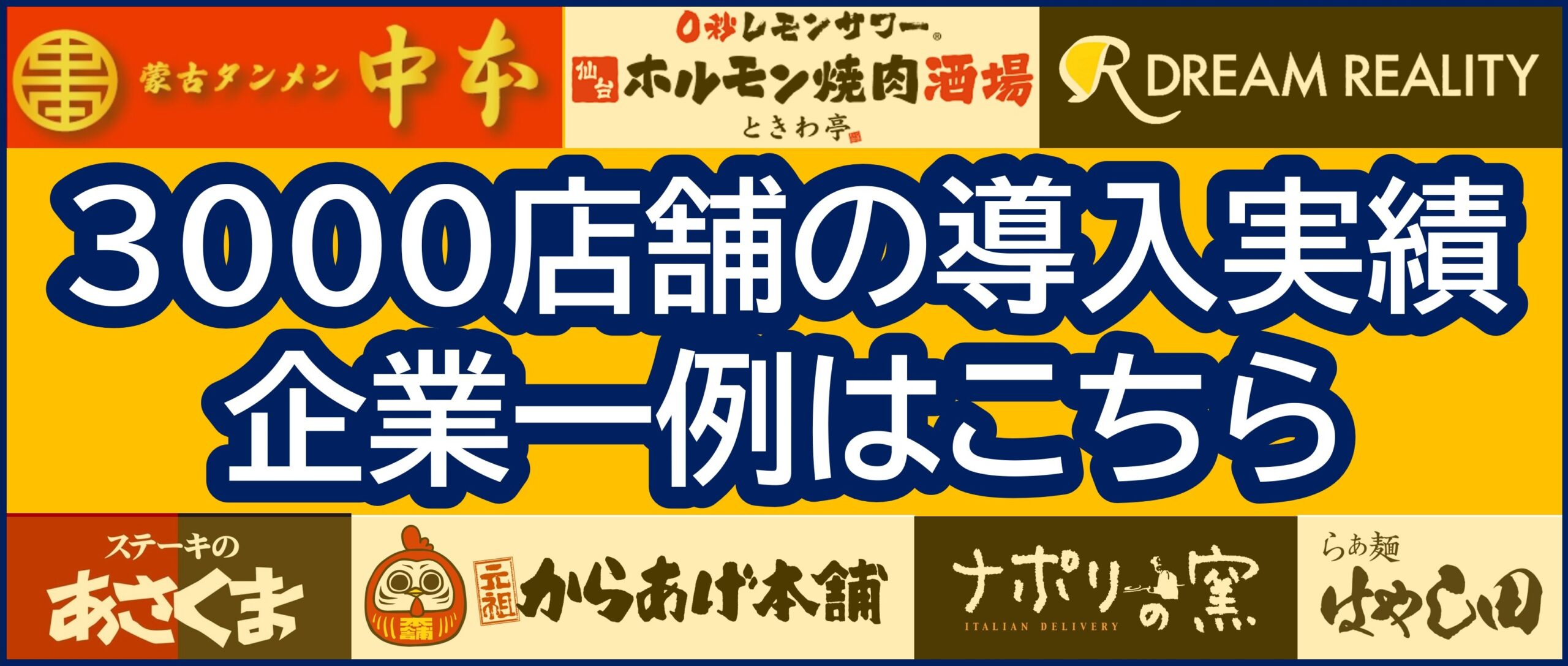【2025年最新】これから伸びる飲食店の特徴・トレンド・業態10選
飲食業界は急速に進化しています。「これから伸びる飲食店」とは、単に美味しい料理を提供するだけでなく、時代のニーズを捉えた新しい価値を生み出す店舗です。
この記事では、2025年に注目すべきこれから伸びる飲食店の特徴やトレンドを詳解し、成功に必要な要素を明らかにします。
SNSで話題になる店や健康志向を満たす店、さらにはサステナブルな取り組みを行う店など、これから伸びる飲食店の要点を押さえることで、あなたのビジネスの未来を切り開くヒントを得られます。
共感を呼び、選ばれる理由を築くことで、飲食店経営の成功を目指しませんか?
この先、どのような飲食業態が成長するのか、そしてその背景にある戦略を知ることで、あなたの店舗も「これから伸びる飲食店」へと成長するチャンスをつかむことができますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1. これから伸びる飲食店とは?【時代が求める変化を先読み】
2025年、飲食店を取り巻く環境は大きく変化しています。物価高や人手不足といった課題が続く一方で、外食へのニーズそのものが消えることはありません。ただし、これから伸びる飲食店は、単に「美味しい」だけでは通用しなくなっています。
キーワードは、「共感」「効率化」「多様性」「体験」です。
消費者はその店を選ぶ“理由”を求めており、「なんとなく入った店」ではなく「行く意味がある店」に惹かれる傾向が強まっています。さらに、SNSやレビューサイトの影響力も無視できず、「紹介されやすい設計」「語りたくなる体験」が重要な時代となっています。
そのため、これから伸びる飲食店には「ターゲット明確化」「ブランドの一貫性」「価値訴求の強さ」など、従来とは異なる“企画力”が求められるようになっています。
2. これから伸びる飲食店に共通する5つの特徴

これからの時代に伸びる飲食店には、いくつかの明確な共通点があります。ただ料理が美味しい、立地が良いというだけでは差別化が難しく、5つの要素を意識して設計されているかがカギになります。
2-1. SNSで映える/話題にしやすい
InstagramやTikTokをはじめとするSNSは、若年層を中心に店舗選びの判断材料になっています。メニューの見た目や店内の雰囲気、写真を撮りたくなるポイントなど、「シェアしたくなる要素」があるかが重要です。映えるだけでなく、ストーリー性や世界観を持つことで話題性が高まります。
2-2. 健康志向・代替食品への対応
近年、健康を意識する層が増加しており、糖質オフ・グルテンフリー・プラントベース(植物由来)のメニューを取り入れる店が注目を集めています。特にヴィーガンやベジタリアン対応があると、訪日外国人からの支持も得やすくなります。
2-3. その店でしか体験できない価値
「体験価値」は飲食店の新たな競争軸です。ライブ感のある調理演出や、予約者限定の特別メニュー、セルフ体験など、“思い出に残る体験”がリピーター獲得の決め手になります。ただ食べるだけでなく「行ってよかった」と言われる設計が求められます。
2-4. サステナビリティ・地産地消の意識
エコ意識の高まりとともに、環境に配慮した店舗運営も評価されるようになりました。地元の食材を活用したり、フードロス削減に取り組んだりする姿勢が共感を呼び、他店との差別化につながります。
2-5. 効率的で再現性のある運営モデル
物価高・人手不足の影響を受けにくい業態が伸びている傾向にあります。仕込みや提供オペレーションがシンプルで、少人数でも回せる構造、複数店舗展開に対応できるマニュアル化・システム化など、運営の再現性があるかが重要です。
3. 2025年注目!これから伸びる飲食店業態10選

2025年の飲食業界は「体験・個性・効率」がカギとなる年です。ここでは、これから伸びると注目されている業態を10個ピックアップし、それぞれの特徴と支持される理由を解説します。
3-1. ファストカジュアル店
ファストフードの手軽さと、カフェ・レストランのクオリティを融合した業態。短時間・低価格でありながら、ヘルシーさや素材へのこだわりを訴求できる点が強みです。働く世代や健康志向の若者に支持され、都市部を中心に拡大中です。
3-2. テイクアウト・デリバリー専門店
コロナ禍以降、定着した「持ち帰り・宅配」需要は今も根強く、専門業態としての成長が続いています。店内イートインスペースが不要なため初期投資も少なく、少人数でも回せる点が開業希望者に人気です。
3-3. プラントベース・ビーガン対応店
健康志向だけでなく、環境意識の高まりも背景に、植物性食品を中心とした店が注目されています。海外観光客のニーズとも合致し、インバウンド対策としても有効。従来の飲食店との差別化にもつながります。
3-4. レトロ系専門店(昭和・平成)
Z世代を中心に“懐かしさ”が逆に新しいというトレンドが拡大。昔ながらの喫茶店風内装や、駄菓子・ナポリタン・純喫茶プリンなど、レトロな世界観を再現した店舗はSNS映えとの相性も抜群です。
3-5. ご当地・ローカル食材特化型店
観光や地域活性と連動した「地元特化型」の業態も注目度上昇中。地域ブランド野菜、郷土料理、日本酒など、土地に根ざした食文化を提供することで、旅行者だけでなく地元住民の支持も得られます。
3-6. セルフスタイル飲食店
省人化と効率化の両立を目指し、券売機・セルフ注文・セルフ受取を採用する業態が増加。人手不足に強く、ピークタイムの回転率も上がるため、収益性の高いモデルとして注目されています。
3-7. 会員制・紹介制の高級店
「体験の特別感」と「限定性」を武器にした会員制業態も堅調です。単価は高くても、顧客ロイヤリティが高く、少ない席数で効率よく収益を上げられるのが魅力。富裕層マーケットとの相性も◎。
3-8. ライブキッチン・体験型レストラン
五感を刺激する「調理のライブ感」や「参加型体験」を提供する業態も伸びています。例:目の前で焼くステーキ、寿司の握り体験、手打ちうどん教室つき食事など。思い出に残る時間が共有され、SNSでも拡散されやすいのが特長。
3-9. スイーツ・デザート専門業態
映え系スイーツは依然として強い集客力を持ちます。特に、海外スイーツ(例:クロッフル、エッグワッフルなど)や、季節限定・地域素材を活用した商品が人気。小規模立地でも開業しやすく、原価率も低め。
3-10. 高付加価値型の焼肉・肉バル業態
原材料価格が上がっている中でも、「良いものを少し楽しみたい」ニーズに応える高単価路線は支持を集めています。個室・タッチパネル注文・完全予約制など、コストをコントロールしつつ満足度を高める工夫が重要です。
4. 「これから伸びる飲食店」を実現するためのヒントと戦略
これから伸びる飲食店を目指すには、トレンド業態を真似するだけでは不十分です。「時代の変化に柔軟に対応し、再現性ある仕組みで集客・売上をつくれる店舗」こそが、生き残り続ける飲食店です。ここでは、その実現に向けた具体的な考え方と戦略をご紹介します。
4-1. 「立地×業態」の相性を見極める
飲食店の成功は、業態だけでなく「どこに出店するか」に大きく左右されます。例えば、オフィス街ではランチ特化のファストカジュアル、住宅街ではテイクアウト需要の高い弁当屋が強く、観光地ではご当地感のある体験型店が好まれます。
立地調査では、通行量や競合の有無だけでなく、「ターゲット層のニーズ」と「業態の提供価値」が一致しているかを丁寧に分析しましょう。
4-2. “小さく始めて、数字で伸ばす”が鉄則
これからの飲食店経営では、「経験や勘」よりも「数値で判断する」姿勢が欠かせません。小規模店舗から始め、客数・売上・回転率・顧客属性などをデータで把握し、反応を見ながら改善を重ねるアプローチが成功率を高めます。
特に重要なのは、来店理由や再来店のきっかけとなった要素の把握。アンケートやアプリ・POSのデータ活用により、感覚ではなく根拠ある改善が可能になります。
4-3. “SNS映え”だけでなく“共感性”も重要
今の若い世代は、単なる見た目よりも「共感」や「ストーリー性」に惹かれます。「誰と来たくなるか」「なぜこのお店を応援したくなるか」など、感情に訴える仕掛けが強い集客効果を持ちます。
例えば、地域食材の背景を伝えるストーリー、頑張る店主の想い、SNS上のユーザーとの交流などは、単なる映えよりも記憶に残りやすく、リピーターや紹介を生む要因にもなります。
4-4. DXとアナログの“ハイブリッド設計”がカギ
完全セルフオーダーやアプリ対応だけではなく、心のこもった接客や、手書きのPOPなどアナログ要素もバランス良く組み込むことが重要です。テクノロジーは“便利さ”を、アナログは“人間らしさ”を届ける手段。両者をうまく組み合わせることで、効率と顧客満足の両立が可能になります。
5. フランチャイズでこれから伸びる飲食業態を狙うのもアリ?
飲食業界では、個人開業に加えて「フランチャイズ(FC)」での参入も選択肢として注目されています。特にこれから伸びる業態においては、フランチャイズ展開によってスピード感のある出店と経営ノウハウの享受が可能になります。
5-1. なぜ今、フランチャイズに注目が集まるのか?
【低リスクでの参入が可能】
既に成功モデルが確立されているため、ゼロからコンセプトを考える必要がなく、未経験でも一定の成功確率が期待できます。
【業態トレンドをいち早く取り込める】
本部が市場動向を分析しメニューや販促をアップデートしてくれるため、個人では追いつきにくいトレンドにも対応できます。
【人手不足・DX化に強い仕組み】
最近のFCブランドは、省人化・セルフオーダー・アプリ連携など、時代に合った運営体制が整っており、現場負担が少ないのも特長です。
5-2. フランチャイズ選びで失敗しないためのポイント
【本部のサポート体制と実績を確認】
マニュアル・研修・販促支援・DX対応などの実力を、実際のオーナーの声などから調査することが重要です。
【契約内容やロイヤリティの比較検討】
収益モデルに無理がないか、初期投資とランニングコストを見極めましょう。加盟金の安さだけで決めると後悔するケースも。
【出店予定エリアとの相性】
伸びている業態でも、地域の属性によってはミスマッチが起きる可能性があります。市場調査と試算を丁寧に行いましょう。
6. まとめ|これから伸びる飲食店は“らしさ”と“共感性”で選ばれる時代へ
これから伸びる飲食店に共通するのは、「他にはない強み(=らしさ)」と、「顧客との心のつながり(=共感性)」を持っていることです。最後にこの記事の内容をまとめます。
6-1. 「売れる業態」ではなく「選ばれる理由」をつくる
・SNSでの拡散、レビュー、紹介――それらはすべて「この店を誰かに教えたい」と思わせる体験があるからこそ生まれます。
・“何を売るか”だけでなく、“なぜ選ばれるのか”を言語化できる店が、今後の時代に強くなります。
・コンセプト、空間、接客、ストーリー――全てに一貫性を持たせて「世界観を届ける店」づくりが求められます。
6-2. 共感・共創・関係性が来店理由になる時代
・食事そのものだけでなく「誰と共有するか」「何を感じられるか」が選択の軸に。
・店舗とお客様の関係は、商品提供者と消費者ではなく、「共感する仲間」や「応援したくなる存在」へと変化しています。
・InstagramやLINEでの発信、ファン向けイベント、メニュー開発の参加型企画など、“関わる余白”がリピートとロイヤル化を生み出します。
6-3. 成功のカギは“変化できる柔軟性”と“継続力”
・どんなに今人気の業態でも、時代が変われば売れなくなる可能性があります。
・大切なのは「変化を捉えて進化する力」と「続けるための地力」。
・データ分析、改善の習慣化、現場スタッフとの連携など、小さな努力の積み重ねが、長く愛される店を育てていきます。
それではこの記事は以上です。
今回の内容があなたの飲食店経営のヒントに少しでもしていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。