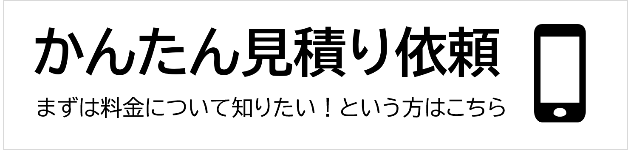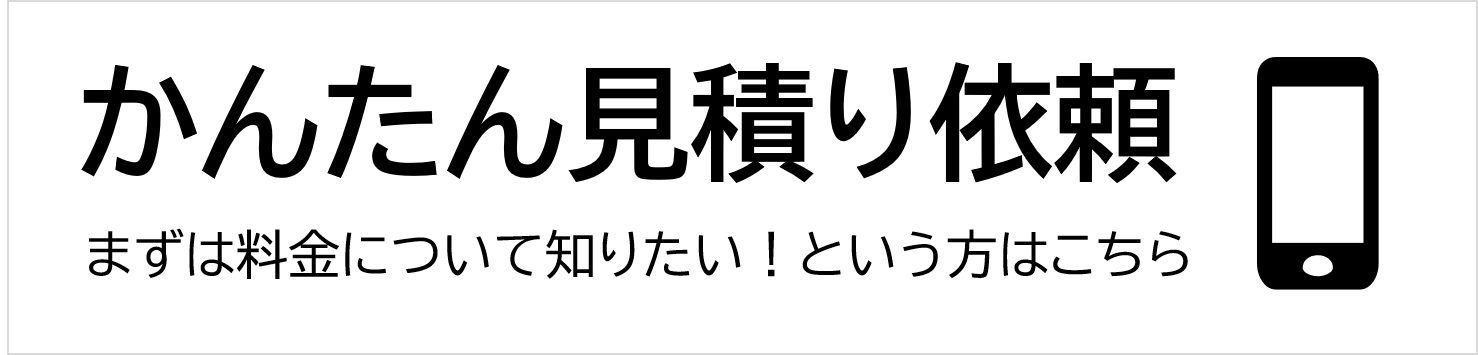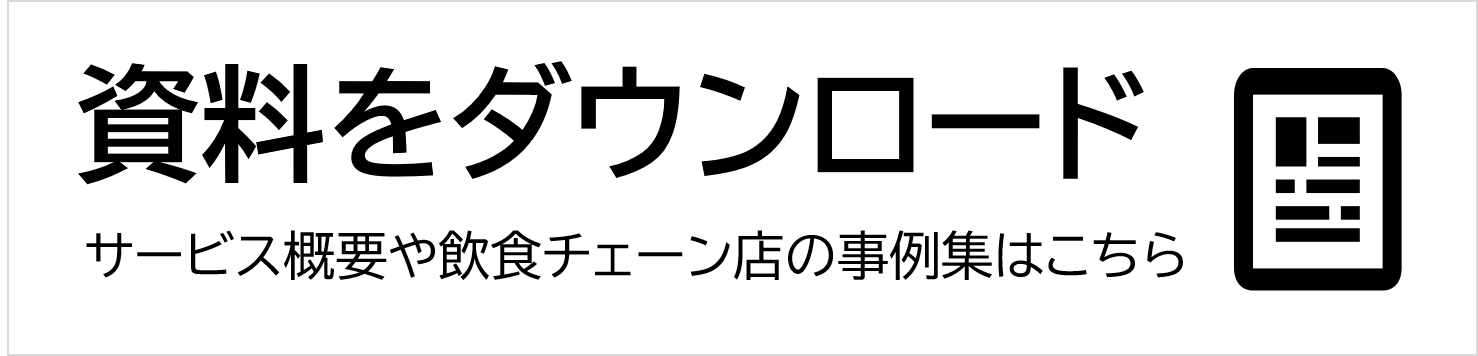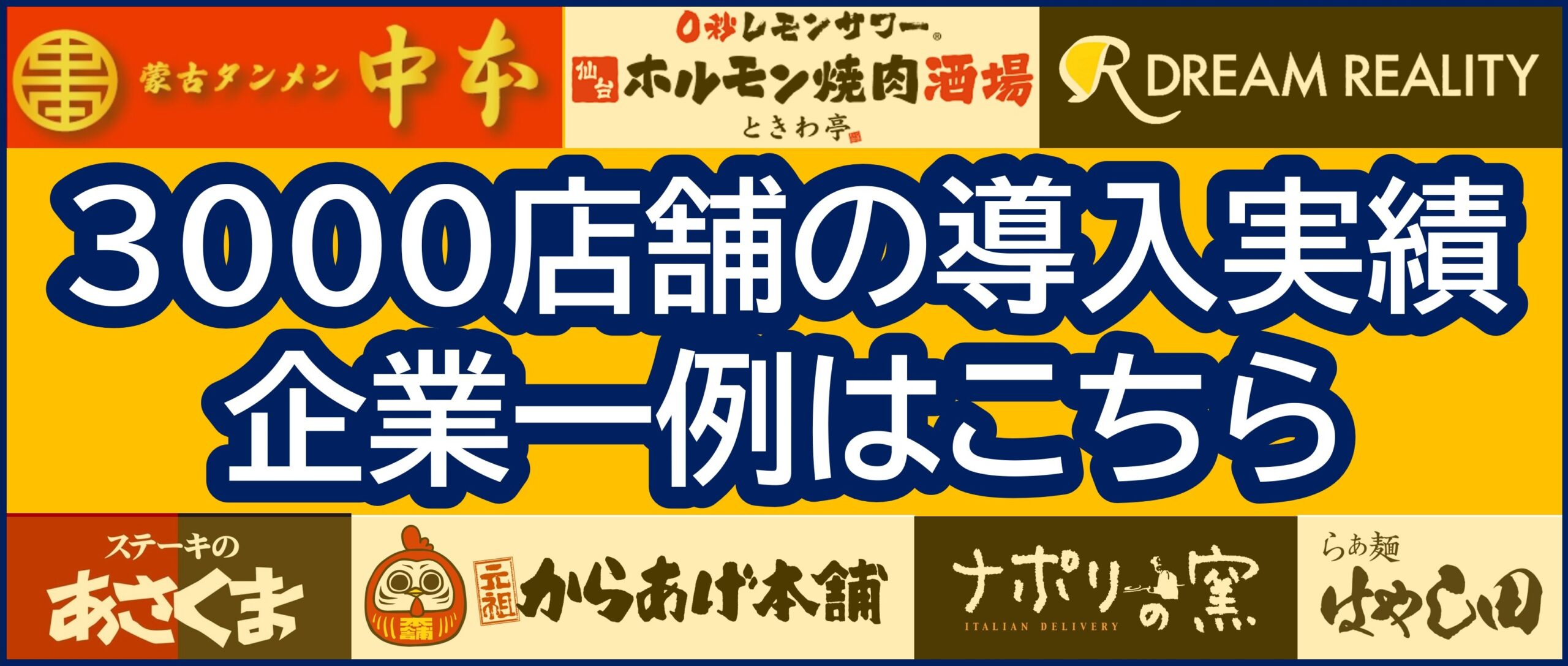【飲食店経営者のための働き方改革ガイド】改善ポイントや成功事例まで徹底解説
飲食店の経営者の皆様、忙しい毎日に追われ、働き方改革の必要性を感じながらも実際の取り組みに踏み切れずにいませんか?外食業界は慢性的な人手不足のため人材確保が急務であると考える方も多いでしょう。
この記事では、飲食店が抱える働き方改革の課題を明らかにし、効率的な改善を図るための具体的なポイントを徹底解説します。
あなたの飲食店に合わせた働き方改革を進めることで得られる労働環境の向上やスタッフのモチベーションアップ、ひいてはお店の利益向上といった大きなメリットを手に入るでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
目次
1:飲食店における働き方改革とは?
「働き方改革」とは、長時間労働の是正や多様な働き方の実現、公正な待遇確保を目的とした国の方針です。製造業やオフィスワークの現場で注目されがちですが、実は飲食業界こそ改革が急務とされています。
その背景には、人材不足や高い離職率があります。飲食店は営業時間が長く、繁忙期と閑散期の差も激しいため、労働時間や休暇制度が不安定になりがちです。こうした状況は「ブラック飲食」と揶揄され、若い世代の就職希望者が減る原因にもなっています。
経営者にとって「働きやすい職場づくり」は、単なるイメージ改善にとどまらず、店舗の存続や競争力を左右する経営課題と言えるでしょう。
2:飲食店の労働環境の現状と課題

飲食店における労働環境は、他業種に比べて厳しい側面が多くあります。
まず、長時間労働の常態化です。営業時間が長く、仕込みや片付けまで含めると1日の拘束時間が非常に長くなり、残業が常習化しやすい状況にあります。
さらに、週休2日や連休の取得が難しい点も問題です。繁忙期には休みを取りづらく、長期休暇制度が形だけになっている店も少なくありません。
また、労働対価としての給与水準が低いことも、人材流出を加速させる要因です。従業員が「労働に見合わない」と感じると、モチベーションは下がり、定着率の低下につながります。
結果として「飲食業界=ブラック」という負のイメージが社会に根づき、採用難をさらに深刻化させています。
3:働き方改革関連法と飲食店が守るべきルール
近年、働き方改革を後押しする法改正が次々と施行されています。飲食店経営者にとっても無関係ではなく、違反すれば罰則やブランドイメージの低下につながりかねません。
代表的なものは「時間外労働の上限規制」です。原則として月45時間、年360時間までとされ、特別条項があっても無制限な残業は認められません。
また、「年次有給休暇の取得義務化」により、特定の従業員に対して年5日の有休を付与・取得させることが義務づけられました。
「勤務間インターバル制度」も推奨されています。終業から次の始業までに一定の休息時間を確保するもので、過労防止に有効です。
さらに「同一労働同一賃金」によって、正社員と非正規雇用の待遇差をなくすことが求められています。
これに加えて、社会保険の適用拡大、インボイス制度、パワハラ防止法など経営に直結する法改正も進んでおり、経営者は常に最新情報を把握する必要があります。
4:飲食店が取り組むべき働き方改革の施策

働き方改革は「法律に従うため」だけでなく、人材不足時代を乗り越えるための経営戦略です。ここでは、飲食店が現場で取り組める具体策を紹介します。
4-1:労働時間の見直しと残業削減
飲食業界では「営業時間が長い=売上が増える」と考えがちですが、長時間労働は人材流出を招きます。営業時間を短縮したり、深夜営業を見直したりすることで、従業員の負担は大幅に軽減されます。
また、残業前提のシフトをやめ、必要な人員をピークタイムに集中させる仕組みに変更することも重要です。例えば、ランチとディナーの間のアイドルタイムを一時閉店にするだけでも、スタッフの休憩確保や人件費削減につながります。
長時間働かせるのではなく、短時間で成果を出す「効率の良い働き方」を店舗文化として根づかせましょう。
4-2:シフト制度・有給休暇制度の改善
「休みが取れないから飲食業を辞めた」という声は非常に多いです。これは人材不足を悪化させる最大の要因でもあります。
週休2日制の導入や連休取得の仕組みをつくれば、応募者にとって魅力的な求人になります。また、有給休暇についても「取りたければ取っていい」ではなく「必ず年5日は取らせる」仕組みにしなければなりません。
有給取得率を掲示板や社内アプリで可視化すると、スタッフ同士が「自分も取ろう」と思いやすくなります。結果的に、制度を実際に活用する文化が根づいていきます。
4-3:評価制度・福利厚生の整備
飲食店では「頑張っても評価されない」「昇給の基準が不透明」といった不満が溜まりやすい傾向があります。これを放置するとモチベーションが下がり、離職率の上昇を招きます。
まずは、成果や貢献を数値で可視化する仕組みを整えることが重要です。売上貢献度だけでなく、接客態度・チームワーク・お客様アンケート結果など多面的に評価する制度を導入しましょう。
さらに、福利厚生の充実も大きな効果を持ちます。食事補助や交通費支給に加え、誕生日休暇や家族手当などを導入すれば、従業員に「大切にされている」という実感を持ってもらえます。
4-4:教育・研修制度の強化
教育は「即戦力を育てる」だけでなく、従業員が自分の成長を実感できる仕組みでもあります。
新人研修やマニュアル整備により、現場での業務効率が上がるだけでなく、指導する側の負担も軽減されます。接客スキル研修や調理研修に加えて、リーダー層向けにマネジメント研修を行えば、店全体の運営力が底上げされます。
また、外部セミナーやオンライン講座を活用することで「飲食店で働きながらスキルアップできる環境」を整備できます。教育はコストではなく投資であり、従業員定着率を高める最も有効な手段です。
4-5:ITツール導入による効率化を通じた働き方改革
テクノロジーは「人を減らす」ためだけではなく、「人がやりがいを持てる環境をつくる」ための武器です。
POSレジや勤怠管理システムを導入すれば、店長の事務作業が大幅に削減されます。さらに、配膳ロボットやセルフオーダーシステムの活用で、ホールスタッフの負担を軽減し、接客の質に集中できるようになります。
また、特に効果的なのは、アプリによる顧客アンケートの活用です。従業員が「自分の接客が評価されている」と実感すれば、モチベーションは確実に上がります。そのフィードバックを教育や評価制度に反映させることで、サービス改善の好循環が生まれます。詳しくは後ほど私たちの成功事例をお伝えいたします。
4-6:多様性ある働き方(時短勤務・副業容認など)
少子高齢化が進む中で、「フルタイムで働ける若者だけに頼る経営」は現実的ではありません。
子育て中のスタッフが働ける短時間勤務制度や、介護と両立できる柔軟な勤務体系を整えることで、多様な人材が集まります。
また、副業や兼業を認めることで「飲食業=自由度が低い」というイメージを払拭できます。さらに、外国人スタッフやシニア人材の受け入れを進めれば、人材確保の幅が一気に広がります。
多様性を受け入れる職場は、結果的に「長く働ける環境」につながり、採用・定着の両面で大きな効果を発揮します。
5:実際の取り組み成功事例
働き方改革は「理想論」ではなく、すでに多くの飲食店で取り組まれている“現実的な戦略”です。ここでは有名事例から、中小飲食店でも応用できるヒントを紹介します。
飲食店の働き方改革の成功事例1:ロイヤルホストさん「24時間営業の廃止」
かつて外食産業を象徴するように広がった「24時間営業」。しかし、ロイヤルホストさんは2017年に24時間営業を廃止しました。背景には、深夜帯の売上が人件費や光熱費に見合わなくなっていたこと、そして従業員の健康とワークライフバランスを守る必要性がありました。
結果として、従業員の休息時間が確保され、定着率が向上。さらに「ホワイト企業イメージ」がついたことで新規採用にもプラスに働きました。営業時間を短縮しても、売上が大きく落ち込むことはなく、むしろ効率的な経営につながった事例です。
飲食店の働き方改革の成功事例2:日本酒原価酒蔵さん「顧客アンケートでES向上」

私たちのアプリを導入中の居酒屋チェーン店「日本酒原価酒蔵」さんでは、アプリで顧客にアンケートを実施。その中でスタッフを褒めていただいているコメントを抜き出して、同スタッフに共有。スタッフのモチベーションUPに繋げています。
さらに、アンケートの評価点数をスタッフの教育や評価制度にも導入していることで、従業員も会社からの自分に対する評価に「お客様の声」や具体的数値が反映されますので、納得度が高くなります。
結果的に顧客アンケートをES(従業員満足度)向上に活用されています。
実際にどのように活用されているのか?など、詳しくはアプリサービスと共にご共有可能です。詳しくは以下の資料をダウンロードしていただくか、お気軽にお問合せください。
↓ ↓ ↓
飲食店の働き方改革の成功事例3:日高屋さん「配膳ロボットで効率化」

関東圏に400店舗以上を出店する人気中華チェーン店の「日高屋」さんでは、USENの配膳ロボットを導入しました。スタッフが注文を受けた後、料理をロボットが客席まで運ぶ仕組みです。これによりホールスタッフの負担が大幅に軽減され、接客やリピーター対応に集中できる環境が整いました。
導入には初期投資が必要ですが、長期的には人件費削減とサービス品質向上の両立が可能となり、現場スタッフの働きやすさにもつながっています。
※詳しくはUSENさんの配膳ロボット導入事例記事をご覧ください(https://usen.com/case/robot/hidakaya_meguro.html)
※また、弊社では配膳ロボットの正規代理店となっておりますので、ご関心のある方はお気軽にお問合せください。
提供:アクティブ・メディア株式会社(USEN配膳ロボット正規パートナー企業)
開発元・サポート:株式会社USEN-NEXT HOLDINGS
↓ ↓ ↓
中小飲食店で働き方改革の成功事例を応用できるヒント
「うちは大手じゃないから難しい」と感じるかもしれませんが、工夫次第で中小店舗にも応用可能です。例えば:
営業時間の短縮:深夜営業をやめて定休日を設ける
完全予約制の導入:来店数をコントロールし、過剰労働を防ぐ
小規模IT導入:モバイルオーダー、会員証アプリ、配膳ロボット
これらはどれも大きなコストをかけずに始められる施策であり、現場の負担を減らす効果は十分に期待できます。
6:働き方改革がもたらすメリット
働き方改革は「従業員のため」だけのものではありません。経営者にとっても、長期的な利益や安定経営につながる多くのメリットがあります。
6-1. 人材定着率の向上と採用コスト削減
飲食業界では、年間離職率が25%を超える(厚生労働省による令和3年雇用動向調査の「産業別入職・離職」の結果より)と言われています。新人が定着しないと、採用・教育コストが膨らみ続け、利益を圧迫します。
しかし、労働時間を見直し、休日を確保すれば「辞めない従業員」が増えます。例えば、有給取得率が50%以上の店舗では離職率が半分以下になったという調査結果もあります。長く働いてくれるスタッフは店の文化を育み、新人教育の負担も軽減します。
6-2. 採用力の強化と飲食店のブランド価値向上
「飲食業界=ブラック」というイメージを持っている人も少なくありません。そのイメージを払拭できれば、求人応募数は確実に増加します。
特に、求人票で「完全週休2日制」「有給取得率70%」といった数値を明示すれば、それだけで他店との差別化が可能です。最近では「働き方を改善している飲食店」がSNSや口コミで話題になり、採用ブランディングに直結するケースもあります。
6-3. 顧客満足度の向上
従業員が笑顔で働ける環境は、そのまま接客や料理の質に反映されます。疲弊したスタッフが無理に働くよりも、余裕を持って接客する方がお客様は安心し、再来店につながります。
従業員満足度(ES)と顧客満足度(CS)は密接に関係しており、働きやすさを改善することは「売上改善の近道」とも言えます。
6-4. 飲食店経営の安定化と利益向上
短期的には「人件費が増えるのでは?」と心配する経営者も多いでしょう。しかし、離職率低下による採用コスト削減、リピーター増加による売上安定化は、中長期的に見れば大きな利益につながります。
働き方改革はコストではなく、投資です。人材が安定し、顧客が定着する店舗は、景気や外部環境の変化にも強くなります。
7:働き方改革を進めるためのステップ
「必要なのは分かるけど、何から始めればいいのか分からない」という経営者も多いはずです。ここでは、段階的に進めるための5つのステップを解説します。
7-1. 現状を見える化する
まずは数字を出すことから始めます。
・従業員の平均残業時間
・年間離職率
・有給休暇取得率
これらを定期的に集計し、グラフ化するだけで課題が明確になります。「なんとなく忙しい」ではなく「月平均残業時間〇時間」という事実を把握することが改善の第一歩です。
7-2. 課題に優先順位をつける
課題は山積みでも、一度にすべては改善できません。
例えば「まずは残業削減、次に休日取得」というように優先順位をつけ、段階的に進めます。短期的なゴール(残業20%削減)と長期的なゴール(離職率半減)を設定すると進捗管理がしやすくなります。
7-3. 小さくテスト導入する
いきなり全店舗・全スタッフで改革を行うと現場が混乱します。
まずは「1店舗だけ営業時間を短縮」「一部スタッフだけ有給取得率をチェック」など、小規模にテスト導入しましょう。効果が出れば徐々に横展開していくのが現実的です。
7-4. 従業員の声を反映する
経営者だけが旗を振っても、従業員の理解がなければ失敗します。
定期的にアンケートを実施したり、ミーティングで意見を出してもらったりすることで、現場の納得感が高まります。従業員が「自分たちの声で環境が変わった」と実感すれば、協力体制も強まります。
7-5. 経営者自身の意識を変える
最後に必要なのは経営者の意識改革です。
「長く働く=成果」という古い価値観を捨て、「効率よく成果を出す」ことを評価基準に変えましょう。人件費を削るのではなく、人材に投資して成長を促すことが、長期的に見れば経営の安定につながります。
8:まとめ|飲食店の未来をつくる働き方改革
飲食業界における働き方改革は、単なる流行ではなく「生き残りの必須条件」です。
これまでの「長時間労働・低賃金・休めない」という常識を変えなければ、若い世代は飲食業界を選ばず、優秀な人材は定着しません。結果として、経営そのものが立ち行かなくなるリスクがあります。
一方で、働き方改革を積極的に進めた店舗は「働きたい店」として人材を集め、安定した経営基盤を築いています。従業員が安心して働ける環境は、お客様にも伝わり「また来たい」と思われる店へとつながります。
これからの飲食店経営に求められるのは、単に料理やサービスを提供するだけでなく「働く人の幸せ」まで設計できる経営者です。働き方改革はコストではなく、未来をつくる投資です。今こそ改革に取り組み、自店舗の強みとして打ち出していきましょう。