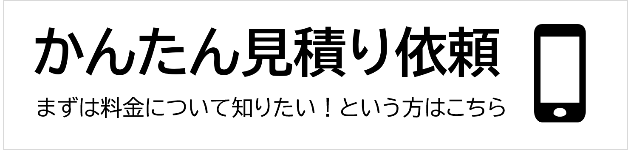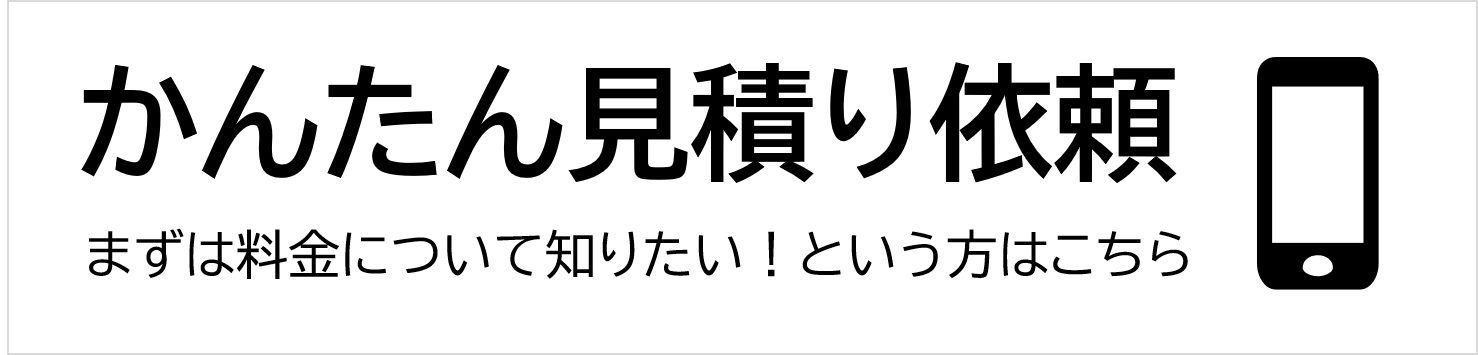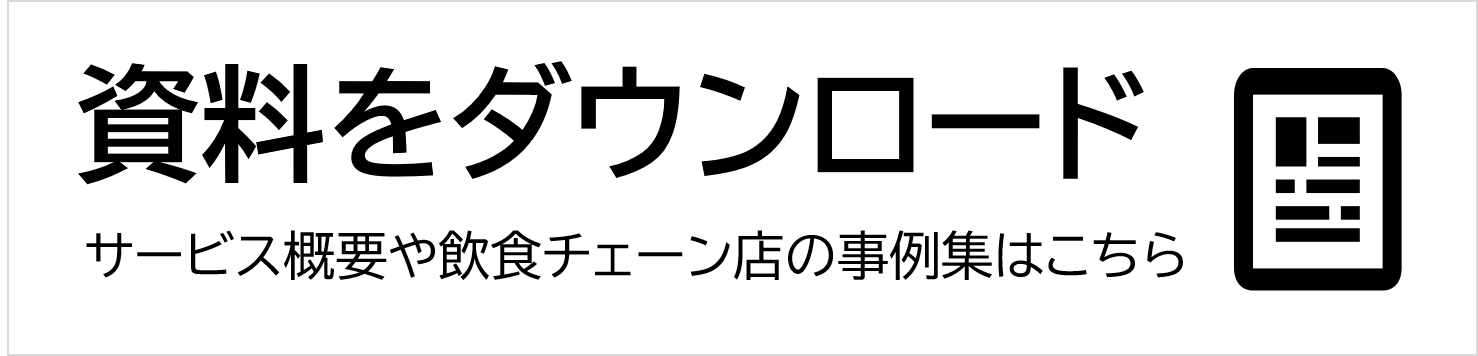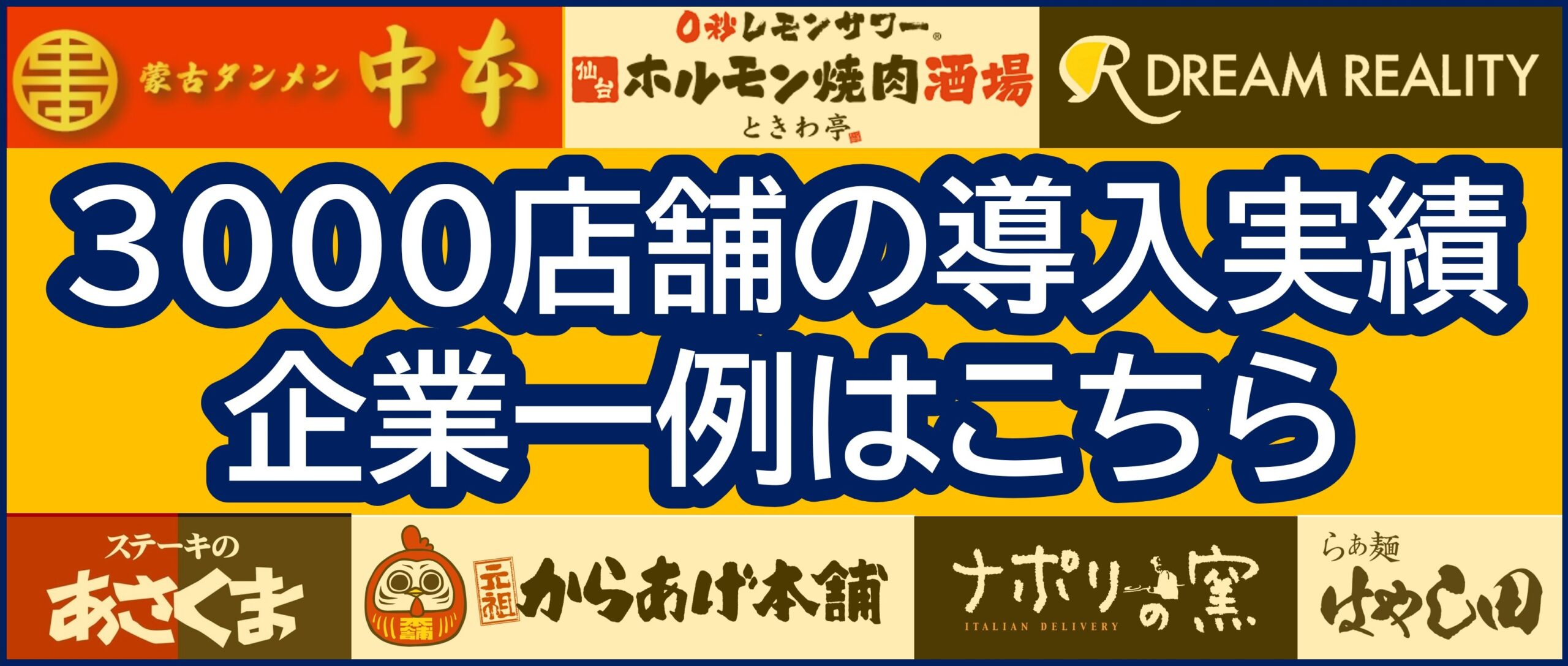【飲食店必見】よくあるトラブル事例と原因、解決策などを徹底解説
飲食店を経営していると避けて通れないのが「トラブル」です。お客様からのクレーム、従業員間の人間関係、予約のキャンセルや設備の故障、さらには近隣住民からの苦情まで、飲食店ならではの多様なトラブルが発生します。これらは店舗の信用や売上に直結するため、正しい知識と対応策を持っておくことが非常に重要です。
本記事では、飲食店で起こりやすいトラブルを「お客様」「従業員」「店舗運営」「外部要因」に分け、それぞれの事例・原因・解決策・予防策を徹底解説します。トラブルを未然に防ぎ、発生時にも冷静かつ迅速に対応できるよう、ぜひ参考にしてください。
目次
1:飲食店で発生するトラブルの全体像
飲食店のトラブルは、大きく以下の4つに分類されます。
・お客様関連(クレーム、客同士のトラブル、物損事故など)
・従業員関連(人間関係、給与、労務問題)
・店舗運営関連(予約、会計、仕入れ、衛生、設備故障)
・外部要因(近隣住民、競合、人手不足、資金繰り)
これらのトラブルを放置すると、店舗の評判が落ちて売上が減少するだけでなく、従業員の離職や法的トラブルに発展するリスクもあります。経営者は「どの領域でどんなトラブルが起きやすいのか」をあらかじめ把握し、準備しておくことが大切です。
2:お客様関連のトラブル事例と対応策

2-1:食品の品質・衛生に関するクレーム
飲食店で最も深刻なトラブルの一つが食品の品質や衛生に関する問題です。異物混入、腐敗、さらには食中毒などはお客様の信頼を大きく損ねます。
発生時には、まず誠実な謝罪と迅速な対応が不可欠です。状況を確認し、原因を明らかにした上で再発防止策を説明することが大切です。例えば「調理器具の清掃不足」や「保管温度の不適切管理」が原因であれば、改善の具体策をその場で伝えることで信頼を回復できます。
予防のためには、日々の衛生管理マニュアルを徹底することが最重要です。従業員への衛生教育や、冷蔵庫・厨房機器の定期点検も欠かせません。
2-2:請求トラブル(誤請求・追加請求)
会計での誤請求や追加請求は、小さなミスに見えて大きなクレームにつながる典型的なトラブルです。
例えば「注文していない料理が加算されていた」ケース。対応としては、事実確認 → 誤りの訂正 → 謝罪 → 再発防止策の提示という流れが基本です。この一連の流れを誠実に行うだけで、店舗の信用は大きく変わります。
防止策としては、POSレジや会計システムの導入が効果的です。また、従業員教育を徹底し、会計時の二重チェックを仕組みに組み込むことも重要です。
2-3:お客様同士のトラブル
店内では、騒音や座席争い、子供の行動や匂いなどが原因でお客様同士のトラブルが起こることがあります。
スタッフはまず冷静に状況を把握し、双方の話を聞き、公平な立場で対応します。小さなことでも感情が高ぶると大きなクレームに発展するため、初動の冷静さがカギです。
予防策としては、店内ルールの掲示や従業員への対応トレーニングが効果的です。また、トラブルが深刻化した場合には、第三者(管理会社や警察)にエスカレーションする判断も必要です。
2-4:従業員とお客様のトラブル
接客ミスや物損事故もよくあるトラブルです。注文間違いや料理の遅延、ドリンクをこぼしてしまうなどが代表例です。
対応としては、即時の謝罪と誠実な補償が第一です。さらに、マニュアルに沿った対応を従業員全員が共有していることで、対応に一貫性を持たせることができます。重大な事故や法的リスクがある場合には、弁護士や保険を活用して対応する体制も整えておきましょう。
3:従業員関連のトラブル事例と対応策

3-1:従業員同士の人間関係
飲食店はチームワークが欠かせない業態ですが、その分「人間関係のトラブル」が頻繁に起こります。代表的なのは シフト調整や業務分担をめぐる不公平感、コミュニケーション不足による誤解などです。これを放置すると、雰囲気悪化→作業効率低下→離職につながり、結果として人手不足が深刻化します。
対応の第一歩は、従業員が安心して相談できる窓口の設置です。第三者的な立場で話を聞き、早期に火消しを行う仕組みを整えましょう。また、定期的なチームミーティングを実施して「普段からの対話の場」を持つことも効果的です。さらに、マニュアル化された問題解決フローを用意しておけば、誰が対応しても一定の基準で公平な対応が可能になります。
3-2:店長/オーナーと従業員の摩擦
従業員と管理者の摩擦もよくあるトラブルです。例えば「曖昧な業務指示で二度手間になる」「評価基準が不透明で昇給に納得できない」など。これが蓄積すると従業員のモチベーションは下がり、最悪の場合は労務トラブルに発展します。
解決のためには、業務マニュアルや評価基準を文書化して共有することが不可欠です。さらに、月1回の面談や1on1を設け、従業員が不満を安心して口にできる環境を整えると効果的です。公平で透明性のある評価制度を導入することで、トラブルの多くは未然に防げます。
3-3:給与・労務トラブル
飲食業界では、有給休暇が取れない、残業代未払い、休業時の補償不足といった労務トラブルが多発しています。これらは放置すると法的リスクに直結し、労基署からの是正勧告や訴訟に発展するケースもあります。
予防には、勤怠管理システムを導入して労働時間を正確に把握し、労務マニュアルを整備することが有効です。さらに、制度を従業員全員が理解している状態を作ることが大切です。問題が発覚した場合は早急に弁護士や社労士に相談し、トラブルの拡大を防ぎましょう。
3-4:労働訴訟・行政対応
労務トラブルがこじれると、労働審判・労働基準監督署からの指導・あっせん通知といった段階に進むことがあります。この段階では経営者の感覚的対応ではなく、証拠資料の整理と専門家の助言が不可欠です。
例えば「残業代未払いを主張されたケース」では、勤怠記録や給与明細が証拠となります。普段から法令順守の姿勢を示し、記録を残す仕組みを整えることで、万が一の際にも有利に対応できます。
4:店舗運営でよくあるトラブルと解決法

4-1:予約トラブル
キャンセルやダブルブッキングは売上に直結するトラブルです。特に週末や繁忙期に重なると、空席損失や顧客不満が一気に高まります。
予防には、キャンセルポリシーを明文化し、予約時点で顧客に周知することが必須です。たとえば「前日キャンセルは○%のキャンセル料」など具体的に示すと、顧客も理解しやすくなります。また、オンライン予約システムを導入すれば、予約状況をリアルタイムで確認でき、ダブルブッキングのリスクも激減します。
4-2:レジ・会計のトラブル
会計での間違いは「金銭に直結する」ため、小さなミスでも信頼を大きく損ないます。お釣りを間違える、レジ入力を誤るといったケースは日常的に起こり得ます。
対策としては、POSレジの導入や二重チェック体制を設けることが効果的です。誤請求が発覚した場合には「謝罪+速やかな返金対応」が基本。さらに、再発防止策を説明すると顧客の安心感につながります。
4-3:食材仕入れトラブル
飲食店の生命線である仕入れでもトラブルは起こります。納品遅延や不良品、仕入れ価格の急な変動は避けられません。
解決策は、複数仕入れ先の確保と契約内容の明確化です。急な食材不足の際には「代替メニュー」を提案できる体制を用意しておくと営業を止めずに済みます。仕入れ先との定期的なコミュニケーションも、トラブル防止に有効です。
4-4:衛生管理・設備トラブル
冷蔵庫や厨房機器の故障は、最悪の場合営業停止につながります。食器の破損なども、顧客体験を損なう要因です。
日常的に定期点検を行い、予備の備品や修理業者のリストを用意しておきましょう。営業中に発生した場合は「迅速に代替対応」を取ることで、顧客への影響を最小限にできます。
5:外部要因によるトラブルとリスク管理
飲食店は、店舗内部だけでなく「外部からの影響」によってもトラブルに直面します。経営者自身がコントロールできない事象も多く、長期的に見れば店舗運営を左右する重大なリスクとなります。
5-1:近隣住民からの苦情
最も多いのが「騒音・匂い・ゴミ処理」に関するクレームです。
・夜遅くまでの営業による話し声や音楽
・焼肉やラーメン店での強い匂い
・店舗裏に積まれるゴミの臭気や散乱
こうした苦情は一度発生すると地域全体で悪評が広まりやすく、行政への通報や営業停止につながる可能性もあります。
対策としては、日頃から住民とコミュニケーションを取り、改善要望には誠実に対応すること。換気設備やゴミ置き場の見直しも有効です。
5-2:自然災害・設備停電
台風・地震・大雪などは飲食店に直接被害をもたらします。特に冷蔵庫が止まれば食材ロスにつながります。
対策は、非常用電源や保険加入、災害時の営業マニュアルの準備です。
5-3:行政からの規制
コロナ禍の時短営業要請や禁煙条例など、行政の規制は突然強まることがあります。経営者の力では避けられないため、柔軟にメニューや営業時間を調整できる体制を整えておくことが重要です。
5-4:人手不足・人材流出
飲食業界の慢性的な課題が人材不足です。シフトが埋まらず営業に支障をきたすのも典型的な「外部要因トラブル」です。
対策は、採用強化に加えて「勤怠管理システム導入」や「オペレーション簡素化」で少人数でも回せる体制を構築することです。
5-5:資金繰り・物価高騰
仕入れ価格の高騰や景気悪化でキャッシュフローが悪化するのも大きな外部要因です。補助金の活用や金融機関との連携で早めに対策を講じることが求められます。
6:トラブルを未然に防ぐための予防策
「予防こそ最大の防御」です。飲食店にとってトラブルは避けられませんが、発生を最小化する仕組みを整えておくことで、被害を大幅に減らせます。
・従業員教育:接客マナー、クレーム対応、衛生ルールを日常的に訓練
・社内ルール整備:労務管理、ハラスメント防止、セキュリティルールを明文化
・勤怠管理システム:残業代未払い防止・シフト調整の透明化
・衛生管理体制:手洗い・消毒・温度管理・交差汚染防止を徹底
・店舗環境改善:座席配置、分煙、防音設備を工夫して客同士の摩擦を軽減
こうした仕組みを「形式だけ」ではなく「日常業務に落とし込む」ことがポイントです。例えば朝礼でクレーム事例を共有したり、月1回の衛生チェックを徹底するなど、小さな積み重ねが大きな予防効果を生みます。
7:トラブル発生後のフォローアップと信頼回復
トラブルは発生してしまうもの。しかし「その後の対応」次第で、お客様や従業員からの信頼を回復するどころか、逆に強化することすら可能です。
・初期対応:誠実な謝罪、代替案提示、必要に応じた補償。初動の誠実さが印象を左右する。
・事後対応:原因を分析し、再発防止策を立案して従業員に共有。
・損害軽減:保険の活用、弁護士相談、社内リスクマネジメントチームの設置。
・顧客へのフォローアップ:進捗報告や謝罪メールを送り、対応の透明性を示す。
・従業員への再教育:トラブルを共有し、次に活かす研修を行う。
誠実な対応を継続することで「この店は信頼できる」と評価され、結果的にリピーター獲得につながるのです。

ちなみに私たちが提供する飲食店アプリ作成サービス「レストラン★スター」には、お客様にアンケートをとる機能があります。
アンケートという自分の声をお店に届ける仕組みをお客様に用意してあげることによって、トラブルによって生まれた不満を内々に事前キャッチすることができます。もしアンケートの仕組みがなければ不満をGoogleマップの店舗情報などに書かれてしまう可能性もあります。アンケートはお客様の声をキャッチできるだけでなくリスクを減少する効果もあるわけです。
さらに、レストラン★スターにはアンケートに特定の回答をしたお客様を絞り込んでアフターフォローメッセージをPUSH配信できます。
(例)料理の提供スピードに低評価を付けたお客様を絞り込んで、お詫びとクーポンをつけて「先日は失礼しました。改善しましたので是非またご来店ください」とメッセージ配信することが可能です。
この他にもアンケートを使って多くのことが実現できますので、詳しくは資料をダウンロードしていただくかお気軽にお問合せください。
↓ ↓ ↓
8:まとめ|飲食店トラブルは「原因分析と予防」が最重要
飲食店のトラブルは、内部・外部問わず必ず発生します。大切なのは「予防策」と「初期対応」、そして「フォローアップ」です。
衛生・接客・労務・設備といった内部要因は、教育・システム・マニュアルで予防できる
外部要因(住民苦情・災害・規制・人材不足)は、事前の備えと柔軟な体制が鍵
発生後の対応と信頼回復策次第で、むしろ顧客からの信頼を高めるチャンスにもなる
飲食店経営者にとって、トラブルは「避けるべきリスク」であると同時に「改善と成長のチャンス」でもあります。日常から仕組みを整え、誠実な姿勢を持つことで、長く愛される店舗へとつながるでしょう。