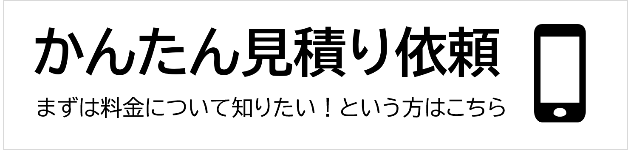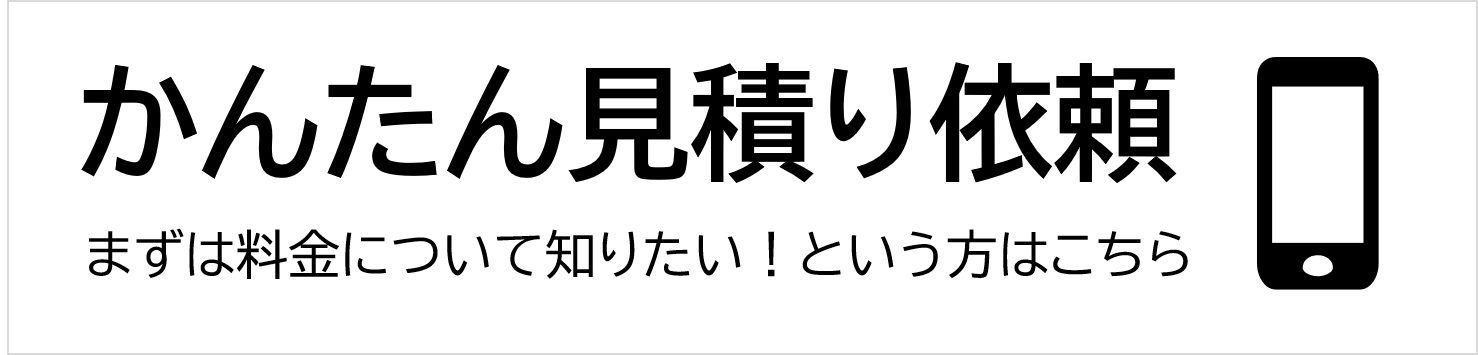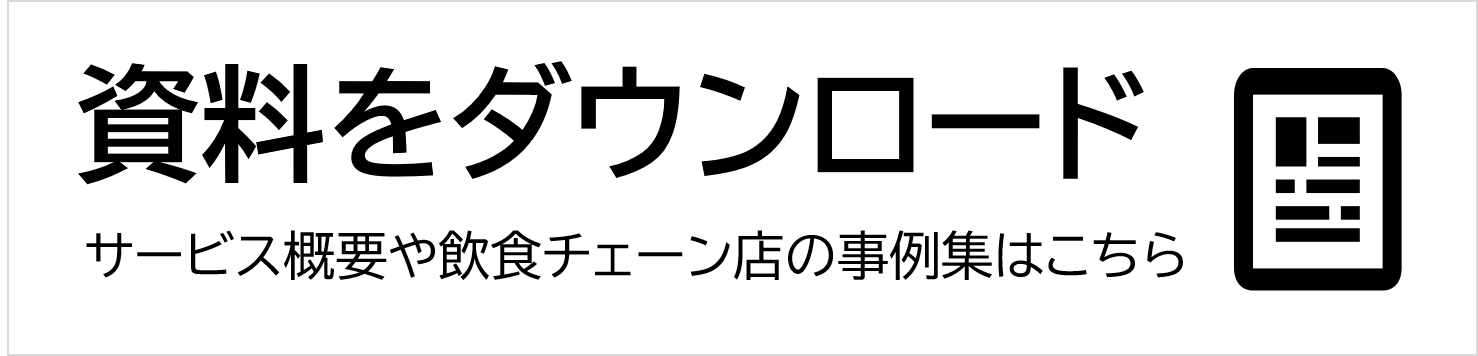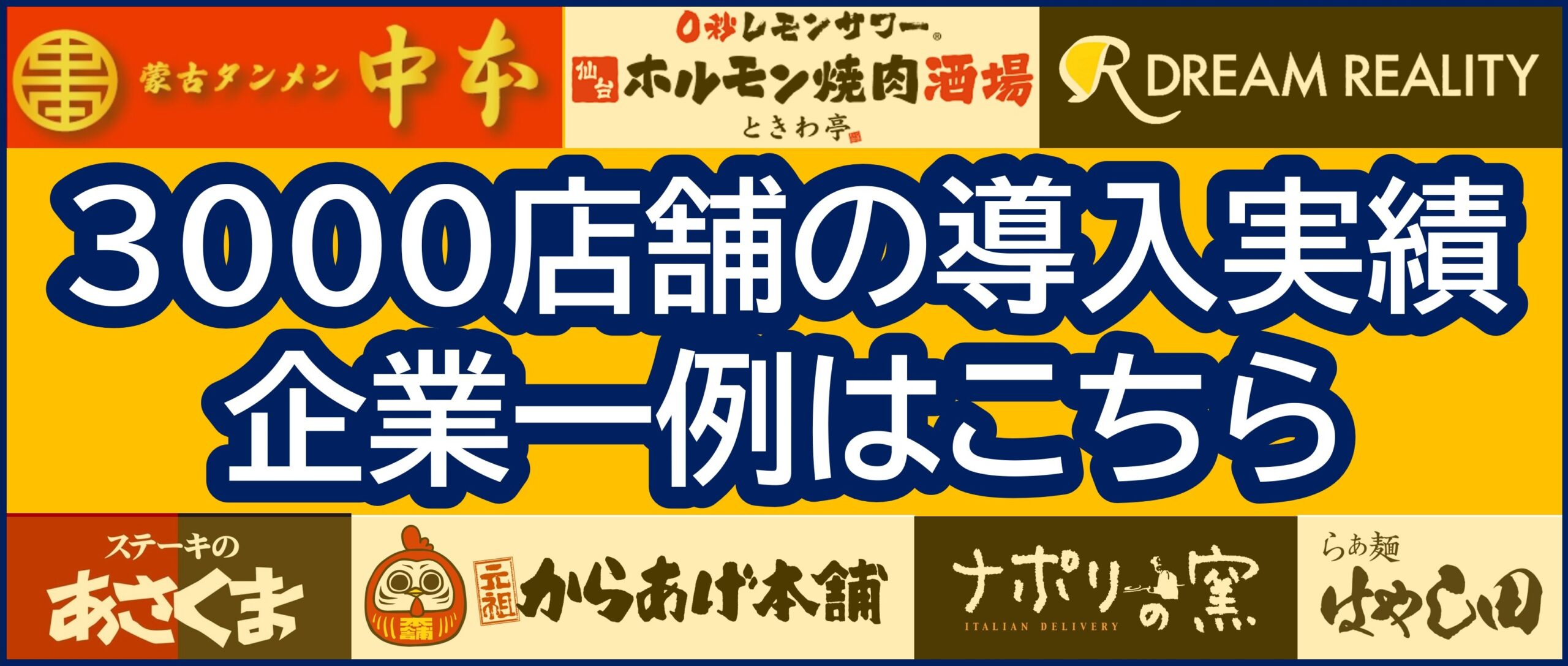【飲食店の値上げで客離れを防ぐ方法】価格戦略・伝え方・告知例文
飲食店の経営者にとって、「値上げ」は避けられない課題です。
しかし、適切な価格戦略を取らないと客離れにつながるリスクがあります。
この記事では、飲食店の値上げによる客離れを最小限に抑えるための具体的な方法をご紹介。価格設定の見直しや効果的な告知方法、そしてお客様に納得していただける値上げの伝え方までを徹底解説します。
値上げに踏み切ることで、経営を安定させつつ、顧客満足度を維持するための重要なポイントを押さえましょう。
価格の変更が避けられない状況でも、この記事を読むことで、あなたの飲食店が客離れを防ぎ、さらにファンを増やすための有効な対策を見つけることができます。
目次
1:飲食店の値上げでなぜ客離れが起きるのか
飲食店にとって、値上げは経営を守るために避けられない決断です。しかし、実際に値上げをすると「常連のお客様が減った」「新規客が来なくなった」と悩むケースは少なくありません。
まず理解すべきは、来店頻度の高い飲食店の利用者ほど値上げに敏感だという点です。頻繁に利用する人にとっては、50円や100円の値上げでも「月に数回来ると合計で数百円の負担増」として実感されやすく、心理的抵抗が強まります。
さらに、説明がないままの値上げや「ステルス値上げ」(料理の量を減らすだけ、原価の安い食材に変えるなど)は、不信感を招きやすい典型例です。「裏切られた」と感じれば、すぐに競合店へ流れるきっかけとなります。
特に競合が多いエリアでは、価格差がシンプルに来店動機を左右するため、値上げは顧客離脱を加速させるリスクがあります。
つまり、『値上げによる客離れの大きな要因は「価格そのもの」よりも「納得できない上げ方」にある』といえるのです。
2:値上げしても客離れしない店の共通点
一方で、値上げをしても客足が落ちない飲食店も存在します。その違いは「価格以上の体験価値を提供しているかどうか」です。
たとえば、食材の産地や生産者を明示したり、料理の背景にあるストーリーを伝えたりすることで、「高いけれど納得できる」と顧客は感じます。単なる料理ではなく「安心感」や「特別感」を売っているのです。
また、ターゲットの再設定を検討することも重要です。低価格を最重視する層ではなく、「味や体験にお金を払う層」に焦点を移すことで、値上げに対する許容度が高まります。
加えて、日頃から誠実にお客様へ情報を発信し、スタッフが丁寧な接客を続けているお店は、多少の価格改定では信頼を失いません。
つまり、**「伝え方」「付加価値」「信頼関係」**の3つが揃っている飲食店は、値上げ後も選ばれ続けるのです。
3:客離れを防ぐ値上げの実践ステップ

3-1:対象メニューの選び方
全メニューを一律で値上げするのはリスクが高いため、まずは原価の上昇が大きい商品から優先的に値上げすることが基本です。輸入食材や季節変動の激しい食材を使うメニューは、価格調整の理由が説明しやすいからです。
看板商品や人気メニューは特に慎重に扱う必要があります。これらを値上げする際には、品質向上やサービス特典をセットで提示することで顧客の納得度を高めましょう。
また、客単価を上げる方法として、セットメニューやオプション追加を活用するのも効果的です。「値上げ」ではなく「選択肢が増えた」と感じてもらえる工夫になります。
3-2:効果的な価格設定の手法
価格設定の失敗は、客離れを招く最大の要因です。
まずは競合の価格帯を調査し、自店の立ち位置を明確にしましょう。次に、自店のコスト構造を分析し、利益と顧客満足の両立を意識して価格を決めることが大切です。
心理的価格設定も効果的です。たとえば「1,000円」よりも「999円」、「1,300円」よりも「1,280円」とすることで、実際の差以上に安く感じさせることができます。
さらに、段階的に値上げするのもひとつの手です。一度に大幅な値上げをすると反発を招きやすいため、数回に分けて実施することで顧客が慣れやすくなります。
3-3:来店頻度ごとの戦略
値上げの影響は、お客様の来店頻度によって異なります。常連客は少額の値上げでも年間では大きな負担と感じるため、離脱リスクが高い層です。逆にライト層は多少の価格変動では離れやすいものの、売上への影響は限定的です。
そのため、まずは自店のデータを分析し、「客数が◯%減っても粗利は◯%確保できる」といった基準を決めることが重要です。
特に常連客に対しては、値上げ時に特典や個別フォローを優先的に行うことで、長期的な信頼関係を維持できます。
3-4:値上げ幅の目安
値上げを行う際にもっとも悩むのが「どの程度の幅に設定するか」です。一般的に、値上げ幅は最大で15%以内が望ましいといわれています。これは心理的な受容ラインを超えると、たとえ小額でも「高くなった」という印象が強まり、客離れのリスクが一気に高まるためです。
例えば、1,000円のメニューを1,150円にする程度なら「少し高くなった」と感じながらも受け入れられることが多いですが、1,200円や1,300円に跳ね上がると抵抗を示す顧客が増えます。
また、一度に大幅な値上げを行うよりも、小幅で段階的に実施する方が顧客が慣れやすいという特徴もあります。まずは50円〜80円程度の上げ幅で試し、反応を見ながら調整するのも効果的です。
業態ごとに基準を設けることも大切です。たとえば、日常的に利用されるラーメンや定食業態では「ワンコインを超えるかどうか」が心理的な分岐点になりやすい一方で、焼肉や寿司など特別な場面で利用される業態は、多少高くても受け入れられるケースが多いです。
つまり、値上げ幅は一律ではなく「15%以内を目安にしつつ、業態と顧客層に合わせて調整する」のが基本戦略といえます。
4:値上げの告知方法と伝え方のコツ

4-1:告知タイミング
値上げを伝える際に最も避けたいのは「突然知らされた」という顧客の不満です。
価格改定は最低でも1か月前には伝えることが基本です。余裕を持たせることで「理解し準備する時間」を与えることができ、不信感を最小限に抑えられます。
また、告知の時期は店舗の繁忙期や大型イベント直前を避けることも重要です。忙しい時期に値上げが重なると「稼ぎ時に便乗しているのでは?」という誤解を招きかねません。閑散期やキャンペーン終了後など、比較的落ち着いたタイミングを選ぶと良いでしょう。
4-2:告知方法
値上げの伝え方は「伝える方法の多さ」と「一貫性」がカギです。
店頭POPやチラシ:来店客に一目で伝えられる基本ツール
公式サイトやSNS:幅広い顧客層への告知に有効
アプリ通知やLINEメッセージ:常連客に直接届けやすいチャネル
口頭での直接説明:特にVIP顧客や常連にはスタッフから直接伝える
これらを併用して一貫性のあるメッセージを発信することで「しっかり準備して誠実に伝えている」という安心感を与えられます。
4-3:誠実に伝える告知例文
値上げはどうしてもネガティブに受け取られがちですが、理由+感謝+今後の努力を含めて伝えると印象は大きく変わります。
例文①(一般告知用)
「このたび、原材料価格や人件費の高騰により、一部商品の価格を改定させていただくことになりました。これまでと同じ品質を守り、さらにサービスの向上を目指すための判断です。日頃のご愛顧に心より感謝申し上げます。」
例文②(常連向け/アプリ通知やLINE)
「いつもご利用ありがとうございます。大切なお知らせとして、来月より一部商品の価格を改定いたします。これからも安心してご利用いただけるよう、品質やサービスを一層磨いてまいります。ご理解賜りますようお願い申し上げます。」
例文③(特典付き案内)
「価格改定に伴い、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて【次回ご利用500円割引クーポン】をご用意しました。これからも変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。」
5:値上げ後のフォローで客離れを防ぐ

5-1:再来店を促すサービスをして客離れを防ぐ
値上げ直後は、顧客が「この店に通い続けるか」を判断するデリケートな時期です。そこで重要なのが「値上げしたけれど、それ以上に得をした」と感じさせる施策です。
具体的には、次回来店時に使える割引クーポン、新メニューの先行試食券、曜日限定の特別割引などが効果的です。
また、会員限定イベントやスタンプ特典など「特別扱いされている」と感じられる工夫も再訪率を高めます。値上げを単なる負担ではなく「新しい楽しみにつながる出来事」に変えることがポイントです。
5-2:顧客満足度を高める接客・サービス改善をして客離れを防ぐ
価格が上がったとき、顧客は無意識に「サービスが以前より良くなったか」を観察します。
だからこそ、スタッフ教育を強化し、笑顔・清潔感・丁寧な対応を徹底することが欠かせません。小さな気配り(例:料理提供時に一言感謝を添える、注文後に一度目を合わせて確認する)も「この店は違う」と感じてもらえるポイントになります。
さらに、スタッフが値上げの背景を理解していれば、顧客から質問された際にも誠実に答えられ、信頼が揺らぎません。
5-3:アンケートやレビューを活かした改善サイクルで客離れを防ぐ
値上げ後の顧客心理を見極めるには、直接「声」を集めることが大切です。アンケートやオンラインレビューを通じて「どの点に納得したか/不満か」を把握し、早めに改善策を講じましょう。
改善策は必ず顧客にフィードバックします。「いただいたご意見を反映し、〇〇を改善しました」と発信することで「この店は自分の意見を大事にしてくれる」と感じてもらえます。結果的に、値上げ後も強いロイヤルティが築かれます。
6:値上げをチャンスに変える飲食店の経営改善

6-1:人件費率や仕入れコストの見直し
値上げは単なる「価格改定」ではなく、経営全体を見直すきっかけになります。
仕入れ先との交渉や複数ルート化を進めれば、原材料価格の変動リスクを抑えられます。また、フードロス削減や仕込み量の最適化によって、仕入れコストを下げる余地も見えてきます。
さらに人件費率の管理も欠かせません。シフト管理をデータ化し、混雑予測を活用することで、人員配置を効率化できます。これにより人件費率が下がり、同じ売上でも利益率を上げられます。
「値上げで得た利益を浪費する」のではなく、コスト削減と組み合わせることで、より強固な経営基盤を築くことができます。
6-2:デジタル化・システム活用で飲食店経営を効率化
人手不足やコスト高が続く中で、デジタルツールの活用は避けて通れません。
予約管理システムを導入すれば、ドタキャンや予約漏れを防止できます。POSレジや売上分析システムを使えば、値上げの効果を数値で確認でき、次の施策にも活かせます。
さらに注目したいのが 「会員証アプリ」 です。
店舗アプリを導入すれば、来店履歴や購入データをもとにプッシュ通知やクーポン配信が可能となり、リピート率を大幅に向上させられます。結果として、新規集客に投下していた広告費を抑え、同じコストでより多くの売上を生み出す効率的な集客構造をつくれます。
つまり、DXや会員証アプリの導入は「人件費や広告費を削減する守りの施策」であると同時に、「リピーターを増やし売上を伸ばす攻めの施策」でもあるのです。
飲食店に特化した会員証アプリについて「詳しく知りたい!」という方は以下から資料をダウンロードしていただくか、お気軽にお問合せください。
↓ ↓ ↓
6-3:利益体質を強化して「値上げしなくても耐えられる飲食店」へ
最終的な目標は「値上げに頼らなくても利益が出せる体質づくり」です。
そのためには、売上の多角化が不可欠です。
・テイクアウトやデリバリーの導入で新しい販路を確保
・サブスク(定額制サービス)で安定収入を確保
・通販や物販で店舗外収益を創出
こうした複数の収益源を持つことで、材料高騰や景気変動があっても耐えられる強い経営に変わります。
値上げを「一時しのぎ」に終わらせず、経営改善のきっかけにすることが、長期的に顧客から選ばれる店舗になるための最大のポイントです。
7:値上げしても客離れしにくい具体事例
値上げによる客離れは必ずしも起こるとは限りません。実際には、業態や利用シーンによって「値上げに強い店」と「値上げに弱い店」が存在するのです。ここでは、いくつかの具体事例を見てみましょう。
7-1:焼肉店の場合
焼肉店は「誕生日・記念日・宴会」といった特別な会食需要が多く、値上げにある程度の耐性がある業態といえます。利用シーンが非日常的なため「多少高くてもこの店を選びたい」という心理が働きやすいのです。さらに、グループでの利用が多いため、1人あたりの値上げ額が分散され、心理的負担が小さく感じられます。
7-2:カレー・ラーメンチェーンの場合
カレーやラーメンといった日常食でも、強力なブランド力や固定ファンを持つチェーンは値上げに成功しています。実際に「CoCo壱番屋」さんでは、1杯のカレーが1,000円を超えるケースも珍しくありませんが、味やトッピングの自由度を支持するファン層が離れず、安定した集客を維持しています。
つまり、ブランド力と独自性があれば、日常食でも値上げは受け入れられるのです。
7-3:海外の事例
海外では物価上昇に応じた値上げが一般的で、消費者も「品質を維持するためには当然」と理解する傾向があります。特に欧米では、オーガニック食材やサステナブルな取り組みなど付加価値を提示することで、価格が高くてもむしろ好意的に受け止められる例が増えています。
7-4:客離れしない飲食店に共通するポイント
これらの事例に共通するのは、
・「特別な日需要」がある業態は強気の値上げに耐えやすい
・ブランド力やファン層の厚い店舗は値上げを受け入れてもらいやすい
・付加価値をしっかり提示できる業態は海外でも成功している
という点です。
逆に、低価格競争が激しいファストフードや立地依存型の店舗では、値上げに対する耐性が低く、慎重な戦略が必要になります。
まとめると、値上げに成功するかどうかは「業態の特性」「顧客層の心理」「ブランドへの信頼感」に大きく左右されるのです。
8:まとめ|誠実さと戦略があれば値上げは怖くないし客離れは防げる
飲食店にとって値上げは避けられない決断ですが、やり方次第で結果は大きく変わります。
・値上げは「価格」ではなく「納得感」で受け入れられるかが決まる
・ターゲットシフトと付加価値提供で「価格に強い顧客」を育てられる
・誠実な告知とアフターフォローで信頼を維持できる
・DXや会員証アプリの導入で、値上げ以上の効果をもたらすことができる
・値上げをきっかけに経営体質を改善すれば「値上げ不要の強い店」へと進化できる
つまり、値上げは単なるコスト対応ではなく、顧客との信頼関係を強化し、店舗を成長させるチャンスです。
誠実な姿勢と戦略的な取り組みをもって臨めば、値上げは決して「客離れの原因」にはならないでしょう。
それではこの記事は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。