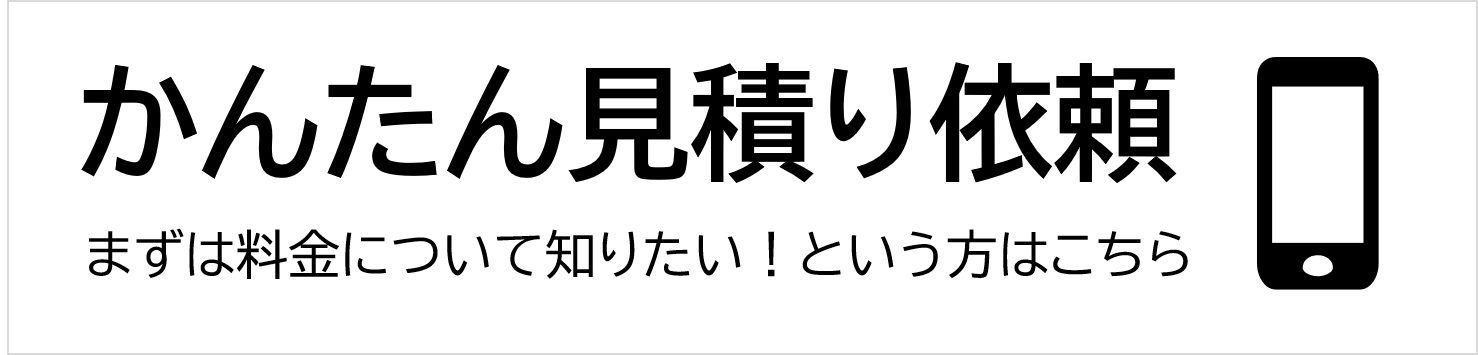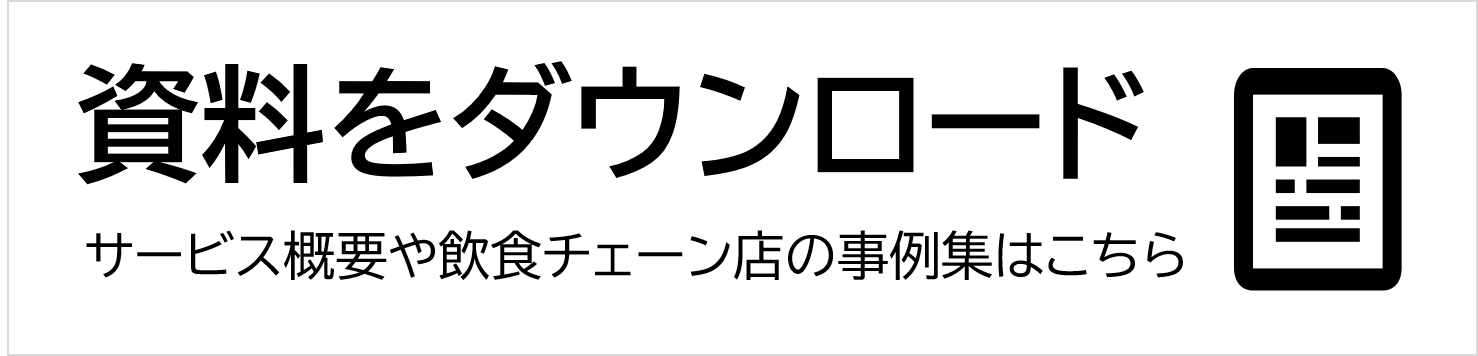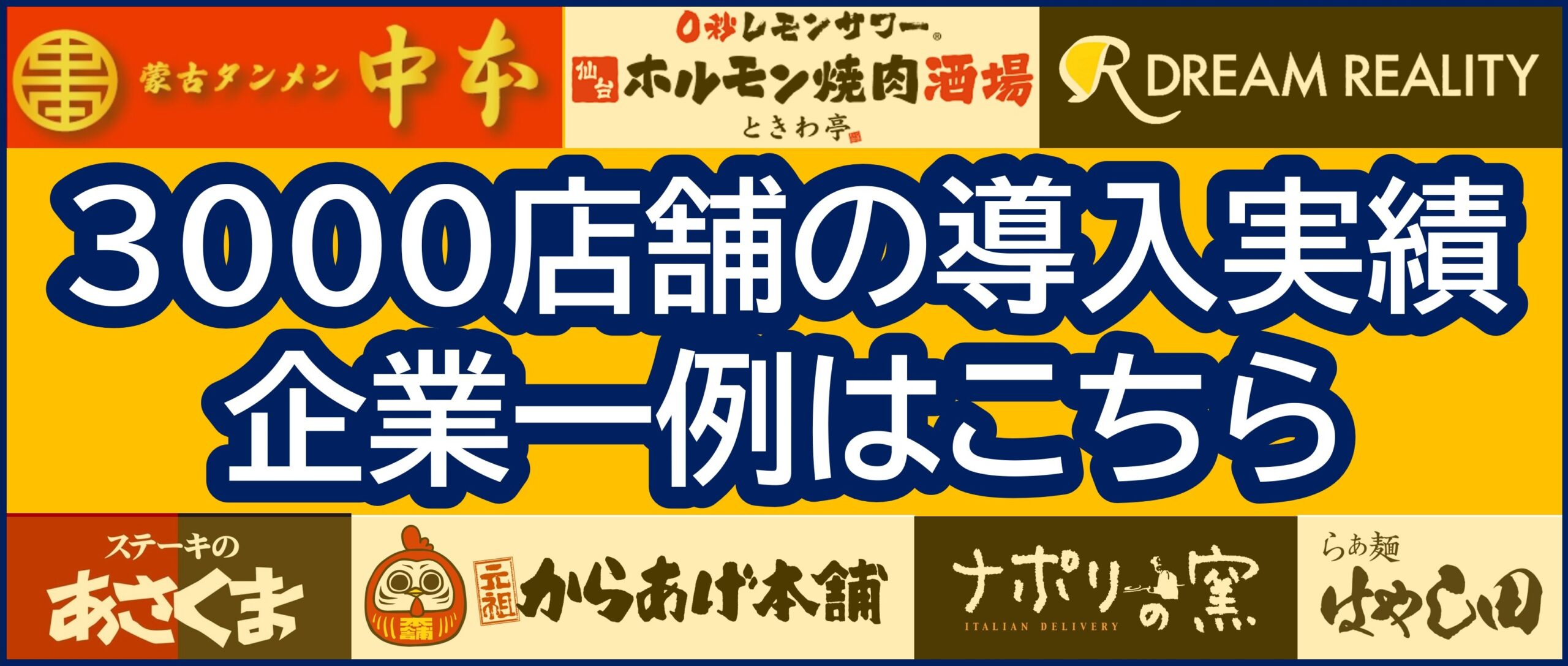【飲食店のターゲット設定ガイド】集客効果UP術を徹底解説
飲食店経営において、「ターゲット設定」は集客成功の鍵となる重要な要素です。
しかし、多くの飲食店オーナーが「誰に向けて店を開くべきか」というターゲット設定に悩んでいます。
このガイドでは、飲食店のターゲットを効果的に設定する方法を徹底解説し、集客効果を飛躍的に向上させるための具体的なステップを提供します。
この記事を読むことで、ターゲットとしている顧客層のニーズを的確に把握し、それに基づいた戦略的なマーケティングを展開する方法を学ぶことができます。
飲食店の経営を成功に導くための鍵を手に入れ、売上アップを実現するための第一歩を踏み出しましょう。
目次
1:飲食店におけるターゲット設定とは?【基礎知識】

1-1:ターゲット設定の意味と役割
飲食店経営において「ターゲットを設定する」という行為は、単なるマーケティング用語ではなく、店舗運営のすべての判断軸となる重要な工程です。
「誰に来てほしいのか?」を明確に定めることで、メニューの内容、価格帯、接客スタイル、内装デザイン、広告戦略といった全ての要素に一貫性が生まれます。
例えば「30代女性会社員」をターゲットにしたカフェなら、提供時間はランチタイム中心、価格は1,000円前後、内装は落ち着きがありSNS映えする空間、メニューは野菜中心のヘルシー系などが自然と導き出されます。
反対に、「誰でも歓迎」という曖昧な方針では、何を優先すべきか分からず、結果として“誰にも響かないお店”になってしまう可能性があります。
ターゲット設定とは、言い換えれば、「選ばれる理由」を作るための起点なのです。
1-2:なぜターゲットが必要か
飲食店が限られたリソースの中で成果を出すには、狙いを定める必要があります。
集客・接客・商品開発・販促など、あらゆる意思決定の場面で、「この選択は誰のためか?」を判断する基準となるのがターゲットです。
マーケティングの世界では「1つのターゲットに集中するほど、メッセージは強くなる」と言われています。
それは飲食店にも当てはまります。たとえば、「学生向けの低価格・大盛無料定食」と「ビジネスマン向けの静かで落ち着いた和定食ランチ」は、同じ店で両立させようとすると、どちらつかずになり、どちらの客層からも選ばれにくくなるのです。
ターゲットを定めることは、取るべき行動に優先順位をつけるための羅針盤となり、日々の判断ミスを減らすためにも欠かせません。
1-3:ターゲットを設定しないリスク
もしターゲットを決めずに店舗運営を始めてしまうと、
「店の強みは何なのか」「どんな人が利用してくれるのか」が曖昧なままになり、結果としてどの集客施策も弱く、コストだけがかかる状態になります。
たとえば、「メニュー数が多いけどコンセプトが分からない」「広告は打っているのに反応が薄い」「クチコミやSNSの評判が伸びない」などの現象は、ターゲット不在の典型例です。
また、スタッフ教育にもばらつきが生まれ、接客品質にも差が出てしまいます。
つまり、ターゲットを設定しないことは、“コスト高”で“ブランド低下”を招く大きなリスクであり、それが長期的な売上不振に繋がっていくのです。
2:ターゲットを設定するメリット【集客・売上への影響】

2-1:広告や販促が効率化できる
ターゲットが明確であれば、訴求内容や媒体選定に迷いがなくなります。
たとえば、若年層がターゲットならInstagramやTikTok、シニア層なら地元紙やポスティングが効果的。
また、広告文のトーンや写真の選び方、キャッチコピーもターゲット像に合わせて最適化でき、無駄な広告費の削減と反応率の向上が両立できます。
2-2:商品・サービス設計がしやすくなる
誰に食べてほしいのかが定まっていれば、「どんな料理を出すべきか」「価格はどれくらいが適正か」「どんな雰囲気の店舗が合うのか」が自然と見えてきます。
この状態は、メニュー開発や店内レイアウト、BGMの選定、テーブル配置など、細部の施策にまで好影響を及ぼします。
結果的に、ターゲットにとって心地よく、ストレスのない空間が作れるため、満足度の高い体験を提供できるようになるのです。
2-3:顧客満足度とリピート率が向上する
「このお店、自分のこと分かってるな」と感じてもらえた瞬間、顧客の満足度は一気に高まります。
ターゲット設定が明確なお店は、“自分のために存在している”と感じさせる力があります。
これはリピート率、ひいてはLTV(顧客生涯価値)の向上に直結します。
リピーターが増えるということは、「安定した売上」と「クチコミによる無料の宣伝」が期待できるということ。これは小規模店舗にとって非常に大きな武器となります。
2-4:ブランド構築と競合との差別化ができる
ターゲットが決まると、店舗の価値や個性も際立っていきます。
「このエリアの中で、○○向けならこのお店」といったように、地域内での明確なポジションを築けるようになるのです。
差別化が進むことで、価格競争からも抜け出しやすくなり、「値段で勝負する店」ではなく「価値で選ばれる店」に変わっていけます。
2-5:ターゲット外にも良い影響が出る
意外かもしれませんが、ターゲットを明確にすると「それ以外の層」の居心地も良くなります。
ターゲットが絞られることで、空間やサービスに一貫性が生まれ、結果的に誰にとってもわかりやすく、使いやすい店舗になります。
つまり、「中心に誰を置くか」を決めることで、周囲にも良い影響を与える波紋が広がるのです。
3:飲食店ターゲットの考え方と設定方法

3-1:属性でターゲットを捉える
まず第一に考えるべきは、来店客の「属性」です。
性別、年齢、職業、居住地、来店時間帯などの基本情報をもとに、「どんな人が、どのタイミングで、何を求めて来るのか」を分析します。
また、「1人で来るのか/家族連れか」「仕事中のランチか/友人とのディナーか」といった来店シーン別の切り分けも非常に重要です。
さらに、最近は「健康志向」「SNS映え」「手軽さ重視」などの価値観・ライフスタイル視点でも分類が進んでいます。
3-2:ペルソナを設定する
次に行うべきは、「ペルソナ」の作成です。これはターゲットをより具体的に、一人の架空の人物像として描き出す方法です。
例:
都内勤務の30代女性。健康に気を使っており、外食は週2回。ランチは1,000円前後で、時間は1時間以内。おしゃれなカフェでのんびりしたいが、混雑しすぎる店は避ける。Instagramで新店舗情報をチェックするのが日課。
このようにペルソナを描いておくことで、「この人なら何に惹かれるか?」を具体的に想像しながら施策を打てるようになるのです。
3-3:現場の声と競合店から学ぶ
ペルソナは机上の空論になりがちなので、実際の顧客やスタッフの声を必ず取り入れましょう。
「なぜこの店に来たのか」「何に満足して、何に不満だったか」といったリアルな意見は、ターゲット像を肉付けする貴重な材料になります。
また、競合店のSNSやレビュー、価格帯やメニュー内容なども分析しておくと、自店との差別化ポイントが見えてきます。
3-4:ターゲット設定後は排他にならないことが重要
ターゲットを設定したからといって、それ以外の人を切り捨てる必要はありません。
あくまで“軸”として設け、そこを中心にしながら、他の層にも配慮した空間設計や接客を心がけることが、結果的に売上の最大化につながります。
4:データを活用したターゲット分析の手法【実践編】
ターゲット設定は「勘」や「思い込み」だけで決めるのではなく、客観的なデータ分析を通じて、精度を高める必要があります。
ここでは、飲食店で実践しやすいデータ活用法を6つ紹介します。
4-1:属性分析で基本的な傾向をつかむ
まず最も基本的なのは、来店客の「性別・年齢・エリア・来店時間帯」などの情報を集めることです。
これはPOSレジの履歴や予約時の入力データ、アンケートや会話から拾うことができます。
例:
平日のランチ来店は30代女性が多い
土日の夕方はファミリー層の割合が高い
学生の利用は夜の時間帯が中心
こうしたデータは、**「どの時間に、どんな層が、何を求めて来ているか」**を可視化し、施策の優先順位を見極める指針になります。
4-2:デシル分析で売上の偏りを確認
デシル分析とは、顧客を「売上金額の多い順に10グループに分けて分析する手法」です。
例えば、上位10%の顧客が売上の50%以上を占めている場合、その人たちに向けた施策(会員制度・限定メニュー等)が非常に重要になります。
**“売上に貢献しているのは誰か”**を明確にできるのが、この分析の強みです。
4-3:RFM分析でリピート傾向を把握
RFM分析は「最近の来店(Recency)」「来店頻度(Frequency)」「金額(Monetary)」の3軸で顧客を分類する手法です。
・頻度も金額も高い:超優良顧客。特別対応やVIP施策を検討。
・頻度はあるが最近来ていない:再来店を促すDMやクーポンが有効。
・一度きりの来店:改善点を探るヒントに。
このように顧客タイプごとに施策を分けることができ、再来店やファン化の鍵を握ります。
4-4:商圏分析で立地に合ったターゲットを知る
商圏分析とは、「店舗の周辺エリアにどんな人がどれだけ住んでいるのか」を調べる分析手法です。
人口構成や年収水準、生活スタイルなどがわかる行政データや地図分析ツール(例:JSTAT MAP、商圏分析サービスなど)を活用します。
・駅前立地 → 通勤層・OL・学生
・住宅街 → ファミリー・主婦層・シニア
・オフィス街 → ランチ特化・回転率重視
「地域の生活者」と「ターゲット想定」がズレていないかを確認するための重要な視点です。
4-5:アンケート・SNS・口コミを活用する
「10件以上のリアルな声を集める」ことは、現場の感覚を補強する大きなヒントになります。
オンラインアンケート(Googleフォームなど)やSNSのDM・コメント、Googleレビュー、食べログのクチコミなどを通じて、顧客のホンネを収集しましょう。
・よく注文されているメニュー
・好まれるポイント(接客/味/空間)
・改善点や不満(提供スピード/価格感)
口コミの共通点や言葉選びを抽出することで、ターゲットの価値観やニーズの言語化が進みます。
4-6:メニュー・売上データを定点観測
「どのメニューが、どの時間帯に、どんな層に人気か?」という情報は、POSやオーダー表を定点的に記録することで見えてきます。
例えば:
・夜に注文が集中する高単価メニューは誰に刺さっているのか?
・リピーターが必ず頼むサイドメニューは?
・売れていない商品がターゲットとズレていないか?
このように、メニューと顧客を紐づける視点で分析することで、商品開発や販促の判断精度が劇的に上がります。
5:ターゲット別の集客施策テンプレ集【チャネル×ターゲット×運用の型】

飲食店の集客は、ターゲットによって刺さる施策がまったく異なります。
ここでは、代表的な6つのターゲット層に分けて、それぞれに効果的なアプローチを具体例とともに紹介していきます。
5-1:学生向け|SNSと“映え”を武器にする
学生層は「SNS映え」「友達とのシェア」「コスパの良さ」といった価値観を重視する傾向があります。
日常的にInstagramやTikTokを使って情報収集しており、感情を動かす“ビジュアル重視”のプロモーションが有効です。
有効な施策例:
Instagram・TikTokを主軸に写真・動画を投稿
→ 盛り付けが豪華な「映えるメニュー」や、ユニークなネーミングがSNS上で拡散されやすいです。
学生証提示で特典(学割/ドリンク無料)
→ 学生は「特別扱い」に弱い層。気軽に利用しやすくなる心理的ハードルの低下が狙えます。
グループ来店キャンペーン(4人以上で割引など)
→ シェア文化に強い学生は、友達を誘って来店することが多いため、来店人数に応じたインセンティブが有効です。
公式アプリでクーポン配信
→ 登録・拡散しやすく、スマホでの情報接触頻度も高いため、継続的な関係構築に向いています。
5-2:ビジネスマン向け|時短・快適・信頼感を提供
ビジネスマン層が飲食店に求めるのは、「スムーズな体験」「コスパ」「静かさ」「安定感」。
特にランチタイムの集客は、“時間内に必ず食べ終わる安心感”と“落ち着いた空間”が重要な決定要因になります。
有効な施策例:
日替わりランチ+提供10分以内の設計
→ メニュー数を絞り、注文から提供までの時間を徹底管理することで、時間のない来店客の支持を集めます。
席予約・モバイルオーダー導入
→ 来店前にオーダーや着席が完了している状態は、短時間での食事が必要な層にとって大きな価値です。
落ち着いた空間演出と簡潔な接客
→ 賑やかすぎる店内や過度な接客はビジネスマンに敬遠されがち。内装・BGM・導線なども整えましょう。
法人向けランチチケット/定期予約の導入
→ 同じ会社の人が複数回使う店舗になると、一気にLTVが高くなります。
5-3:ファミリー層向け|“安心・快適・子連れ対応”がカギ
家族連れは、他のどのターゲットよりも「安全性」「居心地の良さ」「子どもへの配慮」を求めています。
親の心理的ハードルを取り除くことで、再来店率が圧倒的に上がる層です。
有効な施策例:
お子様メニュー・キッズチェア・おもちゃの提供
→ 子どもが喜ぶ=親の満足度が上がる。これは鉄則です。特に“お子様ランチ+おまけ”はリピートの起爆剤に。
「ベビーカーOK」や「おむつ交換台あり」などの表記
→ 表示していない=対応していないと思われがち。事前に安心できる情報をオンライン上に明記しましょう。
記念日プレートやファミリー写真撮影などの体験価値
→ 誕生日や七五三、入学祝いなど、家族の節目に選ばれる店になるには“思い出”を提供する工夫が必要です。
ポイントカード・回数券など家族単位のインセンティブ
→ 小さな得が積み重なることで“子育てに優しいお店”という印象が定着します。
5-4:カップル・女子会層向け|空間と演出が勝負
この層にとっての外食は「食事」だけでなく「体験」や「気分転換」でもあります。
特別な時間を過ごすために、「雰囲気の良さ」「フォトジェニックな料理」「ちょっとした非日常感」が欠かせません。
有効な施策例:
シェアしやすいプレート料理やペアセットの導入
→ 食事中の会話が自然に盛り上がるメニュー構成は、カップルや女子会利用に強く刺さります。
誕生日・記念日プレートや“メッセージデザート”の提供
→ 名前入りのサプライズプレートは、Instagram投稿される確率も高く、自然な宣伝効果があります。
照明・内装・食器・音楽まで「撮られる前提」で整える
→ SNS時代の飲食店は「美味しい」だけでなく「映える」が不可欠。フォトブースを設置するのもおすすめ。
SNS投稿キャンペーンやハッシュタグ特典
→ 来店後の“自発的な宣伝”を促す導線を設けましょう。
5-5:シニア層向け|“落ち着き・健康・会話”をサポート
シニア層には「体へのやさしさ」「ゆっくり過ごせる環境」「安心感」が求められます。
外食は娯楽でもあり、コミュニケーションの場でもあるため、心地よく過ごせる“居場所性”が鍵となります。
有効な施策例:
やわらか食/減塩/地元野菜など健康志向の料理提供
→ メニューの説明には「塩分控えめ」「油不使用」などを明記し、安心して選べる工夫が大切です。
段差のない店内・ゆったりしたテーブル間隔・座り心地の良い椅子
→ 快適性と安全性を両立させた物理的設計は、来店頻度を左右します。
新聞折込広告や電話予約対応など“アナログ対応”を重視
→ 高齢層はスマホに不慣れな方も多いため、電話・紙ベースでの情報提供を取り入れると強い支持が得られます。
“ご近所さん”との会話を生む店づくり
→ 常連同士の雑談が生まれるような温かい接客は、地域密着店としての信頼感を育てます。
5-6:インバウンド層向け|多言語・口コミ・即時性を意識
訪日外国人の集客には、「安心して利用できる導線」と「文化体験としての食」が大切です。
特に、多言語対応とSNS・地図情報の整備が重要な“来店きっかけ”となります。
有効な施策例:
メニューに英語/中国語/韓国語の翻訳を付ける
→ 写真付き・アレルゲン表示付きが望ましい。指差しで注文できる設計が安心感につながります。
Google MapsやTripAdvisorの情報を充実させる
→ 外国人観光客の多くは紙のガイドブックよりも“地図アプリ+レビュー”を頼りに店を選びます。
Facebook・YouTube・Instagramなど多国籍SNSで情報発信
→ 日本語だけでなく、簡単な英語キャプションを付けるだけでも、効果が変わります。
現地SNSとの連動キャンペーン(#JapanFoodTrip など)
→ 来日前/滞在中/帰国後の3段階で情報が循環し、口コミ効果が波及します。
6:出店立地とターゲットの関係【選ばれる場所の条件】

飲食店のターゲット設定は、店舗の“中”だけで完結するものではありません。
店舗の「場所」もまた、ターゲットに大きな影響を与える戦略要素です。
どのようなエリアに出店するかによって、自然と来店する客層は変わり、訴求ポイントや価格帯、提供スタイルも調整が必要になります。
ここでは、代表的な立地タイプごとの特徴と、相性の良いターゲット・業態を解説します。
6-1:駅前・駅近|フットワークの軽い人々を狙う
駅前エリアは、圧倒的な人通りとアクセスの良さが魅力です。
通勤・通学・買い物・乗換など、さまざまな目的で人が集まるため、短時間滞在のニーズが高く、回転率重視の設計が求められます。
相性が良いターゲット例:
学生・会社員・単身者・観光客など
ランチタイムやサク飲み・テイクアウト利用も多い
業態例:
立ち食い・フードスタンド
回転重視の定食屋・ファストフード
駅ナカのベーカリーやカフェ
ポイント:
看板や店頭販促物で“即決来店”を促す設計に
テイクアウト導線やモバイルオーダーとの親和性も高い
6-2:商店街|地域密着型でファンを作る
昔ながらの商店街は、地元住民との関係性が生まれやすい立地です。
リピーター獲得や口コミの広がりが鍵となり、継続利用される“日常の店”としてのポジションを確立できます。
相性が良いターゲット例:
ファミリー層・主婦層・シニア層
業態例:
和食屋・焼鳥・町中華など日常的な価格帯の業態
お惣菜テイクアウト・惣菜併設型食堂
ポイント:
クチコミ・チラシなどオフライン販促が効果的
店主の顔が見える接客で“ご近所さん”の安心感を演出
6-3:ビジネス街|昼の勝負と法人対応の工夫
オフィスビルが立ち並ぶビジネス街は、平日のランチタイムが圧倒的に重要です。
逆に、夜や休日は人通りが激減するため、売上構成や時間帯別の戦略設計が必要になります。
相性が良いターゲット例:
ビジネスマン・OL・ランチ利用者
業態例:
日替わり定食・高回転ランチ専門業態
弁当配達・ケータリング・会議弁当提供店
ポイント:
“時間内にしっかり食べて出られる安心感”が大前提
テイクアウトや事前注文で混雑回避をサポート
6-4:ロードサイド|駐車場と“目的来店”が肝
幹線道路沿いや郊外のロードサイド立地では、目的を持って車で来店するスタイルが中心になります。
目立つ看板と広めの駐車場が不可欠であり、ファミリー層や郊外型コミュニティを意識した設計が求められます。
相性が良いターゲット例:
ファミリー・カップル・中距離からの目的来店客
業態例:
焼肉・回転寿司・大型レストラン・チェーン系飲食店
ポイント:
駐車場の台数と導線が収益に直結
ドライブスルーやテイクアウト対応で強みを増す
このように、「ターゲット→施策」だけでなく、「立地→ターゲット→施策」という流れで思考することが、出店戦略や新規プロジェクトを成功させる鍵になります。
7:施策の見直しとKPI設計【集客を継続的に育てるために】
ターゲットを設定し、施策を実行したあとに最も大切なのが、**「やりっぱなしにしないこと」**です。
飲食店の集客力は、一度設定して終わりではなく、状況に応じて定期的に見直し、改善し続ける“育てる集客”が必要です。
ここでは、施策の振り返りや数値管理のポイントを解説します。
7-1:定期的にターゲット像を再確認する
ターゲットのニーズや行動は、時間とともに変化します。
例えば、コロナ禍をきっかけに「デリバリー利用者」「健康志向」の増加などが挙げられます。
そのため、3〜6ヶ月ごとに以下のようなチェックを行いましょう。
・来店者の属性に変化はないか?
・SNSのフォロワー層と実際の来店者層は一致しているか?
・売れているメニューに偏りはあるか?
このように、定期的な“ターゲットのアップデート”が、ズレた施策を防ぐポイントです。
7-2:KPI(重要指標)を設定して効果検証する
KPI(Key Performance Indicator)とは、「集客施策が目標に近づいているかどうかを判断する数値」です。
施策を打ちっぱなしにせず、“どの数字が上がれば成功か”をあらかじめ決めておくことで、行動の評価・改善が可能になります。
具体的なKPIの例:
| 項目 | 測定単位 | 意味・目的 |
| 来店人数 | 日/週/月 | 集客力の総量 |
| リピート率 | 月内2回以上の割合 | ファン化・満足度の指標 |
| 客単価 | 1人あたりの平均支払額 | メニュー戦略・価格帯設計の参考 |
| SNSフォロワー数 | 主要SNS別 | 潜在顧客の興味関心の広がり |
| クーポン利用数 | 時間・曜日別 | 施策の反応率・訴求力の測定 |
7-3:PDCAを実践し、育てる集客を回す
Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(検証)→ Act(改善)のサイクルを意識的に回しましょう。
例えば、SNS施策なら:
Plan:20代向けにInstagramキャンペーンを実施
Do:週3投稿+リール動画を配信
Check:1ヶ月後、フォロワー数は+300、来店者数に明確な変化なし
Act:リールの再生回数は伸びていた→動画活用を強化し、投稿内容を「裏側紹介」に変更
このように、“数値と顧客の声をもとに戦略を微調整する”ことが、集客成功の継続条件です。
8:まとめと次のアクション【ターゲット設定で“選ばれるお店”へ】
ここまで、飲食店におけるターゲット設定の重要性と、具体的な設定・分析・施策の実践方法を解説してきました。
最後にもう一度、要点を整理しつつ、これから「何を始めるべきか」について明確にしていきましょう。
8-1:この記事で押さえたターゲット設定の7つのポイント
➊ターゲット設定は、飲食店経営の軸になる重要なステップ
→ 全体戦略・商品設計・空間づくり・集客施策がブレなくなる
❷属性+ライフスタイルで具体的な“ペルソナ”を描くことがカギ
→ 年齢・性別だけでなく、「どんな生活をして、何を求めているか」まで深掘り
❸データ分析を組み合わせて、ターゲット設定の精度を高める
→ POS、アンケート、口コミ、商圏データなど活用できる情報は多い
❹ターゲットごとに施策の“型”が異なるので、戦略は使い分けが必要
→ 学生、ファミリー、シニア、ビジネスマンそれぞれに刺さる導線がある
❺出店場所によっても集客の考え方が変わる
→ 駅前、ロードサイド、商店街、ビジネス街それぞれに向いた戦い方がある
➏KPIを設計し、施策を“数字で振り返る”ことが集客成功の鍵
→ 客数、リピート率、単価、SNSフォロワーなどを可視化しよう
❼PDCAを回し、集客施策を“育てていく”感覚が重要
→ 一発で当てようとせず、小さな改善を続けることが、強いお店を作る近道
8-2:明日からできる3つのアクション
読み終えたあなたが、**実際に動き出すための「小さな一歩」**として、次の3つをぜひ実践してみてください。
➊ 来店してほしい理想の「1人」を紙に書き出してみる(=ペルソナ設定)
→ 名前、年齢、仕事、生活習慣、趣味、どんな時に来店するのか…を想像しながら、「あなたのお店のファンになってくれる一人」を描いてみましょう。
それが、すべての施策の“軸”になります。
❷ 過去3ヶ月のレジデータを見て、傾向を1つだけ見つける
→ 例えば「ランチの平均単価が1,200円」「リピート率が50%を切っている」「土曜日の売上が極端に低い」など、小さな発見でかまいません。
気づきがあれば、改善案も自然と見えてきます。
❸ 今日から1つだけ、ターゲットに向けた施策を実行してみる
→ SNSでメニューの紹介を投稿する/チラシのキャッチコピーを変える/POPにペルソナを意識した一言を足す…
どんなに小さなことでも、“ターゲットを意識した行動”が、あなたのお店の未来を変えていきます。
最後に:ターゲットを意識することは、「人を大切にする経営」そのもの
飲食店のターゲット設定とは、誰か一人に“あなたのために用意しました”と伝えることです。
それは、お客様を知ろうとする姿勢であり、喜んでもらいたいという想いの現れです。
つまり、ターゲットを意識することは、「人を大切にする経営」の第一歩なのです。
あなたのお店に来るお客様が、「ここは、自分のことをわかってくれている」と感じた瞬間、
そのお客様はリピーターになり、ファンになり、応援者になってくれます。
このガイドを通して、あなたの店舗にとって最適なターゲットが見つかり、
その人たちの心を動かす集客施策が、ひとつでも多く実行されることを願っています。