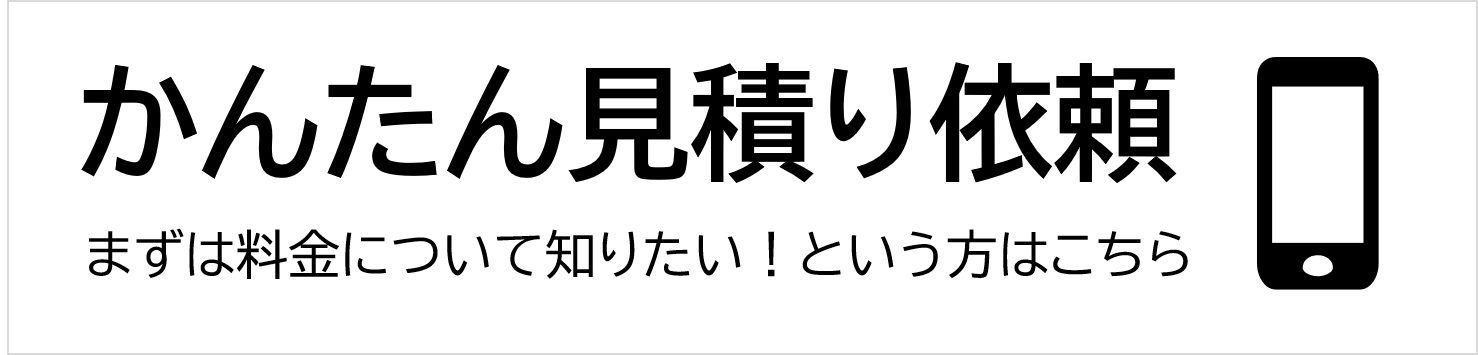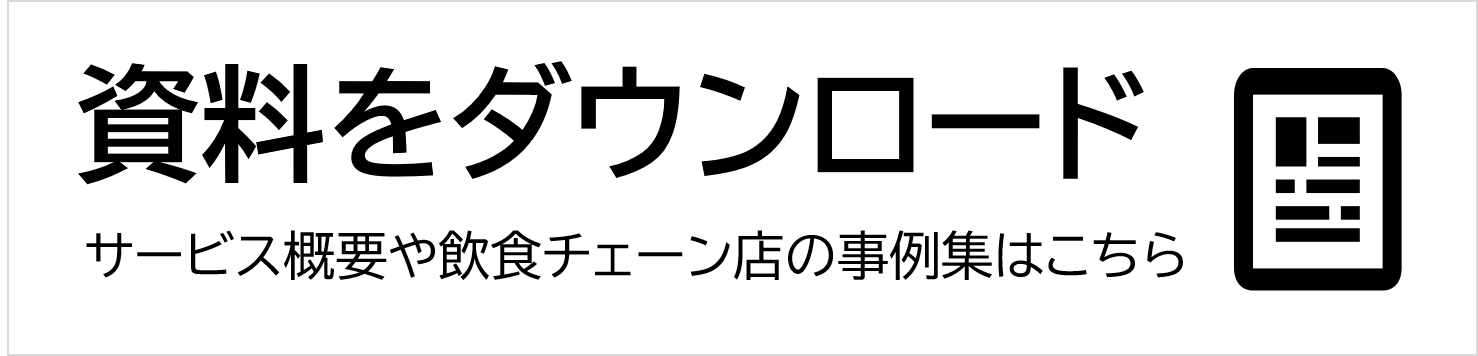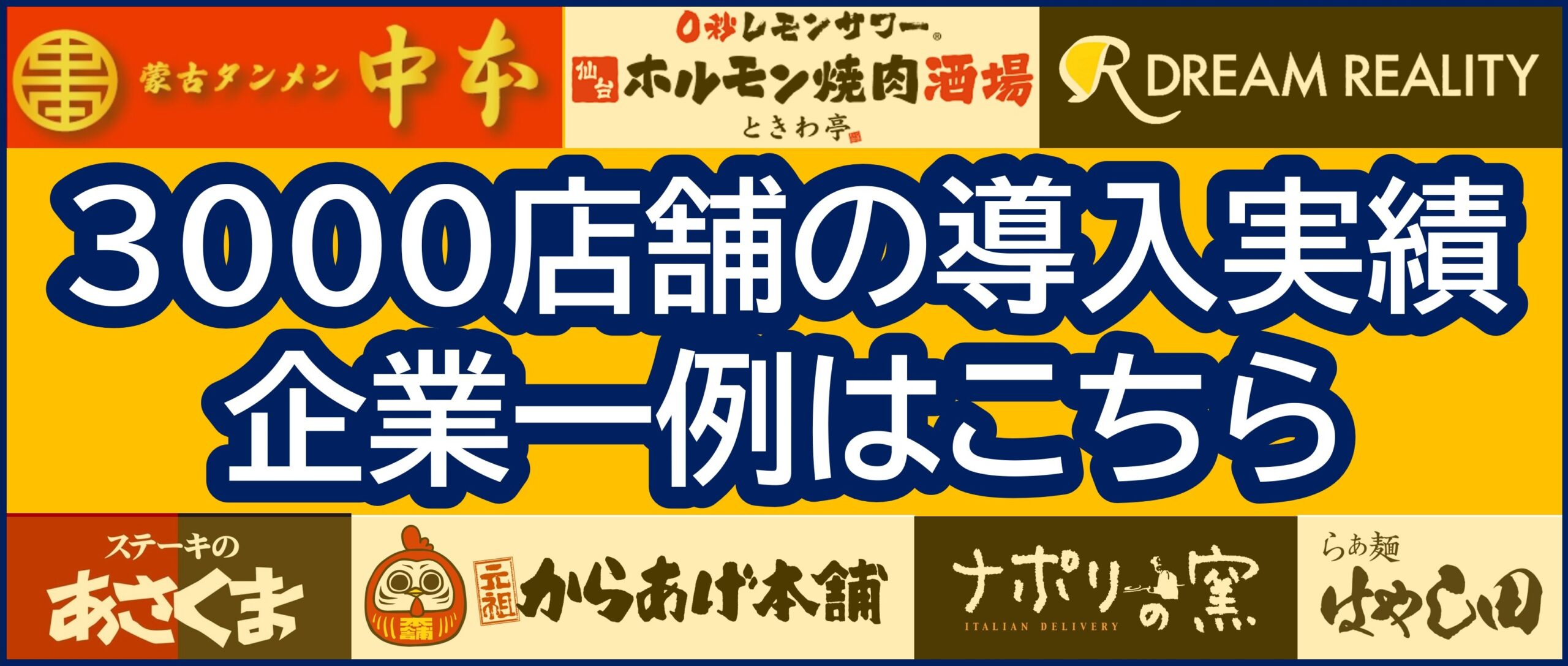儲かる飲食店の価格設定7つのポイント|原価率に頼らない値付け術
飲食店を経営する上で、価格設定は収益を左右する重要な要素です。
しかし、単に原価率に依存するだけでは、競争の激しい市場で成功を収めることは難しいかもしれません。
この記事では、飲食店の価格設定において押さえておくべき7つのポイントを紹介し、原価率以外の指標を活用した、より戦略的な値付け術を解説します。
価格設定の戦略をしっかりと理解することで、収益性の向上や集客力の強化を図ることが可能です。
あなたの飲食店の価格設定を見直すことによって、店舗の収益を最大化するヒントにしていただければ幸いです。
目次
1:なぜ飲食店に価格設定の戦略が必要なのか?
飲食店における価格設定は、単なる「値決め」ではなく、経営の成功を左右する重要な要素です。
価格は、収益の設計図として機能し、戦略的に設計されるべきです。原価率だけに依存して価格を決定すると、競争力や利益を損なう可能性があります。加えて、価格は固定されたものではなく、柔軟に見直し可能な「マーケティングの武器」として活用することが求められます。
また、価格は顧客にとっての価値の表現という側面もあります。
適切な価格設定は、顧客に提供する価値を伝える手段となり、店舗のイメージを形成します。例えば、同じ料理であっても、その価格には素材の質や調理技術、店舗の雰囲気などが反映されており、それが顧客の満足度と直結します。
さらに、価格設定は競合との差別化を図る上でも重要です。
競争が激しい市場では、価格だけでなく、付加価値や顧客体験を通じて他店との差別化を図る必要があります。これにより、顧客に選ばれる店舗としての地位を確立し、長期的な成功を収めることが可能となります。
このように、飲食店の価格設定は、ビジネスの根幹を支える戦略的な要素であり、収益性や集客力を向上させるために、しっかりとした戦略のもとで見直されるべきです。
2:飲食店の価格設定で押さえるべき3大指標

飲食店の価格設定を成功させるためには、単に原価率をベースにするだけでなく、他の重要な指標も考慮する必要があります。
以下に、価格設定において特に注目すべき3つの指標を詳しく解説します。
2-1:業態別に異なる「原価率」の目安を知り、価格設定に反映
価格設定の基本となる原価率は、業態によって異なる目安があります。
例えば、レストランでは35%前後、居酒屋では30%、カフェではフードが20~30&でドリンクは10〜20%が一般的な目安とされています。
ただ、近年では原材料費の高騰により、主要な外食チェーンの平均原価率が37.5%に達しています。このような状況に対応するため、多くの飲食店は価格設定を見直し、コストを抑える戦略を立てる必要があります。結果として、メニューの価格を引き上げることを検討するケースが増えています。
※出典:帝国データバンク|「主要外食 100 社」価格改定動向調査
原価率は、「原価 ÷ 売価 × 100」で計算され、これを基に価格を設定することで、一定の利益を確保できます。
しかし、すべてのメニューに一律の原価率を適用するのではなく、主力商品や看板商品に応じて調整することが重要です。これにより、競争力を維持しながら、利益率を最適化することが可能となります。
2-2:「FLコスト」「FLR比率」で収益構造を管理し、価格設定に反映
FLコストとは、Food(食材費)とLabor(人件費)を合わせたコストのことで、売上の50〜60%以内が理想とされています。
また、FLR比率は、FLコストにRent(家賃)を加えたもので、70%以内に抑えるのが目安です。
これらの指標を利用することで、経営の健全性を保ちつつ、価格設定に反映させることができます。
FL管理を怠ると、経営が圧迫される可能性があるため、定期的にレシピや人件費の見直しを行い、FLコストを最適化することが鍵となります。
2-3:FD比率(Food:Drink)の活用で利益構成を最適化
FD比率とは、Food(食べ物)とDrink(飲み物)の売上構成比率を指します。
業態によって異なりますが、例えば居酒屋ではF60%:D40%、カフェではF20%:D80%が一般的です。ドリンクは通常、原価率が低いため、販売を強化することで利益向上に大きく寄与します。
FD比率を最適化するためには、セット販売の導入やメニュー提案の強化が有効です。これにより、ドリンク販売を促進し、全体の利益率を向上させることができるでしょう。
3:売れる価格設定を作る7つのポイント

価格設定は、飲食店経営の成功を左右する重要な要素です。
ここでは、売れる価格設定を作るためのポイントを7つ紹介します。
3-1:原価×相場×付加価値で価格を設定
価格設定の際には、「食材原価」「市場相場」「店舗独自の価値」という3つの軸を考慮することが重要です。
食材の原価に加え、市場での競争力を意識した価格設定を行い、さらに独自の価値を加えることで、顧客に納得感を与えることができます。例えば、特別な素材や調理法、限定商品など、その価格の背景をしっかりと説明できることが重要です。
こうした価値を付加することで、相場より高い価格でも顧客の満足度を高め、売上を伸ばすことができます。
3-2:「中心価格帯」を設けて価格設定のぶれを抑える
価格帯を安定させるために、「中心価格帯」を設けることが効果的です。
よく売れるメニューを基にした価格レンジを設定し、その中に人気商品を集約します。極端に安いまたは高い価格設定を避け、適切な価格帯を設計することで、顧客が選びやすくなり、注文率が安定します。
また、エントリー、スタンダード、プレミアムの3段階価格構成を取り入れることで、顧客に選択肢を提供しつつ、売上を最大化することが可能です。
3-3:利益額×販売数で「店舗貢献度」を可視化
各メニューの「粗利」と「販売数」を掛け合わせることで、店舗への貢献度を明確にすることができます。これにより、利益をしっかり出せるメニューや、売れても利益が薄いメニューを把握し、戦略的なメニュー開発が可能になります。
貢献度の高い商品は、メニューの目立つ位置に配置し、視覚的に強調することで、顧客の目に留まりやすくなります。
3-4:看板メニューは収益より集客を優先する
看板メニューは、店舗の顔としての役割を果たし、集客に繋がります。原価率が高くても、集客力がある看板商品を持つことで、来店客を増やし、他のメニューで利益を確保する戦略(ロスリーダー戦略)が有効です。
看板商品の魅力を伝えるために、ネーミングやビジュアル、ストーリーも工夫して、価格に対する納得感を高めることが重要です。
3-5:セットメニュー・お得感の演出で単価アップ
セットメニューを導入することで、顧客にお得感を与えつつ、客単価を自然に上げることができます。単品価格とセット価格の差を心理的に小さく感じさせることで、顧客にセットを選ばせやすくします。
また、期間限定のプロモーションを活用し、セット選択率を高める工夫をすることも効果的です。
3-6:注文動線と価格帯のシミュレーションを行う
実際の来店シーンを想定し、メニューの配置や価格帯を戦略的に設計することが重要です。高い価格で引きつけ、安い価格の商品を選ばせる「アンカリング効果」を活用することで、売りたい商品を自然と選ばせることができます。
さらに、ラベルやデザインでおすすめ商品を強調し、顧客の注目を集めます。
3-7:価格設定は“定期的に見直す”もの
価格設定は一度決めたら終わりではなく、定期的に見直すことが重要です。仕入れコストや人件費、競合の動向、お客様の反応を観察しながら、必要に応じて価格を調整します。
価格を下げるのではなく、提供する価値を高めて価格を維持する方法を優先し、長期的な経営の安定化を図ります。
これらの鉄則を活用することで、飲食店の価格設定をより戦略的に行い、収益性と集客力を向上させることが可能です。
4:価格決定前にやるべき準備
飲食店の価格設定を成功させるためには、事前の準備が欠かせません。
ここでは、価格決定前に行うべき準備を4つのステップで解説します。
4-1:食材原価とロス・歩留まりの正確な把握
価格設定の基礎となるのは、食材の原価とそれに関連するロスや歩留まりの計算です。
単に仕入れ価格を基にするのではなく、調理過程でのロスや可食部の割合を考慮し、実際に使用される食材の原価を正確に把握することが重要です。具体的には、グラム単価を計算し、1食あたりで使用する量を明確にしていくことで、メニューごとの実原価を“見える化”します。
さらに、仕入れ価格の変動や季節による価格高騰にも対応できるよう、各食材のコストを定期的に管理することが必要です。
4-2:店舗コンセプト・客層・客単価の確認
価格設定は、店舗のコンセプトやターゲットとする客層との整合性が求められます。
「誰に」「どんな価値を提供するか」という店舗のコンセプトを明確にし、その上でターゲットとする客層に最適な価格帯を設定します。例えば、ビジネス層を狙うのであれば、質の高い食材を使用した少し高めの価格設定が適しているかもしれません。
また、1人あたりの平均客単価を基準とし、その範囲内で価格帯を設計することが顧客満足度を高める鍵となります。
4-3:競合店の価格設定・メニュー構成をリサーチ
競合店の価格設定やメニュー構成をリサーチすることは、自店の価格設定において非常に重要なステップです。同エリアや同業態の競合店を調査し、価格や提供内容、人気メニューの傾向を把握します。
ただし、価格をそのまま模倣するのではなく、競合と自店の違いや強みを整理し、差別化ポイントを見つけることが重要です。これにより、競合より高い価格設定であっても納得される要素を組み込み、強気の価格設定が可能になります。
4-4:注文パターン・導線を想定した設計
価格設定を成功させるためには、実際のお客様の注文パターンや店舗内での動線を想定し、それに応じたメニューの配置や価格帯を設計することが重要です。例えば、来店後から注文までの流れをシミュレーションし、どのメニューがどのタイミングで選ばれるかを想定します。売れ筋や利益率の高い商品は、注文が集中しやすい位置に配置し、視覚的に顧客の目を引くようにします。
複数人利用やランチ、ディナーなど、シーン別のオーダーパターンに合わせて価格帯を調整することも効果的です。
これらの準備を行うことで、飲食店の価格設定がより戦略的になり、収益性の向上につながります。
5:メニュー構成で利益を最大化する方法
飲食店のメニュー構成は、ただ料理を提供するだけでなく、利益を最大化するための重要な戦略の一部です。
ここでは、ドリンクの使い方、FD比率の改善、そして商品の配置について解説します。
5-1:ドリンクは利益率が高い=戦略的に使う
ドリンクの原価率は10〜20%程度と低く、フードよりも高粗利になりやすいのが特徴です。したがって、ドリンクは利益率向上のために戦略的に活用するべきです。例えば、セット販売やキャンペーンにドリンクを組み込むことで、全体の利益率を底上げできます。
また、アルコール・ソフトドリンクともに、売れ筋や高利益の商品をメニュー上で目立たせることで、売上増に貢献します。
ドリンクメニューの見せ方や提案方法を工夫することで、顧客の選択肢を広げ、利益率を向上させましょう。
5-2:FD比率を戦略的に改善して価格設定に反映する
FD比率(Food:Drinkの売上構成)を定期的に分析することは、利益構成の最適化に直結します。ドリンク比率が低い場合は、ドリンク付きセットやペアリング提案を導入し、自然にドリンク注文を増やす仕組みを作りましょう。
さらに、スタッフの声かけトレーニングや注文時のアップセル提案が、FD比率の改善に効果的です。
これにより、単にドリンクの売上を増やすだけでなく、全体の利益率を向上させることが可能です。
5-3:利益率の高い商品を「選ばれる位置」に配置
メニュー内での商品の配置は、売上に大きな影響を与えます。粗利率が高い商品は、メニューの中央や左上など、視線が集まりやすい場所に配置することが効果的です。
また、写真付きやおすすめマーク、ランキング表示など、視覚的に選ばれる工夫を施すことで、顧客の目を引きやすくなります。
さらに、利益が出にくい商品を避けさせるために、比較対象として高価格商品をメニューに加えることも有効です。
これにより、顧客が自然と利益率の高い商品を選ぶように促すことができます。
これらの方法を活用することで、飲食店のメニュー構成をより戦略的にし、利益を最大化することが可能です。
6:心理学を活かした“買いたくなる価格設定”の作り方

価格設定は、単なる数字以上の意味を持ち、顧客の購買行動に大きく影響を与える要素です。心理学を活用した価格設定は、顧客に対してお得感や魅力を感じさせ、購入を促すための有効な手段となります。
ここでは、心理学を活かした3つの価格設定テクニックを紹介します。
6-1:端数価格(980円)や切りの悪さを使う
端数価格は、例えば「1,000円」ではなく「980円」といった設定をすることで、顧客に心理的なお得感を与える基本的なテクニックです。人々はほとんどの場合、左から右へ数字を読み取るため、最初の数字が低いことで、全体として安く感じられる傾向があります。この「980円」は、「1,000円」よりも手頃に感じられ、購入意欲を高める効果が期待できます。
一方で、高価格帯の商品には、あえて切りの良い価格(例えば、2,000円)を設定することで、高級感や価値を強調することも可能です。
6-2:価格を目立たせすぎない表示法
価格表示は、顧客の注意を料理名や写真、説明文に向けられるようにすることが重要です。
例えば、価格を控えめに表示することで、顧客の関心を料理そのものに引きつけることができます。具体的には、価格フォントを小さめに設定し、色やフォントスタイルを控えめにすることで、全体のデザインに統一感を持たせます。
また、「円」の表記を外す、価格を右揃えで整列させるなどして、価格がメニュー全体に溶け込むような工夫を施すと良いでしょう。
6-3:メニュー配置や視線の動線を意識する
人間の視線は、一般的に「左上→右上→左下→右下」とZの字に動くと言われています。この視線の動きを利用して、売りたい商品をこの動線上に配置することで、自然と顧客の目に留まるように設計することができます。
さらに、写真やラベル、色使いを工夫することで、他の商品と視覚的に差別化し、注目度を高めることが可能です。これにより、顧客は自然と店舗が推奨する商品に目を向け、選択する確率が高まります。
これらの心理学を活かした価格設定のテクニックを活用することで、飲食店の価格設定をより効果的にし、顧客の購買意欲を引き出すことができます。
7:価格設定に関わる法律と表示の注意点
価格設定を行う際には、法律に基づいた表示が求められます。特に、総額表示義務や景品表示法、未成年へのアルコール提供など、法律に関わる事項は注意が必要です。
ここでは、法律に基づいた価格表示のポイントを解説します。
7-1:総額表示義務と税込表示ルール
2021年以降、飲食店を含む全ての小売業では、税込価格の表示が義務化されています。これは、消費者が支払う総額を一目で理解できるようにするための法律であり、税抜価格のみの表記は法律違反となる可能性があります。
メニュー表やPOP、Webサイト、SNSなど、あらゆるプラットフォームでの価格表示を統一し、消費者に誤解を与えないようにすることが重要です。
7-2:景品表示法と“お得感”の注意点
景品表示法は、消費者に誤解を与えるような不当表示を規制する法律です。「原価割れ」や「赤字覚悟」といった表現は、誤解を招く可能性があり、法律に抵触する可能性があります。
割引やキャンペーンを行う場合は、その根拠や条件を明記し、通常価格の基準や期間もはっきりと示すことが必要です。消費者に対して誠実な情報提供を心掛けましょう。
7-3:20歳未満へのアルコール提供禁止の法的注意
法律により、20歳未満へのアルコール提供は禁止されています。違反した場合には、罰則が科される可能性があるため、年齢確認を徹底することが求められます。
メニューには「※20歳未満の方へのアルコール提供はいたしません」といった表記を入れ、SNSキャンペーンやドリンク割引においても未成年への配慮が必要です。法律を遵守し、全ての顧客に安全で信頼できるサービスを提供しましょう。
これらの法律を遵守することで、飲食店の価格設定は消費者にとって信頼性の高いものとなり、長期的な成功につながります。
8:まとめ|「利益設計」としての価格設定を習慣化しよう
飲食店における価格設定は、単なる「値付け」ではなく、店舗の利益を最大化するための「利益設計」としての重要な役割を果たします。最後のまとめとしてそのポイントを以下に解説します。
価格設定は“売るための値付け”ではなく“儲けるための仕組み”
飲食店の価格設定は、売上を増やすための単純な手段ではなく、店舗の利益を確保し、持続可能なビジネスを実現するための戦略的な仕組みとして捉えるべきです。
価格は、経営戦略の一環として、原価や市場の動向、顧客の期待を考慮し、総合的に判断される必要があります。
数値と感覚の両面から設計し、定期的に見直すことが大切
価格設定は、原価率やFLコスト、FD比率といった数値データを基にした分析に加え、顧客の購買心理や市場トレンドを読み取る感覚的な要素も重要です。
定期的にこれらのデータを見直し、価格設定を調整することで、常に最適な価格を維持し、競争力を高めることができます。
原価率に縛られず、戦略的な値付けで経営を安定化させよう
原価率だけに依存した価格設定は、利益を損なう可能性があります。
むしろ、店舗のコンセプトやターゲット顧客に応じた戦略的な値付けを行うことで、経営の安定化を図ることが可能です。例えば、価値の高い看板メニューやお得感を演出したセットメニューを活用し、顧客の満足度を高めると同時に、収益性を向上させることができます。
以上のポイントを踏まえ、飲食店の価格設定を「利益設計」として捉え、継続的に見直すことで、店舗の長期的な成功を目指しましょう。これにより、収益性の向上だけでなく、顧客満足度やリピート率の向上にも貢献することが可能です。
それではこの記事は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。