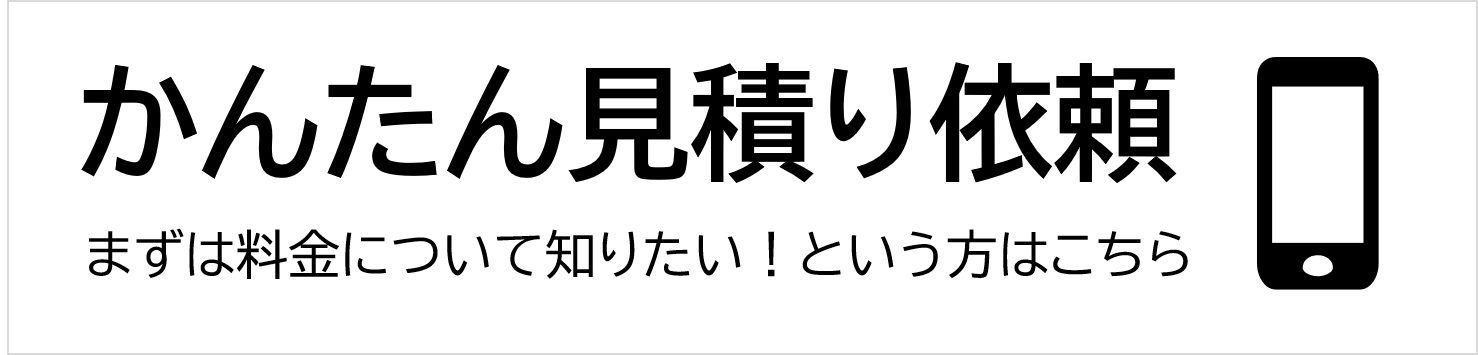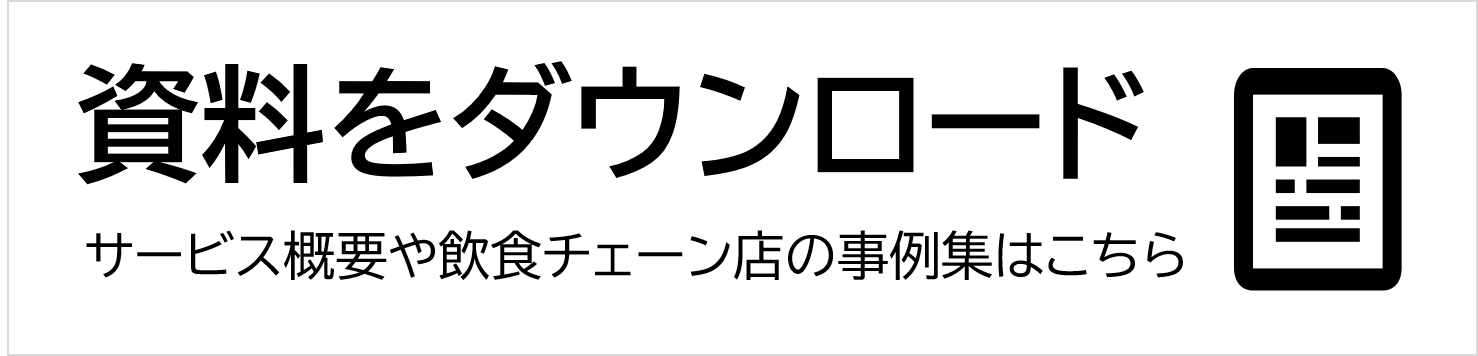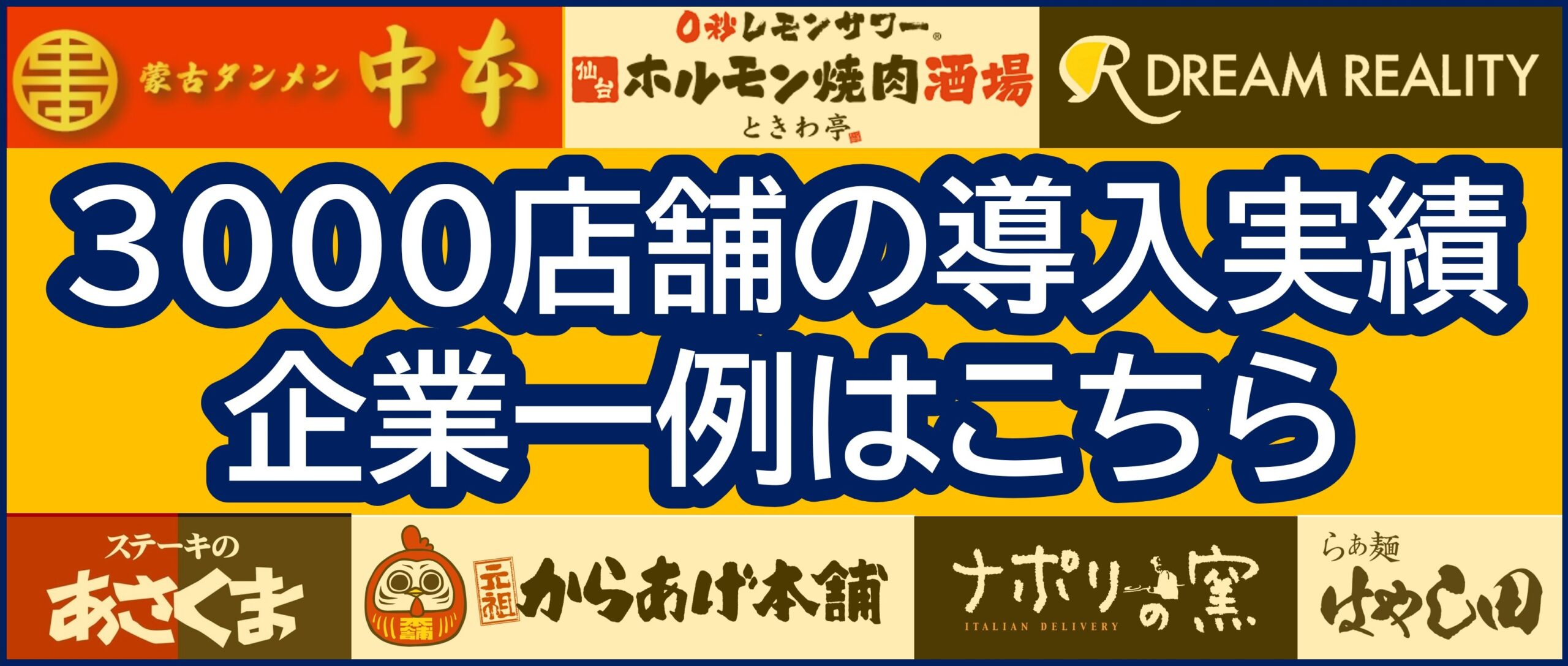飲食店の物件探し方ガイド|流れ・探し方のコツ・居抜き物件の選び方まで徹底解説
飲食店を開業したい方や、新たに店舗をオープンしたいと考えている方の中には、物件探しに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
適切な物件選びは、ビジネスの成功を左右する重要なステップです。
このガイドでは、飲食店の物件探し方を徹底解説し、流れや探し方のコツ、さらには居抜き物件の選び方までを網羅しています。
お客様のニーズに応えられる立地と空間を見つけることで、集客力を最大限に高める方法を知りたい方にとって必読の内容です。
この記事を読むことで、物件探し方のポイントを押さえ、理想的な飲食店舗を見つけるための具体的なステップを明確にする手助けとなります。あなたの飲食店開業や新店舗オープンの夢を実現するために必要な情報を、ぜひ手に入れてください。
目次
1.飲食店の物件探しが重要な理由
1-1. なぜ店舗物件が開業の成否を左右するのか
飲食店経営において「場所選び」は非常に重要なポイントです。
どんなに料理の味や接客に自信があっても、人が集まらない立地や条件の悪い物件を選んでしまえば、集客に苦労し、経営はすぐに行き詰まります。逆に、多少料理や接客に未熟な部分があっても、人通りが多くターゲットに合った立地であれば、一定の売上を確保できる可能性が高いのです。
また、物件は「後から簡単に変えられない」という点でも非常に重要です。移転や撤退には多額の費用と手間がかかるため、最初の選択がそのままお店の未来を決定づけることになります。
1-2. 立地・融資・資金計画との密接な関係
物件探しをする際には、立地や広さ、賃料だけを見て決めてはいけません。
特に注意すべきは「資金計画」とのバランスです。飲食店経営の固定費の中で、家賃は非常に大きな割合を占めます。一般的には「売上の10%以内」に抑えるのが目安とされ、これを超えると収益が圧迫されやすくなります。
また、金融機関から融資を受ける場合にも、物件は審査に直結します。「どんな場所で、どのくらいの賃料か」は返済可能性の判断材料になるため、物件選びと融資計画は常にセットで考える必要があるのです。
1-3. 近隣競合や将来開発計画まで考慮する視点
現在の条件だけでなく、未来の環境変化を想定することも大切です。
例えば、近隣に大型商業施設が新しくできる予定があるなら人の流れが変わる可能性があります。逆に、競合飲食店が急増しているエリアでは差別化が難しくなります。
物件選びの際には、「今の状態」だけでなく「3年後、5年後の街の姿」をイメージしながら判断することが、長期的な安定経営につながります。
2. 飲食店物件探しの全体の流れ

2-1. 出店コンセプトと条件を固める
最初に行うべきは「どんな店をどこに出すのか」を具体化することです。
ターゲット顧客(学生、ファミリー、ビジネスパーソンなど)、提供メニュー、客単価を設定し、それに見合った条件をリストアップします。
例:
・駅徒歩5分以内
・賃料は月額20万円以下
・座席数30席程度
・駐車場2台分あり
このように数字で条件を決めると、候補を効率的に絞り込めます。
2-2. 融資計画と並行して物件探しを進める
物件契約には保証金や前家賃などまとまった資金が必要です。そのため「融資が下りてから物件を探す」ではなく「融資計画と物件探しを同時進行する」のが鉄則です。
事業計画書を用意して銀行や信用金庫と交渉しながら、同時に不動産会社やポータルサイトで候補物件を探しましょう。これにより、希望の物件が出たときにすぐ申込できる状態を作れます。
2-3. 物件を探す
詳しくは後述しますが、物件探しの方法は大きく分けて5つあります。
・不動産会社に相談する
・不動産ポータルサイトを利用する
・知人やネットワークから紹介を受ける
・実際に街を歩く
・開業支援サービスの利用
複数の方法を併用することで、理想の物件に出会える確率は大幅に高まります。
2-4. 内見(内覧)の流れと基本ポイント
候補が決まったら必ず内見を行います。
チェックすべきポイントは以下です。
・昼と夜で人通りや治安が違わないか
・厨房やホールの動線は効率的か
・広さや座席数は想定客単価に合っているか
・設備や内装の状態は問題ないか
実際に現地を見ないと分からないことが多いため、必ず複数回、異なる時間帯で内見するのがおすすめです。
2-5. 入居申し込みと審査の流れ
良い物件は競争率が高く、申し込みはスピード勝負です。
事業計画書、身分証明書、印鑑証明、決算書など必要書類を揃えて、すぐに提出できる準備をしておきましょう。
また、申し込み時に条件交渉を行うことも可能です。例えば「保証金の分割払い」や「家賃のフリーレント期間」などは交渉次第で得られるケースがあります。
2-6. 賃貸借契約と必要書類(居抜きの場合は造作譲渡契約も)
入居が決まったら賃貸借契約を結びます。この際、保証金、礼金、前家賃、仲介手数料などの費用が発生します。
居抜き物件の場合は造作譲渡契約を締結し、譲渡対象となる設備や残置物を明確にします。「どこまで譲渡対象なのか」が曖昧だと、後でトラブルになりかねません。
2-7. 引き渡し時の注意点と手続き
引き渡し時には、必ず設備の動作確認を行いましょう。エアコン、換気扇、給排水、電気系統などは修繕費が高額になるため要チェックです。
また、電気・水道・ガスの名義変更や開通手続きも忘れずに進める必要があります。
3. 飲食店物件の種類と特徴

3-1. 居抜き物件
居抜き物件とは、前のテナントが使用していた設備や内装が残っている物件のことです。
最大のメリットは 初期費用を大幅に抑えられる 点にあります。厨房機器や内装をそのまま活用できれば、開業までのスピードも早く、資金効率が高いのが魅力です。
一方で、古い設備が故障していたり、不要な残置物の撤去費用が発生するリスクもあります。譲渡対象の範囲や費用負担を契約で明確にしておくことが重要です。
3-2. スケルトン物件
スケルトン物件は、前の設備や内装をすべて撤去した状態で引き渡される物件です。
自由にレイアウトでき、コンセプトを反映した内装を実現できるのが大きな魅力です。
ただし、内装工事費用や工期がかかるため、初期投資が大きくなる点がデメリットです。オリジナル性を重視したい人には向いていますが、十分な資金力が必要です。
3-3. 間借り物件
既存店舗の一部を借りて営業するのが「間借り物件」です。
初期費用を抑えられ、短期間で開業できるのが最大の利点です。最近では「間借りカレー」などで注目を集めています。
ただし、営業時間やメニューに制限があったり、独自性を出しにくいというデメリットもあります。テストマーケティング的に小規模で始めたい方には有効な選択肢です。
4. 良い物件を見つけるための探し方の手段

4-1. 不動産会社に相談する
物件探しの基本は不動産会社です。地域密着型の不動産会社は、エリアの事情に詳しく、未公開情報を持っていることも多いです。
また、飲食店専門のテナント仲介業者は、飲食に特化したノウハウがあり、効率的に物件を探すことができます。
4-2. 不動産ポータルサイトを活用
近年はポータルサイトを使った物件探しも一般的です。
「飲食店ドットコム」「居抜き店舗ドットコム」「テンポダス」「店舗ネットワーク」など、飲食店向けに特化したサイトも存在します。
条件を細かく設定して検索できるため、効率的に候補を見つけられるのがメリットです。複数サイトを比較し、情報の鮮度や更新頻度をチェックしましょう。
4-3. 自分で街を歩いて探す
実際に街を歩き、シャッターに貼られた「テナント募集」や空き予定の張り紙を探す方法も侮れません。
オンラインには出ていない物件情報に出会えるチャンスがあるからです。
また、現地の人通りや客層を肌で感じられるため、ネット検索では得られない一次情報が得られます。
4-4. 知人や地域ネットワークからの紹介を活用
業界仲間や商店街のつながりから紹介を受けることで、非公開物件や条件の良い案件に出会えることもあります。
信頼関係のある紹介はトラブルも少なく、効率的な探し方のひとつです。
4-5. 開業支援サービス・専門サービスの利用
最近は、開業支援サービスや飲食店専門のマッチングサービスを利用するケースも増えています。
物件紹介だけでなく、融資の相談や運営アドバイスまでサポートしてくれるため、初めて開業する人にとって心強い存在です。
特に、未公開物件や交渉サポートを提供しているサービスは競合より先に動ける利点があります。
5. 飲食店物件探しで失敗しないコツ

5-1. 条件を明確にし優先順位をつける
まずは「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」を明確にしましょう。
例えば「駅から徒歩5分以内」は必須だが、「駐車場あり」は妥協可能、といった具合です。これを決めておくと、効率的に物件を絞り込めます。
5-2. 妥協点を決めて選択肢を広げる
完璧な物件を探そうとすると時間もコストもかかります。大切なのは「どこで妥協できるか」を事前に考えることです。
例えば、賃料が少し高くても立地が抜群なら検討する、など柔軟な姿勢が成功への近道です。
5-3. 情報収集は継続が鍵
良い物件は突然出てきて、すぐに埋まってしまいます。ポータルサイトやSNSを日々チェックする習慣をつけ、常に最新情報を追うことが重要です。
5-4. 未公開物件へのアプローチ
信頼できる不動産会社や業者と良好な関係を築くことで、未公開の物件を優先的に紹介してもらえるケースがあります。
こうした「水面下の情報」にアクセスできるかどうかが、競合との差を生むポイントです。
5-5. 経験者や専門家に相談して情報精度を高める
飲食店を経営している知人や専門家に相談することで、自分では気づけない視点や成功・失敗事例を知ることができます。特に初めて開業する人は、必ず相談できる相手を見つけておきましょう。
6. 居抜き物件を選ぶときのチェックポイント

6-1. 設備・内装の状態を必ず確認
居抜き物件の最大の魅力は、前の店舗が使っていた厨房設備や内装を活用できることです。しかし、中には長年使われて劣化している設備も多く、そのまま使用するとすぐに修理費用が発生してしまうケースがあります。
特に注意すべきは、水回りや電気設備です。水漏れや排水不良、電気容量不足などは改修に大きなコストがかかります。必ず業者に同行してもらい、専門的なチェックを受けることをおすすめします。
6-2. 造作譲渡契約の内容を精査する
居抜き物件を引き継ぐ場合、多くは「造作譲渡契約」が結ばれます。これは、内装や設備をそのまま譲り受ける契約ですが、譲渡金額や対象範囲が曖昧だとトラブルのもとになります。
「冷蔵庫は譲渡対象か?」「食洗機は含まれるのか?」など細かく確認し、契約書に明記しておくことが大切です。譲渡金が妥当かどうかは、複数業者に見積もりを取って判断しましょう。
6-3. 残置物の有無と費用負担を確認する
前テナントが置いていった残置物は、不要であれば撤去しなければなりません。ここで問題となるのが「誰が撤去費用を負担するのか」です。場合によっては数十万円単位になることもあるため、契約前に明確にしておきましょう。
6-4. 原状回復義務の有無を事前に確認
契約を終了する際に「原状回復義務」があるかどうかも重要です。例えば「壁や床をすべてスケルトンに戻す」契約であれば、退去時に数百万円の費用がかかることもあります。開業時だけでなく、閉店時のリスクも想定して契約条件を確認しましょう。
6-5. 昼夜で周辺環境や治安をチェックする
物件自体が良くても、立地環境が合わなければ経営は苦しくなります。昼間は人通りが多くても夜は閑散とするエリアもありますし、その逆もあります。時間帯を変えて内見を行い、治安や客層の違いも確認することが大切です。
7. 内見(内覧)時に確認すべきポイント

7-1. 立地・動線・周辺競合環境
まずは店舗の立地がターゲット顧客の動線上にあるかを確認しましょう。駅からの導線、駐車場の有無、バス停や学校・オフィスからの距離など、日常的に人が流れる経路にあるかどうかが集客に直結します。
また、周辺に強力な競合店が存在する場合は差別化が難しくなります。競合調査をしながら、同じ業態が集中しているか、逆にブルーオーシャンなのかを見極めましょう。
7-2. 広さ・間取り・導線の適正
店舗の広さや間取りは、コンセプトと直結します。例えば、客単価が高めのレストランなら1人あたりのスペースを広めに確保する必要がありますし、回転率重視のラーメン店なら厨房から席までの導線効率を優先すべきです。
実際に店内を歩きながら、スタッフ動線と客導線が交錯しないか確認しておきましょう。
7-3. 騒音・匂い・近隣住民との関係
飲食店のトラブルで多いのが「騒音」と「匂い」です。特に焼肉やラーメンの店舗では排気ダクトや換気設備が不十分だと、近隣住民から苦情が出るリスクがあります。
開業前から近隣との関係性を意識し、トラブルを未然に防ぐ準備が必要です。
7-4. 許可申請や法規制に適合しているか
用途地域や消防法、建築基準法などの制約を満たしているかも必ず確認しましょう。特に居抜き物件では、前店舗が飲食以外だった場合、営業許可が下りない可能性もあります。行政への確認も内見時に進めておくと安心です。
7-5. 複数回・異なる時間帯での内見の重要性
昼と夜、平日と休日で街の雰囲気や客層は大きく変わります。昼は学生が多いが夜はサラリーマンが中心、休日はファミリー層が多い、というように時間帯で集客層が異なることは珍しくありません。最低でも2〜3回は異なる時間帯で内見しましょう。
8. 飲食店の空き物件が出やすい時期

8-1. 年度末(3月)、9月、2月、8月が狙い目
飲食店の退去や移転は年度末や決算期に集中する傾向があります。特に3月や9月は、新しい期を迎えるために契約を整理する企業や店舗が多く、空き物件が出やすい時期です。2月や8月も繁忙期が終わり閑散期となるタイミングなので撤退が発生しやすくなります。
8-2. 探す人が少ない閑散期を狙うメリット
繁忙期を避けた時期は、物件を探すライバルが少なく競争率が下がります。そのため、好条件の物件を落ち着いて検討できるメリットがあります。
8-3. ネットに掲載されない物件は「足」で探す重要性
人気の物件はネットに掲載される前に決まってしまうことも多いです。街を歩き、直接「貸店舗」の張り紙や地域不動産会社に問い合わせることで、まだ公開されていない情報を得られる場合があります。
9. 資金計画とキャッシュフロー戦略
9-1. 物件取得費・内装工事費・開業費用・運転資金を明確化
飲食店の開業には「物件取得費」「内装工事費」「開業費用」「運転資金」が必要です。
・物件取得費:保証金、礼金、前家賃、仲介手数料
・内装工事費:厨房、空調、内装デザインなど
・開業費用:備品、食材仕入れ、広告宣伝費
・運転資金:売上が安定するまでの3〜6か月分
これらを合算して資金総額を把握することが、経営リスクを減らす第一歩です。
9-2. 初期投資とランニングコストのバランスを考える
家賃は「売上の10%以内」が目安とされています。家賃比率が高すぎると、いくら売上が上がっても利益が残らない構造になってしまいます。
また、初期投資で資金を使いすぎると、運転資金が足りずに資金ショートを起こすリスクがあります。開業時の投資とランニングコストのバランスを冷静に判断することが必要です。
9-3. キャッシュを手元に残して開業する資金管理方法
開業直後は想定より売上が安定せず、赤字が続くこともあります。そのため、最低でも3〜6ヶ月分の運転資金を手元に残した状態でスタートするのが理想です。これにより、予期せぬトラブルがあっても持ちこたえることができます。
9-4. 無理のない返済計画と資金調達のタイミング
金融機関の融資は、複数社を比較して条件を見極めましょう。金利や返済期間だけでなく、保証人や担保条件の有無も重要です。無理のない返済計画を立て、開業後のキャッシュフローを圧迫しないように調整しましょう。
10. まとめ|飲食店物件探しは情報と準備が成功の鍵
飲食店の物件探しは、単なる「場所選び」ではなく、経営そのものを左右する大きな要素です。
・出店コンセプトを明確にする
・物件探しの流れを理解し、複数の方法で探す
・内見や契約では細部まで確認し、トラブルを未然に防ぐ
・空き物件が出やすい時期や未公開情報を狙う
・資金計画を立て、キャッシュフローを意識する
最終的には「お店のコンセプトに合った立地を選ぶこと」が成功の決め手です。
情報収集と準備を徹底し、長期的に安定した経営を実現できる物件を見つけましょう。
それではこの記事は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。