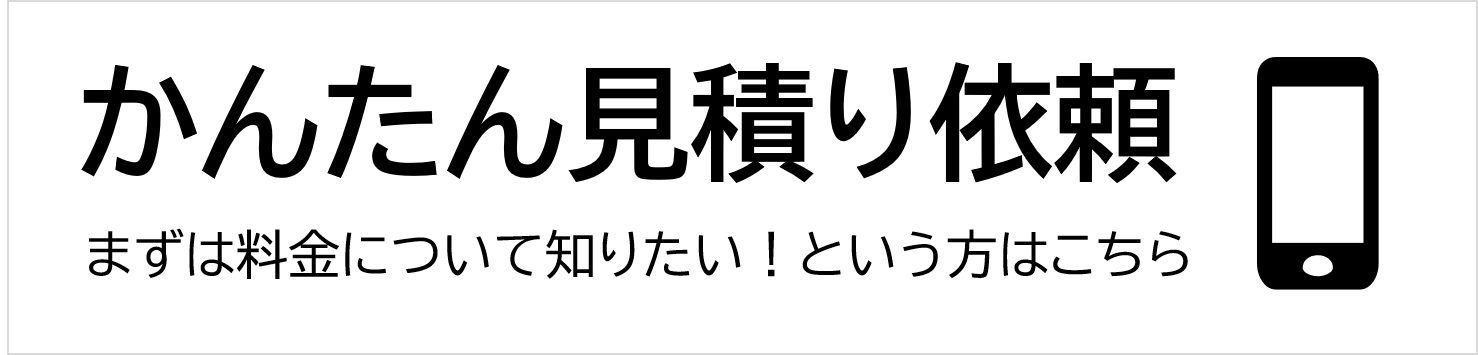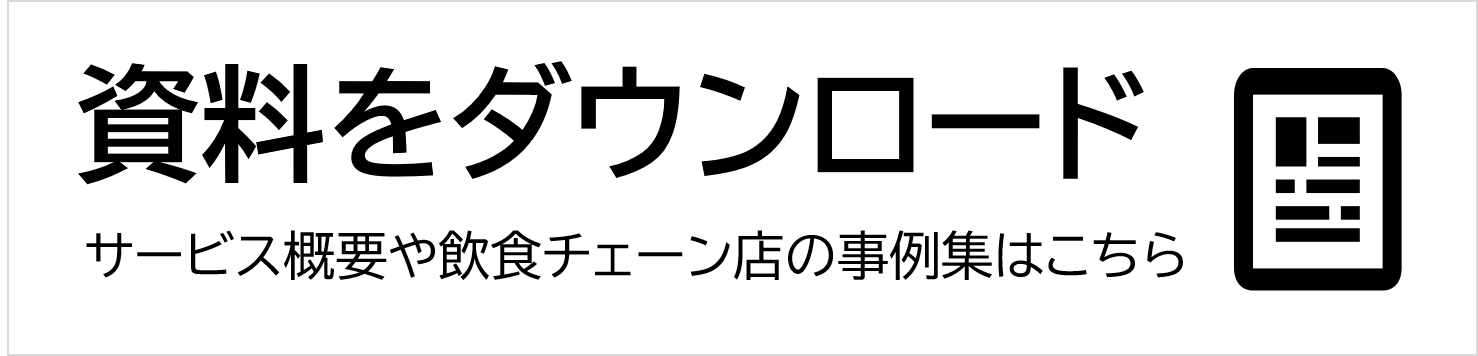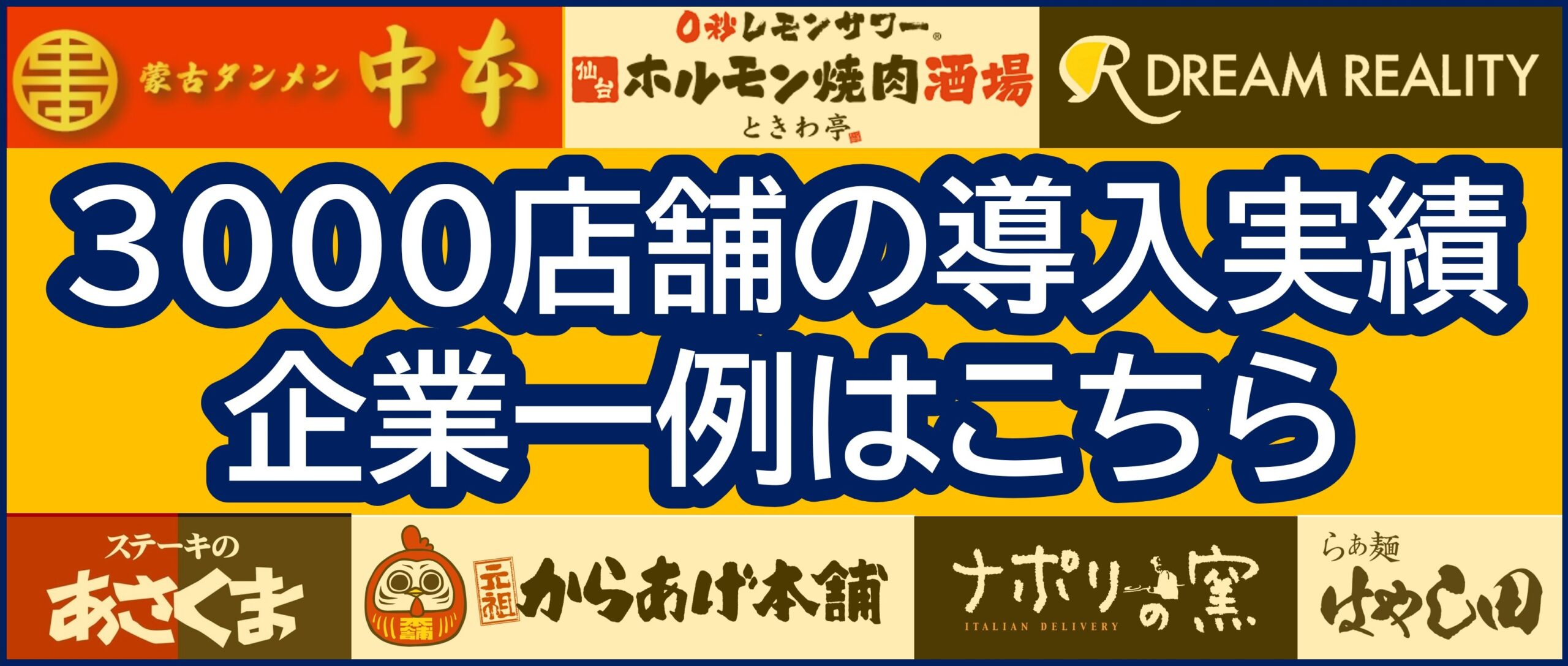後継者のいない飲食店は廃業するしかない?廃業を避ける現実的な方法
日本全国で多くの飲食店が抱える共通の課題、それは「後継者のいない」状態に陥っていることです。
後継者がいないために、長年愛されてきたお店が廃業を余儀なくされるケースが増加しています。
この後継者がいない問題に直面している飲食店オーナーの皆様、廃業以外にどんな選択肢があるかご存知ですか?
本記事では、後継者のいない飲食店が取るべき具体的なステップと、廃業を回避するための現実的な解決策を詳しく解説します。
店舗の未来を守るための方法を知ることで、不安を解消し、次なる一歩を踏み出すためのヒントを手に入れてください。
目次
1:飲食店の後継者不在はなぜ起きるのか?

1-1:個人経営の多さと高齢化
日本の飲食店の多くは個人経営で成り立っており、家族経営や一人で運営している小規模店舗が多数を占めます。そのため、経営者自身が高齢になっても現役で店を切り盛りしているケースが多く見られます。しかし、年齢とともに体力面や健康面に不安が出てくると、引退を考えざるを得なくなります。
特に地方では、70代以上の店主が「体が動くうちは続けるが、跡継ぎがいないので閉めるしかない」と話す事例も多く、後継者不在が事業継続の大きな障壁になっているのです。
1-2:跡継ぎがいない・継ぎたがらない理由
「飲食店を継がせたくても、子どもが他業種に就職していて地元に戻ってこない」「そもそも子どもが店を継ぎたがらない」──そんな声を多く耳にします。実際に、次世代が飲食業を選ばない背景には、労働環境や将来性への不安があります。
飲食業は労働時間が長く、休みも少ないというイメージが根強く、働く世代から敬遠されがちです。さらに、経営リスクが高いという現実も、家族に継がせることを躊躇させる要因となっています。店主自身が「子どもには苦労させたくない」と考え、あえて継がせない判断をするケースも少なくありません。
1-3:業界イメージ・人材流出の背景
飲食業界全体が人材確保に苦労している背景には、業界イメージの問題があります。長時間労働や低賃金といったネガティブな印象が広がっており、若年層からの人気は決して高くありません。
また、都市部への人口流出が進む中、地方ではさらに人材不足が深刻化しています。飲食店の運営には体力・知識・経験が必要であり、簡単に誰でも継げる仕事ではないとされることも、後継者が見つからない理由のひとつです。
これらの要素が複合的に絡み合い、結果として「後継者がいない飲食店」が増加し続けているのです。
2:後継者がいないとどうなる?廃業リスクと現実

2-1:廃業を選ぶ飲食店の割合と傾向
中小企業庁の調査によれば、後継者不在を理由に廃業を選ぶ中小企業は全体の3割近く(日本政策金融公庫のデータより)とも言われています。飲食業界でも同様に、後継者が見つからず廃業に追い込まれるケースが年々増加しています。
特に個人経営の飲食店では、他人に譲るという発想がそもそも少なく、「自分の代で終わりにする」と考える店主も多いのが実情です。そのため、せっかく地域で愛されてきた店でも、継ぐ人がいなければ閉店を余儀なくされてしまうのです。
2-2:閉店時にかかるコスト(原状回復費、契約解除など)
廃業は単に「店を閉める」だけでは終わりません。テナント契約をしている場合、原状回復義務があるため、店舗の内装をすべて解体して返却する必要があります。その費用は一般的に50万〜100万円以上かかると言われています。
さらに、リース契約をしている設備の解約手続きや、従業員の退職金、取引業者への支払い残など、閉店に伴う経済的負担は非常に大きいのが現実です。こうしたコストを考えると、「売却による譲渡」は実は非常に合理的な選択肢と言えるでしょう。
2-3:廃業後の影響:従業員・常連客・地域コミュニティ
店の廃業は、経営者だけでなく、そこで働くスタッフや通っていた常連客にも大きな影響を与えます。従業員は仕事を失い、生活の再建を迫られることになります。また、地域住民にとっては「いつもの店がなくなる」という喪失感も大きく、コミュニティの活力が失われてしまうこともあります。
とくに地方では、老舗飲食店が地域の交流の場として重要な役割を担っている場合も多く、廃業は地域文化の喪失にもつながります。
3:廃業を避けるための4つの現実的な方法

3-1:親族・家族への承継(準備と教育がカギ)
親族や家族への事業承継は、もっとも古くから行われてきた方法であり、家業としての継続性や信頼性の面でメリットがあります。子どもや親族が後継者となることで、経営方針や理念を自然と引き継ぎやすく、既存スタッフや顧客も安心して受け入れやすい傾向があります。
一方で、家族間で「誰が継ぐのか」「どこまで経営に関与するのか」などで意見が食い違うと、感情的な対立に発展するリスクもあります。また、本人にやる気や適性がなければ、無理に継がせても経営が傾く可能性もあるため注意が必要です。
親族承継を成功させるためには、早期に意思確認を行い、段階的な教育と引き継ぎを進めることが重要です。後継者候補がやりたいかどうか、何が不安なのかをしっかり話し合い、育成プランを立てて進めることが“後悔しない選択”につながります。
3-2:従業員への承継(モチベーションと資金支援が課題)
長年働いてきた従業員や店長など、内部のスタッフに事業を引き継ぐ「従業員承継」も、有効な選択肢のひとつです。現場を知り尽くしており、既存の顧客やスタッフとの関係性を維持しながら自然な形での継承が可能です。
しかし、従業員が経営を引き継ぐためには「資金面」「経営知識」「責任の重さ」など、乗り越えるべきハードルが複数あります。実際、「経営に自信がない」「借金を抱えるのが怖い」といった理由で辞退されるケースも少なくありません。
成功事例の多くでは、段階的な教育と支援体制が整っていたことが共通しています。融資制度や補助金、公的な後押しを活用しながら、後継者としての自信と実力をつけてもらうプロセスが欠かせません。
3-3:M&A(事業承継型):第三者への売却・引き継ぎ
親族も従業員も引き継げない場合に有力なのが、M&Aを活用した「第三者承継」です。事業を売却することで、現経営者は店舗の“のれん”を守りながら引退でき、買い手にとっては既存の経営基盤や顧客、従業員を引き継いだ状態からスタートできるという双方にメリットのある仕組みです。
特に近年は、飲食店専門のM&A仲介サービスも増加しており、個人経営の小さな店舗でも売却実績が豊富にあります。譲渡価格は店舗の立地・業績・ブランドなどによって異なりますが、廃業よりも費用面・心理面ともに「前向きな終わり方」ができる手段として注目されています。
成功のカギは、信頼できる仲介業者の選定と、事前準備です。帳簿の整理、設備の状態確認、従業員への説明など、引き継ぎがスムーズになるよう段階的に準備を整えておくことが求められます。
3-4:地域・業界のマッチングサービスの活用
最近では、**公的機関や民間サービスによる「後継者マッチングプラットフォーム」**が数多く登場しています。特に「事業引継ぎ支援センター」などの公的機関は全国に設置されており、無料で相談やマッチングの支援を受けることができます。
また、飲食業に特化したサービスでは、専門料理(ラーメン、焼肉、フレンチなど)のノウハウや厨房設備を理解した希望者とマッチングされる仕組みが整ってきています。マッチングの成功率を高めるには、募集内容や条件を明確にしておくことが大切です。
「誰かに引き継いでほしいけど、どこに声をかけたらいいかわからない」と悩む前に、まずはこうしたサービスを活用して情報を開示し、可能性を広げていくことが重要です。
4:飲食店が事業承継・M&Aを進める際の注意点

4-1:早期の準備と計画立案
事業承継で最も大切なのは「早めの準備」です。経営者が健康なうちに準備を進めることで、万が一の事態にも柔軟に対応でき、選択肢の幅も広がります。
事業承継の準備には通常、5~10年程度の期間が必要(中小企業庁のガイドラインより)とされており、「そろそろ引退を考えたい」と思ったタイミングからでは遅い場合もあります。
準備ではまず、以下の項目を整理しましょう。
・経営理念や店舗のこだわり、歴史などの“見えない資産”
・財務諸表や契約書、営業許可などの“見える情報”
・スタッフや仕入れ先との関係性
これらを文書やデータでまとめておくことで、後継者候補やM&A相手にとっても安心材料となり、スムーズな交渉が可能になります。
4-2:従業員・取引先との信頼関係と情報共有
事業承継をスムーズに進めるためには、従業員や取引先との信頼関係が不可欠です。後継者が決まっていない段階で情報を開示しすぎると、不安や混乱を招く恐れもあるため、タイミングと伝え方には細心の注意が必要です。
一方で、承継が決まった段階では、関係者に丁寧に説明し、協力を得ることが重要です。とくにスタッフに対しては、雇用条件がどうなるか、店舗運営がどう変わるのかをしっかり伝えることで、信頼関係を維持することができます。
また、長年付き合いのある取引先との関係が継続できるかどうかも、承継の成否を左右するポイントです。新しい経営者がスムーズに引き継げるよう、引継ぎ期間中に紹介や契約見直しを行うことも検討しましょう。
4-3:情報管理と機密保持の徹底
M&Aや事業承継の過程では、財務情報・店舗売上・仕入れ先・従業員の個人情報など、外部に漏れてはならないデータが多く存在します。
そのため、**秘密保持契約(NDA)**の締結や、アクセス権の制限など、情報管理の体制を整えておくことが必須です。
特に、M&Aで複数の候補者とやり取りする際には、事前に「どこまで開示するか」「どのタイミングで伝えるか」を明確にしておかないと、社内外でトラブルが発生する原因にもなります。
事業承継に関わる情報は、常に「必要最小限・段階的に開示」を基本とし、信頼できる仲介者や専門家のアドバイスを受けながら進めましょう。
4-4:公的支援制度や専門家の活用
事業承継に不安を感じる経営者のために、国や自治体が提供する支援制度が多数存在します。たとえば、中小企業庁が運営する「事業引継ぎ支援センター」では、無料相談やM&Aのマッチング支援、書類作成のサポートなどを行っています。
また、事業承継税制を活用すれば、相続税や贈与税の負担を軽減しながら店舗を引き継ぐことも可能です。条件を満たせば、税負担が最大100%猶予される場合もあるため、必ず専門家に相談することをおすすめします。
さらに、税理士・中小企業診断士・M&Aアドバイザーなどの専門家と連携することで、法的・財務的なリスクを回避し、より確実で円滑な承継が実現します。
5:どこに相談すべきか?支援機関・専門家の活用法

5-1:公的支援制度の活用(事業引継ぎ支援センターなど)
後継者が見つからず廃業を考える経営者にとって、まず頼るべきは公的支援機関です。
なかでも「事業引継ぎ支援センター」(中小企業庁が全国47都道府県に設置)は、無料で事業承継やM&Aの相談に応じてくれます。
主な支援内容は以下の通りです。
・後継者候補のマッチング支援
・事業承継に必要な計画書や資料作成のアドバイス
・税制や補助金の活用方法の案内
・専門家(弁護士・税理士・中小企業診断士など)との連携
廃業ではなく事業を残したいと考えるのであれば、最初の一歩は公的機関への相談が安心かつコストもかかりません。
5-2:金融機関・商工会議所への相談
取引先の金融機関や地域の商工会議所も、事業承継の重要な相談先です。
銀行は融資だけでなく、M&Aの仲介や後継者紹介のネットワークを持っていることが多く、地域企業同士をつなぐ役割も果たします。
また、商工会議所は「事業承継特別相談窓口」を設けている場合があり、税制優遇や補助金の情報提供、専門家紹介などをワンストップで受けられます。
特に地域密着の金融機関や商工会議所は、地元の人脈に強いため、「地元で事業を続けたい後継者候補」を見つけやすいのがメリットです。
5-3:M&A仲介会社・専門プラットフォームの活用
近年は、飲食業界に特化したM&A仲介会社やオンラインのマッチングプラットフォームが数多く登場しています。
これらを利用すれば、全国規模で「事業を引き継ぎたい人」を探すことが可能です。
メリットは以下の通りです。
・インターネットを通じて広範囲に後継者候補を探せる
・買い手と売り手の情報を効率的にマッチングできる
・契約や交渉の専門サポートが受けられる
一方で、仲介手数料が数%かかるケースや、情報公開のリスクもあるため、利用前にサービス内容をよく確認することが大切です。
特に飲食業は立地・ブランド・味の再現性など独自の評価基準があるため、飲食M&Aの実績が豊富な仲介会社を選ぶことが成功のカギになります。
5-4:税理士・中小企業診断士・弁護士など専門家
事業承継のプロセスには、税務・法務・経営戦略といった複雑な課題が絡みます。そのため、専門家の力を借りることが不可欠です。
税理士:相続税や贈与税の軽減策、事業承継税制の活用、財務状況の整理
中小企業診断士:経営診断、後継者育成プラン、経営改善計画
弁護士:契約やトラブル防止、株式譲渡・賃貸契約の法務面チェック
M&Aアドバイザー:買い手探し、企業価値評価、交渉支援
「専門家に依頼すると費用がかかる」と不安に思う経営者も多いですが、結果的に廃業コストや失敗リスクを大幅に下げられるため、むしろ費用対効果は高いといえます。
6:まとめ|後継者がいないなら“譲る勇気”を
飲食店の後継者不在は、少子高齢化や人手不足といった社会的背景もあり、ますます深刻な課題となっています。
しかし、「親族や従業員への承継」「M&A」「マッチングサービス」など、廃業を避けるための選択肢は複数存在します。
大切なのは、**「できるだけ早い段階で準備を始めること」**です。財務や契約の整理、後継者候補との話し合い、公的支援制度の活用などを進めることで、安心してバトンを渡すことができます。
後継者がいないからといって、必ずしも廃業を選ぶ必要はありません。
“残したい店の価値”を見極め、未来につなぐ方法を検討することで、あなたの飲食店は新たな形で存続していくことができるのです。