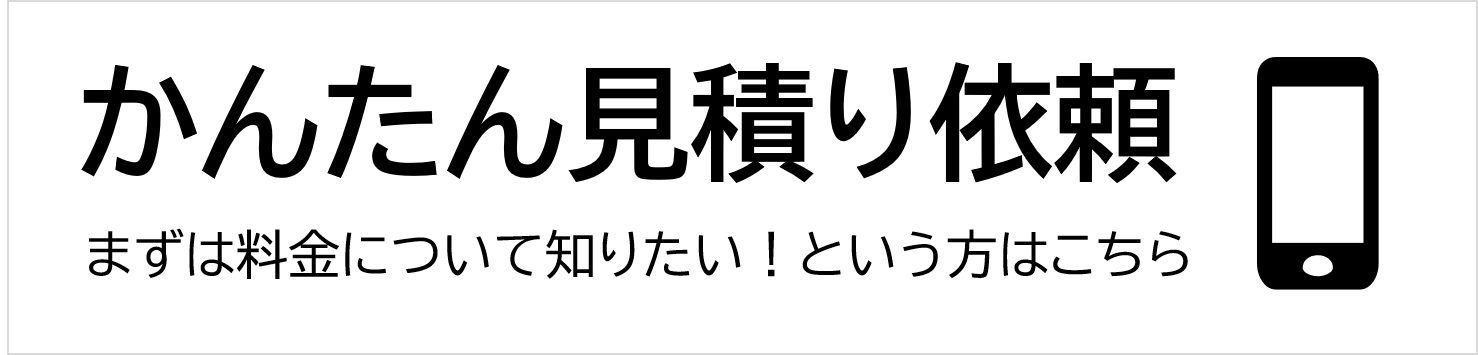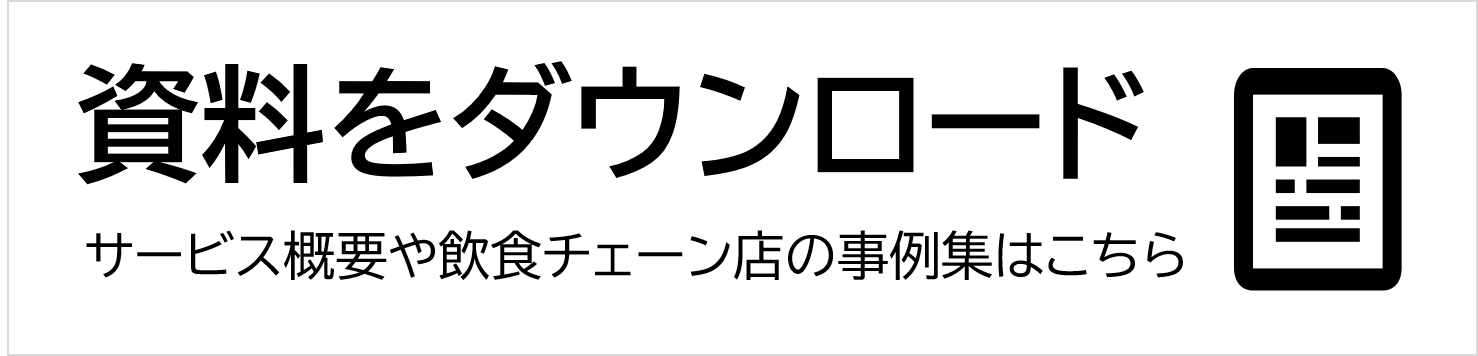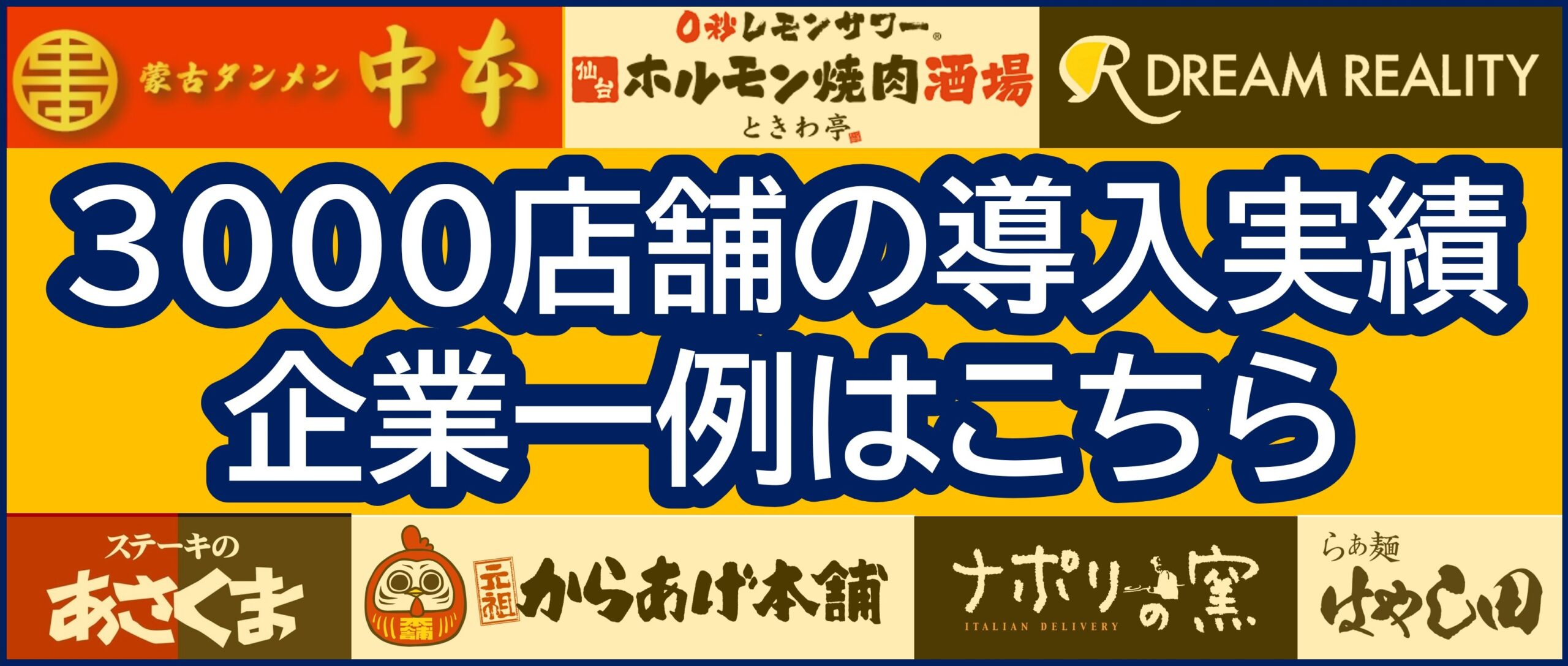オーナーチェンジで飲食店を取得する手続きや失敗しないポイント
飲食店のオーナーチェンジを検討している方にとって、手続きや交渉の複雑さは大きな不安要素です。
しかし、適切な知識と準備があれば、スムーズに飲食店を取得することが可能です。
この記事では、オーナーチェンジの基本から具体的な手続き、交渉のポイントまでを詳細に解説します。
飲食店のオーナーチェンジは、成功すれば新たなビジネスチャンスの扉を開くもの。失敗しないための秘訣を知ることで、あなたの投資が成功に繋がるようなヒントを提供します。
この記事を読むことでオーナーチェンジのプロセスを理解し、飲食店取得の際に直面する問題を解決するための知識を得ていただければ幸いです。
目次
1:飲食店オーナーチェンジとは?【取得前に知るべき基本知識】

1-1:オーナーチェンジとは?仕組みと用語をわかりやすく解説
飲食店におけるオーナーチェンジとは、営業中の店舗をそのまま新しいオーナーが引き継ぐことを意味します。通常の新規開業とは異なり、内装・厨房機器・従業員・顧客基盤など、既存の経営資源を維持したまま事業を継承できる点が特徴です。
一般的に、オーナーチェンジは造作譲渡契約を結ぶことで実施され、売主(現オーナー)は店舗の造作や設備を買主に譲渡し、買主は店舗の運営を引き継ぎます。新規に事業を立ち上げるよりもスムーズにスタートできるため、時間やコストを抑えて出店したい方にとっては魅力的な手法です。
1-2:居抜き物件との違い
オーナーチェンジとよく混同されるのが「居抜き物件」です。大まかに以下のような違いがあります。
【オーナーチェンジ】
・店舗の経営権や契約関係(賃貸借契約、従業員、取引先など)をそのまま新オーナーに引き継ぐこと。
・事業そのもののバトンタッチに近い。
・造作や設備だけでなく、店舗の営業許可や顧客、場合によっては従業員も引き継げる。
【居抜き物件】
・店舗の内装や設備、什器などを残した状態で物件を貸す(または売る)こと。
・前オーナーの事業は終了していて、契約や人材、顧客は基本的に引き継がれない。
・「ハコ(内装・設備付き物件)」を借りて新しいビジネスを始めるイメージ。
1-3:オーナーチェンジでの主な取得方法
オーナーチェンジにはいくつかの取得手段があります。最も一般的なのは「造作譲渡」です。これは内装や設備といった物的資産のみを引き継ぐ方法で、手続きが比較的簡単なため初心者にも扱いやすい手法です。
さらに「株式譲渡」は、法人として運営している店舗を法人ごと譲り受ける形になります。会社の資産・負債・契約もそのまま引き継がれるため、注意点も多いですが、営業許可などの変更が不要な点は大きなメリットです。
いずれの方法も、それぞれにメリット・デメリットがあるため、自身の事業規模や目的に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
2:飲食店オーナーチェンジのメリット・デメリット

2-1:メリット① 開業コストの大幅削減
オーナーチェンジの最大の魅力は、開業にかかる初期コストを大幅に抑えられる点です。通常の新規開業では、スケルトン状態から内装・厨房機器・電気ガス水道の整備などを一から行う必要があり、数百万円〜1000万円以上の資金が必要となることも珍しくありません。
しかし、オーナーチェンジであれば、内装・設備が既に整った状態で引き継げるため、大規模な工事費は不要です。さらに、営業が継続されたままの引き継ぎとなるため、物件が空室になって家賃だけが発生する“空家賃”のリスクも回避できます。
これは「原状回復コストを払って退去したい売主」と「初期費用を抑えて開業したい買主」の利害が一致するWin-Winの関係と言えるでしょう。
2-2:メリット② 従業員・顧客をそのまま引き継げる可能性
オーナーチェンジでは、既存のスタッフや常連顧客を引き継げるケースが多くあります。飲食店において、店舗運営のスムーズさを左右するのが「現場のスタッフ」と「リピーター客」の存在です。
例えば、ホールスタッフやキッチン担当者がそのまま残ってくれることで、メニューやオペレーションの引き継ぎがスムーズになります。さらに、顧客にとっても顔なじみのスタッフが継続して働いていることは安心感につながり、再来店を促す要因になります。
これは、新規開業時に最も大変な「スタッフ採用・育成」と「新規集客」の手間とコストを大きく軽減できる、大きなアドバンテージです。
2-3:デメリット① 設備の老朽化・隠れた不具合リスク
一方で、既存の設備を引き継ぐということは、劣化や故障リスクも合わせて抱えることを意味します。見た目は綺麗でも、排気ダクトや冷蔵庫、給湯器などの内部設備が老朽化していた場合、後から修理や交換で想定外の出費が発生する可能性も。
契約前には「設備チェックリスト」などをもとに、設備ごとの状態を現地でしっかり確認し、必要に応じて専門業者の同行査定を依頼するのが望ましいです。
2-4:デメリット② 既存のブランドやオペレーションの影響を受ける
既存の店舗を引き継ぐということは、その店舗の「雰囲気」「ブランドイメージ」「メニュー」「接客スタイル」などをある程度踏襲せざるを得ない場合があります。
例えば、前オーナーの個性が強く出ていた店舗であれば、顧客から「前と違う」「雰囲気が変わった」とネガティブな反応を受けることもあります。また、従業員にとっても、運営方針や労務条件が急に変わることで混乱が起きるリスクも。
このような“前オーナーの色”が強い店舗ほど、引き継ぎ後のブランディングやマネジメントに慎重な対応が求められます。
3:飲食店オーナーチェンジの流れとステップ【契約から引き渡しまで】
オーナーチェンジで店舗を取得するには、複数のステップを正しい順序で進める必要があります。
この章では、契約書の確認から店舗引き渡し・営業開始に至るまでの具体的な流れを、買い手目線でわかりやすく解説します。
3-1:事前準備|予算・業態・エリアの希望条件を整理する
まず最初に行うべきは、自分が目指す店舗の「理想像」を明確にすることです。
希望エリア、想定する業態(例:カフェ、焼肉、バーなど)、家賃・初期費用などの予算感を整理しておくことで、物件選びの軸がぶれません。また、ターゲット層や出店時期、希望坪数なども併せて整理しておくと、マッチング精度が高くなります。
事業計画が曖昧なままだと、良い店舗に出会っても即決できなかったり、取得後に想定外のリスクが発生することも。最初の段階で戦略を定めておくことが、成功の第一歩です。
3-2:情報収集・物件選定|信頼できる情報元を活用する
次に、希望条件に合うオーナーチェンジ物件を探します。
不動産ポータルサイトやM&Aプラットフォーム、専門の居抜き仲介業者など、複数のチャネルから情報を収集しましょう。中には水面下で出回る“非公開物件”もあるため、信頼できる業者とのネットワークを持つことも重要です。
ここで注意したいのが「情報の鮮度」と「営業中かどうか」。オーナーチェンジ物件はタイミング命。良物件はすぐに売れてしまうため、常にアンテナを張っておくことがポイントです。
3-3:店舗見学・条件確認|現地で見るべきチェックポイント
内見では、以下のような点を丁寧に確認しましょう:
✓ 店舗の衛生状態や設備の使用感
✓ 空調・水回り・電気・ガスなどインフラ状況
✓ 近隣競合店や周囲の人通り・客層
✓ 居抜きで残される備品・造作の一覧
✓ 想定売上と回転率(聞ける場合)
また、現オーナーがどういう理由で売却するのかも大切なヒントになります。退店理由が「赤字経営」なのか、「体力的な限界」なのかで、引き継いだ後のリスクの捉え方が大きく変わるからです。
3-4:条件交渉・意思決定|価格交渉や貸主の承諾取得
物件が気に入ったら、いよいよ価格や契約条件の交渉フェーズに入ります。
造作譲渡費や敷金・礼金の精算、営業許可証の状態などについて、業者や売主としっかり擦り合わせましょう。
可能であれば、「事業計画書」や「買主のプロフィール」などを用意して、貸主に信頼を持ってもらえるようにするのも効果的です。
3-5:契約締結・手続き|造作譲渡契約と賃貸借契約を結ぶ
交渉がまとまったら、正式に契約を結びます。
多くの場合、「造作譲渡契約」と「賃貸借契約」の2つを別個に締結することになります。造作譲渡では、譲渡対象となる設備や備品を明細で記載し、金額・支払条件・引渡し日などを明確にします。
賃貸借契約では自動継承されますので、内容を十分に精査し、不明点は必ず専門家や仲介業者に確認しましょう。
3-6:営業許可・保健所等の申請・変更
契約後、営業開始までに必要な行政手続きを済ませます。
基本的には、前オーナーの営業許可証を新オーナー名義に変更する「名義変更手続き」を保健所で行うことが一般的です。
そのほか、以下のような届出も確認しておきましょう:
✓ 消防署への防火管理者届出
✓ 水道・ガス・電気などの名義変更
✓ 音楽使用がある場合、JASRAC等の利用契約
3-7:引き渡し・営業開始|スタッフ引き継ぎとオペレーション構築
すべての手続きが終わったら、いよいよ引き渡しと営業開始です。
引渡し前には、造作・設備に不備がないかを再確認し、必要書類や鍵などの受け渡しを行います。同時に、従業員との顔合わせや、業務マニュアルの共有など、実務の引き継ぎ作業を丁寧に行いましょう。
また、営業開始後も「引き継ぎ期間」を2週間~1ヵ月ほど設け、前オーナーから直接運営ノウハウを学べるようにするのも理想的です。
4:取得前にチェックすべき重要ポイント【失敗しないための視点】

オーナーチェンジで飲食店を取得する際には、契約や設備だけでなく、見落としやすいポイントにも注意が必要です。
この章では、買い手が取得前に必ず確認すべきチェックリストをもとに、失敗やトラブルを防ぐための視点を解説します。
4-1:造作・設備の状態を事前に必ず確認する
設備や内装の引き継ぎは、オーナーチェンジや居抜き物件における最大のメリットであると同時に、トラブルの原因にもなりやすい部分です。以下のような観点で、実際に現地を見ながらチェックしましょう:
✓ 業務用冷蔵庫・ガスコンロ・食洗機などは正常に稼働するか
✓ 配管・排水・空調・換気などに不具合はないか
✓ 防水・防火・漏電対策など安全面の整備状況
✓ 修理・メンテナンス履歴の記録があるか
✓ 保証書や取扱説明書が残っているか
見た目だけでは分からない不具合も多いため、可能であれば専門業者と同行して設備診断を行うのが望ましいです。
4-2:賃貸契約の条件や制限事項を細かくチェック
賃貸借契約に関する確認は、オーナーチェンジの成否を左右する重要ポイントです。以下の点を必ず確認しましょう:
✓ 名義変更は可能か?(家主の承諾が必須)
✓ 家賃・更新料・敷金・償却金などの条件
✓ 解約予告期間や違約金の有無
✓ 用途制限(飲食業OKか?アルコール提供OKか?)
✓ 禁止行為や共益費の取り扱いなどの細則
これらの条件が明確にされていない場合、引き継いだ後に「実はこの業態では営業できない」といった問題が発覚することも。契約書はすべて読み込み、不安があれば専門家に相談しましょう。
4-3:従業員の雇用条件・継続可否を確認する
従業員の引き継ぎは非常にありがたい一方で、雇用条件や労働環境の確認を怠ると後にトラブルに発展する可能性があります。
✓ 雇用契約書の内容(時給・労働時間など)
✓ どの従業員が継続して勤務するのか(希望者のみなのか)
✓ 賞与・退職金・有休などの未消化分の扱い
✓ 新オーナーとの雇用契約書の再締結が必要かどうか
スタッフが定着している店舗であっても、引き継ぎ後に不安を感じて離職するケースもあります。新体制のビジョンをしっかり伝え、不安を払拭するコミュニケーションが大切です。
4-4:仕入れ・取引業者との契約関係を整理する
飲食店の運営では、食材や消耗品などの仕入れ先との関係も重要です。以下の内容を把握・精査しましょう:
✓ 継続中の契約書の有無(仕入価格・納品条件)
✓ 支払いサイト・掛け払いの有無
✓ 未払いの売掛・買掛金の精算状況
✓ 既存の契約を引き継ぐことが可能か
特に仕入先の条件が有利であれば、そのまま引き継ぐことで運営コストを抑えられる場合もあります。逆に不利な条件や古い慣習が残っているなら、契約の見直しや再交渉を視野に入れる必要があります。
4-5:営業許可・届出・法令順守状況を確認
店舗が適法に営業しているか、保健所や消防署などの各種届出が完了しているかも、必ず確認すべきポイントです。
✓ 営業許可証の有効期限や名義人
✓ 保健所への名義変更手続きの可否
✓ 消防法に基づく防火管理者選任届の提出有無
✓ アルコール・深夜営業に必要な許可の有無
引き継ぎ後に改めて許可が必要となるケースもあるため、事前に行政窓口で確認を取りましょう。法的な抜け漏れがあると、営業停止のリスクに直結します。
5:オーナーチェンジでトラブルを避けるための契約・交渉の注意点【売主・貸主との関係構築】
オーナーチェンジは「売主」「買主」「貸主(物件のオーナー)」が関わるため、契約条件や責任の所在を曖昧にしたまま進めてしまうと、後々トラブルにつながる可能性があります。
この章では、買い手側が特に注意すべき契約・交渉時のポイントを具体的に解説します。
5-1:造作譲渡契約書の内容を丁寧に確認・記録を残す
造作譲渡契約は、店舗の内装・厨房設備・什器などを売主から買主へ譲渡する契約です。以下のような点を明確に記載し、口約束ではなくすべて書面で残すことが重要です。
✓ 譲渡の対象物(設備一覧・写真付きリスト)
✓ 譲渡金額と支払い方法(手付金・残金)
✓ 引き渡し日と物品の状態
✓ 故障時の責任の所在
✓ 引き渡し後のトラブル対応(保証の有無など)
引き渡し後に「設備が壊れていた」「引き渡された数が違う」などのトラブルが起きることもあるため、可能な限り詳細な記載と、設備写真付きのチェックシートを交わしておくと安心です。
5-2:未払い金・保証金の精算条件を明確にする
店舗を引き継ぐ際には、売主側で未精算の支払いが残っていないか、必ずチェックが必要です。
✓ 売掛金・買掛金の精算は済んでいるか?
✓ 保証金や敷金はどう引き継ぐか?
✓ 光熱費・備品代・仕入れ代などの未払いがないか?
また、譲渡価格の中に「保証金の返還権利」や「敷金の引き継ぎ」が含まれている場合もあるため、金銭の取り扱いについては第三者(仲介業者や士業)を交えて明確にしておくと安心です。
5-3:現オーナーとの引き継ぎ期間・役割分担を取り決める
オーナーチェンジで営業を引き継ぐ場合、引き渡し直後からスムーズに営業を続けるためには、現オーナーからのオペレーション引き継ぎが重要です。
✓ マニュアルや仕入れ先リストの提供
✓ 数日間の立ち会いサポート
✓ 仕込みや仕入れのタイミングの共有
✓ 常連客への紹介や周知サポート
これらの引き継ぎ内容や期間を契約時に明記しておくことで、「聞いてない」「伝わってない」といったミスコミュニケーションを防ぐことができます。
5-4:第三者(専門家)に契約書をチェックしてもらう
買い手側が店舗取得に慣れていない場合、自力で契約書や権利関係をチェックするのは非常にリスクが高くなります。少しの見落としが、数十万円〜数百万円の損失につながることもあります。
以下のような専門家に、書類チェックや契約立会いを依頼することを検討しましょう:
・行政書士(契約書作成・名義変更手続き)
・税理士(譲渡価格や消費税の取扱い)
・飲食店に詳しい不動産会社(交渉・媒介)
報酬は数万円〜数十万円かかる場合がありますが、「安心して事業をスタートできる」価値は十分にあります。
6:成功するオーナーチェンジ物件の選び方【見るべきポイント】

同じように見える飲食店のオーナーチェンジ物件でも、成功するかどうかは「物件選び」が大きなポイントになります。
この章では、利益を出しやすく・長く経営できる店舗を選ぶためのチェックポイントを解説します。
6-1:立地と客層のマッチング|数字だけで判断しない
飲食店の立地を考えるとき、「人通りが多い=良立地」と思いがちですが、それだけでは十分ではありません。大切なのは、自分が想定している業態・価格帯・営業時間と、周囲の客層がマッチしているかどうかです。
たとえば:
高単価なフレンチ店 → オフィス街や住宅街の富裕層エリア
サク飲み居酒屋 → 駅近で人の流れがある繁華街
カフェ → 昼間の滞在ニーズが高い大学・公園近く
物件周辺の時間帯別の人の流れ、年齢層、近隣店舗の特徴などをリサーチし、「ここなら狙い通りの客が来る」と確信を持てる場所を選びましょう。
6-2:現オーナーの退店理由を必ず確認する
オーナーチェンジ物件では、なぜこの店舗が手放されるのかを必ず確認してください。理由によっては、買った後に同じ失敗を繰り返すリスクがあります。
✕ 赤字続きで撤退 → 業態・価格設定に無理があった?
✕ トラブルが多かった → 家主や近隣との関係に注意
○ 家庭の事情・体力的限界 → 店舗自体に問題なしの可能性大
売主に直接聞きづらい場合は、仲介業者にヒアリングしてもらうか、周囲のテナント・近隣住民の情報も参考にしましょう。
6-3:居抜き設備の状態とメンテ履歴を確認する
内装や厨房設備が残っているオーナーチェンジ物件では、それらの状態によって、追加の初期投資が大きく変わります。
確認すべきポイント:
✓ 業務用冷蔵庫・製氷機などの耐用年数と状態
✓ 配管や換気ダクトの異臭・不具合の有無
✓ 電気容量やガス圧が希望業態に対応しているか
✓ 消防・保健所基準を満たしているか
✓ メンテナンス履歴や修繕記録があるか
あとから「エアコンが壊れていた」「換気が不十分だった」などの問題が出て、予定外の費用が発生するケースも少なくありません。現地チェック+プロによる設備診断も検討しましょう。
6-4:ライバル店と差別化できるかを判断する
周囲に同業種の店舗が複数ある場合、その立地で新たに参入しても「埋もれる」可能性があります。成功するためには、以下のような差別化ポイントがあるかを見極めましょう:
✓ 立地は同じでも、ターゲット層が異なる(例:若者 vs ファミリー)
✓ メニューや価格帯、コンセプトで独自性を出せる
✓ 空間設計や導線が競合より優れている
✓ SNS映え・話題性・予約のしやすさなどに強みがある
すでに競争の激しいエリアでは「ただ引き継ぐだけ」では太刀打ちできません。事前にリサーチを行い、自分ならどう戦うかの戦略を持って取得に臨むことが重要です。
6-5:営業実績と固定費バランスから利益が見込めるか分析
営業中の店舗を取得する場合、その店舗がどの程度利益を出していたかも大きな判断材料になります。売主が開示してくれるケースでは、以下の数値を確認しましょう:
✓ 月間売上(時間帯別・曜日別)
✓ 客単価・回転率・稼働率
✓ 原価率・人件費率・光熱費の内訳
✓ 家賃・共益費・広告費などの固定費
理想は、売上に対して家賃が10%以下、人件費・原価合わせて60%以内で収まっていること。これ以上にコスト比率が高いと、利益が出しづらい傾向があります。
数字が不明な場合でも、自分で簡易的にシミュレーションを行い、無理のない収支が組めるか検証しましょう。
7:取得後にやるべきこと・営業開始後の注意点【スタートダッシュを切るために】
オーナーチェンジによる店舗取得は「取得して終わり」ではありません。
新オーナーとしての第一歩を成功させるためには、営業開始直後の対応が非常に重要です。
この章では、買い手が取得後に取り組むべき実務と、リスクを避けるための注意点を解説します。
7-1:保健所・消防署・税務署などへの各種届出を忘れずに
営業を正式にスタートするには、各種行政手続きが必要です。旧オーナーの許可証をそのまま使い続けることは基本的にできません。
主な必要手続き:
保健所:営業許可証の名義変更 or 再取得(都道府県ごとに異なる)
消防署:「防火管理者選任(解任)届出書」の提出(一定規模以上の飲食店)
税務署:個人事業の開業届 or 法人設立届出書、青色申告の申請など
年金事務所:従業員を雇用する場合、社会保険の加入手続き
労働基準監督署・ハローワーク:労災・雇用保険の手続き
これらを怠ると、最悪の場合「営業停止」や「罰金」の対象になります。地域の商工会や士業に相談しながら、早めの着手と漏れのない提出を心がけましょう。
7-2:メニューや価格設定の見直し(ターゲットに最適化)
前オーナーのメニューをそのまま引き継ぐ場合でも、立地や客層に合った内容・価格になっているかを見直すことで、売上アップにつながります。
見直しの視点:
✓ 原価率や提供スピードに見合った価格か
✓ 注文率の低いメニューは整理できないか
✓ 看板メニューや名物料理が打ち出せているか
✓ セットメニューやランチ帯の導線を強化できるか
✓ デジタルメニュー化・写真付きメニューの導入も検討
無理な価格変更やリニューアルはリスクもあるため、徐々に変えてテストしながら改善するのが理想です。
7-3:従業員との信頼関係構築が最優先
スタッフが継続勤務する場合、新オーナーとしての信頼構築が最優先課題です。
スタッフの不安を放置すると、離職やサービス品質の低下につながります。
具体的な対応:
・面談や全体ミーティングを実施し、今後の方針や考え方を共有
・雇用条件や業務内容に変更がある場合は早めに説明し、同意を得る
・モチベーションを高めるための評価制度や報酬改善も検討
・「現場の声」をしっかり吸い上げ、改善アクションを早めに取る
店舗運営の根幹を支えるのはスタッフです。丁寧な関係構築が、営業の安定化とファンづくりにつながります。
7-4:常連客・地域顧客への周知と信頼づくり
オーナーチェンジ後に最も気をつけたいのが「常連客の離脱」です。突然オーナーが変わり、接客スタイルや味も変化すると、常連が離れてしまうリスクがあります。
おすすめのアプローチ:
・チラシやPOP、SNSで「新体制のお知らせ」を発信
・オープン記念キャンペーンや挨拶イベントの実施
・常連客に対しては直接の声がけやDMを活用し、継続来店を促す
・味やサービスが大きく変わる場合は、「進化」として伝える
「変わってよかった」と思ってもらえるかどうかがリピートの鍵になります。丁寧な情報共有と、期待に応える営業を心がけましょう。
7-5:開業直後のキャッシュフローと在庫管理に注意
営業開始直後は、仕入れや備品購入などで出費がかさみがちです。一方で、売上は安定しないことも多いため、キャッシュフローの管理が非常に重要です。
・月初で多額の支払いが集中しないよう分散する
・クレジットカード導入でキャッシュの流出を後ろ倒しにする
・開業直後の仕入れは必要最低限にとどめ、回転を見ながら補充する
・仕入れ先と支払いサイトを交渉(締め支払い条件の見直し)
特に初月〜3ヶ月目は「黒字でも資金ショート」のリスクがあるため、現金残高を重視した運営を心がけましょう。
7-6:オーナーとしての理念・ビジョンを明確に伝える
店舗を通じて何を実現したいのか、自分はどんな店をつくりたいのか──
オーナーチェンジの節目は、理念やビジョンを内外に伝えるチャンスです。
・スタッフに対しては「一緒に店をつくる仲間」として共有
・お客様には「この店が大切にしていること」をSNSや張り紙などで伝える
・業態やメニュー、サービスに一貫性が生まれ、店の印象が明確になる
理念や軸がないと、ぶれた判断・空気の悪化につながりやすくなります。
「どんな飲食店にしたいか」を言語化し、経営判断の軸にしていきましょう。
飲食店のオーナーチェンジをする際には、事前にしっかりとした準備と情報収集が欠かせません。
この記事で紹介したように、オーナーチェンジには多くのメリットがある一方で、設備の状態や契約条件などのデメリットにも注意が必要です。
まずは、自分の希望条件を明確にし、信頼できる情報源や専門家の力を借りながら物件選びを進めましょう。さらに、契約手続きや営業許可の申請を慎重に行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
これからオーナーチェンジを考えている方は、まずチェックリストを作成し、各ステップを確実に進めることが成功のカギです。
そして、取得後はスタッフや顧客との良好な関係構築を意識し、新しい経営方針をしっかりと打ち出していきましょう。
この記事があなたの飲食店取得の成功に役立つことを願っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。