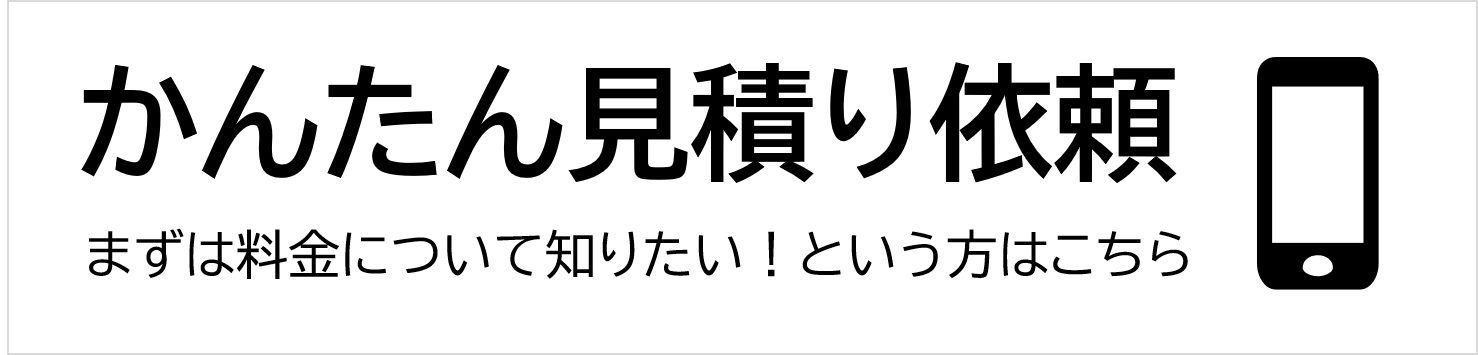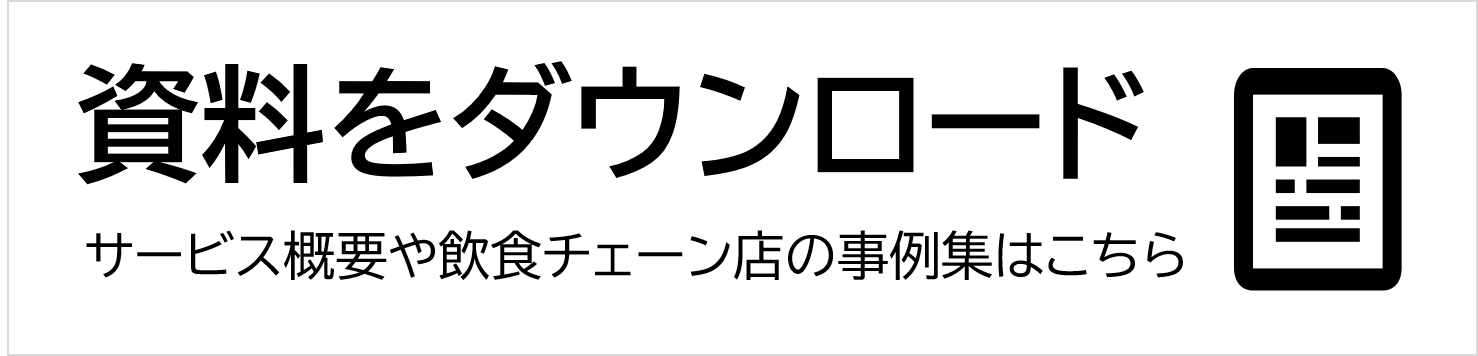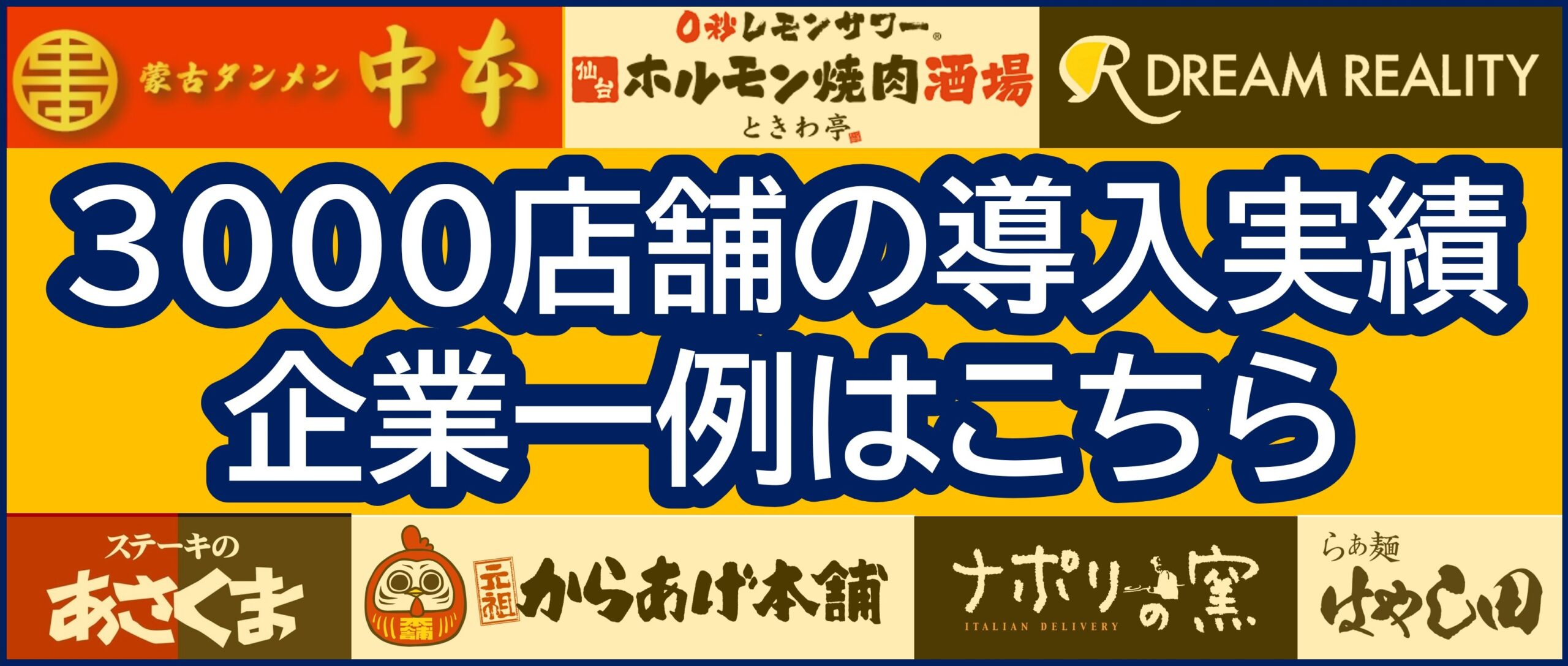飲食店で儲かるジャンルとは?
2026年の最新トレンドを、3000店支援の専門企業が徹底解説
飲食店を経営する皆さん、「儲かるジャンル」を見つけることは、ビジネスの成功に不可欠です。しかし、どのジャンルを選べばリスクを避け、安定した収益を得られるのでしょうか?
近年の最新トレンドを踏まえ、3000店以上を販促支援してきた専門企業である私たちが、飲食店で儲かるジャンルを徹底解説します。
競争が激化する中で、儲かるジャンルの正しい選択をすることは難しいものです。
この記事を読むことで、あなたの飲食店が成功への一歩を踏み出すためのヒントを得ることができるでしょう。
どのような点に注目して儲かるジャンルを選定すべきか、どのように差別化を図れば良いのか、具体的な戦略を知ることで、繁盛する飲食店の経営を実現するための第一歩を踏み出しましょう。
目次
1:飲食店で「儲かるジャンル」とは?市場動向と成功の条件

1-1:外食業界の回復と成長トレンド(2024〜2025年)
飲食店を開業しようと考えている方や、新たな業態での事業拡大を目指す経営者にとって、「今、外食業界は儲かるのか?」という市場の動向は最も気になるポイントのひとつです。
2024年〜2025年にかけて、外食産業は回復基調にあります。経済産業省の商業動態統計や日本フードサービス協会(JFS)のデータを見ると、コロナ禍で大きな打撃を受けた外食市場は、すでに多くの業態でコロナ前の売上水準を超えつつあります。
とくに、ファストフード、居酒屋、ラーメン、焼肉といった業態が復活を牽引しています。これらの業態は「気軽に楽しめる」「短時間で満足できる」「グループ利用が可能」といった特徴を持っており、コロナ後に高まった“日常の外食回帰”や“会食ニーズの復活”といった社会的背景と見事にマッチしています。
このような回復の波に乗ることで、新たに出店した店舗が初月から黒字化する事例も珍しくありません。つまり、2025年の今は「飲食店開業にとって追い風のタイミング」だったといえます。
1-2:飲食店儲かるジャンルの3大共通点とは?
では、同じように出店しても儲かる店とそうでない店があるのはなぜでしょうか?
実際に儲かっている飲食店には、以下の3つの共通点があります。
1つ目は「高い回転率」または「高い客単価」に強みを持っていること。たとえばラーメン店や立ち食いそばなどは1時間に多くの客を回せる高回転型。対して焼肉店や高級居酒屋は1組あたりの売上が高い高単価型です。どちらかに軸を持たず「中途半端な回転率・単価」の業態は、利益が出づらくなります。
2つ目は「原価率・人件費・家賃などの固定費のバランスが最適化されている」こと。食材の仕入れ価格だけでなく、ワンオペ・省人化などで人件費を抑えられる業態設計ができているかがカギになります。家賃に見合った売上構造になっているかの検討も重要です。
3つ目は「立地・業態・ターゲットが一致していて、“選ばれる理由”が明確になっている」こと。たとえばオフィス街で営業するラーメン店なら、ランチタイムの早さとボリュームが必須。逆に住宅街のカフェであれば、滞在時間の長さとくつろげる空間が求められます。自店舗の“業態コンセプト”と“立地特性”がズレていないことが、儲かる店の最低条件です。
1-3:専門企業が見る「飲食店の儲かるジャンル」の特徴
私たちは会員証アプリ「レストランスター」を通じて、これまで3000店舗以上の飲食店の販促支援に携わってきましたが、その中で成功している店舗にはいくつかの共通した特徴が見えてきます。
まず一つ目は「明確なターゲット設定」がされていることです。たとえば“30代女性が仕事帰りに立ち寄れる健康志向の居酒屋”など、誰のための店かがはっきりしているほど、集客も販促もブレなくなります。
二つ目は「継続的な改善」ができる体制を持っていること。メニュー改定、接客改善、販促の見直しなど、日々のPDCAを怠らない店ほど、競争が激しいエリアでも勝ち残っています。
そして三つ目が「再来店を生む仕組み」を作れていること。たとえばLINE登録やアプリ導入、誕生日特典などを活用して、1回来たお客様を次回につなげる仕組みを作れているかどうかが、長期的な収益の差になります。
目先の利益を追いすぎず、地に足をつけた設計と運営で「長く続く飲食店経営」を目指す店舗こそが、結果的に“儲かるジャンル”を体現しているといえるでしょう。
2:【2026年版】飲食店の儲かるジャンル|ベスト10

2-1:儲かるジャンルを選定する根拠と評価ポイント
飲食店の開業や事業拡大を検討する際、「どのジャンルを選ぶか」は成否を分ける最大の要素です。本記事では、2025年の市場動向をふまえて「儲かる飲食店ジャンルベスト10」を選定しました。
評価の基準としたのは、「開業件数」「原価率」「客単価」「回転率」「再来店性」の5つの要素です。単に人気があるかどうかではなく、実際に収益構造が優れており、運営面での再現性があるかどうかも加味しています。
加えて、近年では「SNS映え」「話題性」「テイクアウト対応力」なども重要な指標となっており、これらを加点要素として最終的なベストジャンルを選出しています。運営の難易度や立地の適性など、実務面での成功率も踏まえた「実用的なベストジャンル」としてご活用ください。
2-2:儲かるジャンルの飲食店ベスト10
2-2-1:居酒屋
居酒屋は、ターゲットに応じて価格帯や内装、提供スタイルを柔軟に変えやすいのが最大の強みです。カジュアルな立ち飲みから高級和風居酒屋まで、幅広い選択肢があるため、立地や客層に合わせた設計がしやすくなっています。
仕事帰りのサラリーマン、週末の飲み会、団体利用など多様なニーズを拾えるのも魅力で、回転率と客単価のバランスが良い「バランス型の勝ちパターン」と言えるでしょう。特に駅近や繁華街といった立地との相性が良く、安定した収益モデルを築きやすい業態です。
2-2-2:焼肉店
焼肉店は、グループ利用や特別な会食との親和性が高く、「来店の理由」が自然と生まれやすい業態です。誕生日や記念日、接待など、特別感を求める利用シーンが多いため、高単価のメニューでも受け入れられやすい点が強みです。
食材原価は高めですが、部位ごとに価格差をつけて販売でき、また食材ロスも少ないため、利益率の調整がしやすいという特徴もあります。内装やサービスで高級感を演出することで、単価の底上げも可能です。
2-2-3:ラーメン屋
開業資金が比較的少なく、原価率も抑えられるラーメン屋は、個人経営者にとって人気の高い業態です。客単価は低めでも、昼夜問わず安定した集客が見込めるため、高い回転率でカバーできます。
スープやトッピングで差別化を図る余地が大きく、SNS映えや限定メニューで話題を作る施策も打ちやすいのが特徴。1人客が多いため、少人数オペレーションで運営できるのも経営面でのメリットです。
2-2-4:カフェ
カフェは女性客や若年層を中心に安定した需要があり、店舗空間そのものに価値を持たせやすい業態です。SNSでの拡散効果が高く、「映える内装」や「季節感あるメニュー」がそのまま集客力につながります。
小規模なスペースでも成立し、居抜き物件や少人数スタッフでの開業が可能な点も新規参入にとって有利です。ドリンクやスイーツの原価率も抑えやすく、粗利の取りやすい構造になっています。
2-2-5:ファストフード
スピード提供と価格訴求を武器に、回転率を極限まで高めることで収益を確保できるのがファストフード業態です。店内飲食だけでなく、テイクアウトやデリバリーとの親和性が非常に高く、多様なニーズに対応できます。
最近では注文のセルフ化・厨房の機械化が進み、少人数運営で高い利益率を出せる仕組みも整いつつあります。効率と回転を極めた業態である一方、ブランドづくりや商品開発に力を入れれば、他店との差別化も可能です。
2-2-6:お弁当・惣菜専門店
コロナ禍以降、テイクアウト需要の高まりとともに再注目されているのが、お弁当・惣菜専門店です。イートインスペースが不要なため初期費用を抑えやすく、厨房機能に集中した店舗設計が可能です。
商品はあらかじめ作り置きができるため、人件費の最小化も図れます。住宅街やオフィス街、駅前といった立地との相性も良く、「毎日の食事ニーズ」に応えることで安定的な売上が見込めます。
2-2-7:スイーツ専門店
SNSや口コミによる拡散を狙いやすく、流行を敏感に取り入れることで話題化しやすいのがスイーツ専門店の魅力です。1商品あたりの価格は安くても、高粗利・高回転で十分な利益が出せるビジネスモデルを構築できます。
限定メニューやコラボ企画との相性も良く、マーケティング次第で短期間での売上爆発も見込めます。トレンドの移り変わりが激しいため、柔軟なメニュー開発力が問われるジャンルでもあります。
2-2-8:バー
バーは夜間営業に特化しており、他業態とのバッティングが少ない点が特徴です。比較的少ない初期投資で開業でき、カウンター中心の店づくりなら1人〜2人でも運営が可能です。
ドリンクの原価率は低く、高粗利を確保しやすいため、顧客単価が低くても一定の利益が見込めます。世界観や音楽、内装などにこだわることで「居心地の良さ」がリピートにつながる業態です。
2-2-9:定食屋・町中華
日常的に利用される“生活密着型”業態で、地域住民や職場近隣の常連客に支えられる堅実なビジネスモデルが築けます。ランチタイムとディナータイムで異なるメニュー設計をしやすく、客層を広げる工夫も可能です。
原価や回転率のバランスを取りやすく、効率よく利益を確保できます。特別な演出やマーケティングよりも「いつもの味」「安心できる接客」が最も求められる業態です。
2-2-10:天ぷら・鰻など和食専門業態
高級感のある和食業態は、単価が高くても一定の需要があるのが特徴です。接待や記念日など特別な日を過ごすために選ばれやすく、“来店理由”が明確である点も集客において有利です。
職人技が求められるジャンルですが、それゆえに差別化が可能で、老舗化しやすい傾向もあります。短期で大きく儲けるというより、長期にわたり安定した経営を目指す方に適したジャンルです。
3:儲かるジャンルの成功例と共通点
3-1:儲かるジャンルの飲食店の成功パターン
実際に黒字化を達成している飲食店には、いくつかの共通した成功パターンが存在します。特に開業から3年以内に軌道に乗った店舗の多くに見られるのが、「ターゲットの明確化」「立地との一致」「強みの一点突破」の3つが噛み合っている点です。
たとえば、「コスパ重視のボリューム定食」「スープにとことんこだわったラーメン店」「内装と空間に全振りした雰囲気重視のカフェ」など、自店の“強み”を明確に打ち出し、それを軸に店舗全体を設計しているケースが多く見られます。
必ずしも低価格が求められているわけではなく、客単価が高くても「この店でなければ」と思わせるだけの明確な価値が伝われば、しっかりリピーターを獲得できるのが今の飲食市場の特徴です。
3-2:立地・メニュー・接客が噛み合った儲かるジャンルの飲食店成功例
「どこで・何を・どんなふうに提供するか」の整合性が取れている店舗は、成功の確率が高まります。実際、学生街でボリューム満点のラーメン店を展開したり、繁華街に立ち飲み特化の居酒屋を出店したり、住宅街で手づくり惣菜に特化したテイクアウト店を営むなど、それぞれの立地ニーズと業態が見事にフィットした事例は数多く存在します。
また、「名物メニュー」がある店はSNSや口コミでの拡散効果が高く、自然と集客の導線ができていく傾向にあります。加えて、丁寧な接客や居心地の良い空間演出は、「また来たい」と思わせる要因としてリピート率に大きな影響を与えています。
つまり、単に美味しい・安いだけではなく、「この場所で、こういう人たちに、こういう体験をしてもらいたい」という全体設計がハマった店ほど、安定した売上を確保しやすいのです。
3-3:ターゲット明確化とストーリー設計が鍵
成功している店舗に共通する最大の要素は、「誰に、何を、なぜ提供するのか」というメッセージが一貫していることです。これにより、打ち出すコンセプトがブレず、店舗のすべてが明確な軸でつながるため、顧客にとっても分かりやすく、記憶に残りやすくなります。
さらに、SNSや口コミで語られる“ストーリー”がある店舗は、ファンの獲得スピードが早く、ブランドとしての認知拡大も加速します。「創業者の想い」「地元の食材へのこだわり」「生まれた経緯や背景」などが物語として語られることで、価格競争に巻き込まれにくい“選ばれる理由”が生まれるのです。
立地や商品力に頼るだけでなく、その背景にある「意味や価値」を可視化することで、共感と信頼を呼び、競合との差別化を図ることができます。
4:儲からない・失敗しやすい飲食店ジャンルとは?その理由を解説

飲食業界には、どれだけ努力しても構造的に利益を出しにくいジャンルや、集客・運営の難易度が高いために失敗が多い業態も存在します。ここでは、実際に苦戦を強いられているジャンルと、その背景にある課題を解説します。
4-1:高級創作系のリスク:原価率と固定客不足
高級志向の創作料理店は、一見すると単価が高く利益が出やすそうに見えますが、実際にはその逆です。料理の素材には高級食材を使用し、人件費もスキルの高いシェフを確保する必要があり、さらに内装や雰囲気づくりに多額の設備投資が必要となるため、原価率・人件費・家賃の三重苦に陥りがちです。
加えて、こうした業態はリピーターの獲得が不可欠ですが、最初の集客のハードルが高く、口コミやSNSでの拡散にも時間がかかる傾向があります。予約制やコース料理中心の営業スタイルでは「一見さん」を取り込みにくく、一定数の固定客を獲得するまでは赤字が続くというリスクもあります。
特に、広告やメディア露出による認知拡大が追いつかないまま閉店に追い込まれるケースも珍しくありません。
4-2:パン屋や洋食レストランが苦戦する背景
一見、地域に根付いた店として理想的に思える「パン屋」や「街の洋食屋」ですが、実際には継続経営が非常に難しいジャンルです。まず、商品が日持ちしないという特性があるため、毎日の販売予測が非常に重要で、廃棄リスクが常につきまといます。
また、パンや洋食は使用する食材の種類が多く、原価管理が難しいうえに、オペレーションも複雑化しやすい点が課題です。仕込みの手間も大きく、個人店では人手不足になりがちです。
さらに、「そこそこ美味しい」では埋もれやすく、価格帯のわりに“選ばれる理由”を作りづらいジャンルでもあります。中途半端なブランド設計や差別化の欠如は致命的で、安定的な売上を確保できずに閉店となる例も少なくありません。
4-3:立地・価格・業態のミスマッチがもたらす失敗
飲食店経営で最も多い失敗パターンの一つが、「立地と業態・価格帯のミスマッチ」です。たとえば、高価格帯のレストランを庶民的な下町に出店したケースや、ランチ営業に注力した業態を夜間人口が多いエリアに出したケースなど、ターゲットと実際の商圏がかみ合っていないことが原因で集客に苦しむ店舗は非常に多く存在します。
また、初期費用を抑えるために好立地ではない物件を選び、結果的に集客力を大きく損なう例もあります。立地よりも業態を優先し、物件選定を後回しにした場合は、そもそも顧客が来ないという事態になりかねません。
さらに、想定していたよりも家賃が売上に対して重すぎて、利益がまったく残らずに閉店を余儀なくされるパターンも後を絶ちません。業態設計・価格設定・立地分析を一体で考えることの重要性がよく分かる典型的な失敗事例といえます。
5:儲かるジャンル選びで重要な4つのチェックポイント
飲食店の開業や新業態への挑戦は、ジャンル選びがすべてと言っても過言ではありません。儲かる可能性のあるジャンルでも、自身の状況や地域の特性に合っていなければ、失敗につながるリスクは高まります。ここでは、失敗を避けるために事前に確認すべき4つのポイントを紹介します。
5-1:自分のスキル・経験を活かせるか?
飲食店の運営には「調理スキル」「接客対応」「経営感覚」のすべてが求められますが、その中でも自分がどこに強みを持っているかを明確にしておくことが重要です。
たとえば、調理経験が豊富な人なら味で勝負できる業態(ラーメン・定食・専門店など)、接客が得意なら雰囲気やホスピタリティが強みになるカフェやバーが適しています。一方で、経営経験が浅い場合は、複雑なオペレーションが必要な業態を避け、シンプルなメニューと少人数体制でも回せる仕組みを選ぶと失敗しにくくなります。
5-2:商圏・地域ニーズとの整合性は?
どんなに良い業態でも、その地域のニーズと合っていなければ集客は望めません。開業予定地が住宅街なのか、オフィス街なのか、学生街なのかによって、来店時間帯や価格帯、人気メニューの傾向が大きく変わります。
さらに、地域の年齢層や文化的背景、食習慣も重要です。たとえば高齢者が多いエリアではヘルシーで柔らかいメニューが好まれる傾向にあり、若年層中心のエリアではSNS映えやトレンド感のある商品が人気になります。
また、すでに競合店が多い場合は、自店がどこで差別化できるか、あるいは他店と棲み分けができるかも含めて、立地と業態の相性を冷静に見極める必要があります。
5-3:差別化できるコンセプトはあるか?
同じような業態が並ぶ中で「選ばれる店」になるためには、他店とは違う明確なコンセプトが欠かせません。
自店の強みを一言で説明できるか?メニューなのか、空間なのか、接客なのか、どこで勝負するのかを最初に決めておくことで、開業後のブレを防ぎ、マーケティング戦略にも一貫性が出ます。
競合店をリサーチする中で、「この立地でまだ誰もやっていない業態」や「ニーズはあるのに供給が少ないジャンル」を見つけることができれば、空白のポジションを狙う形で優位に立つことも可能です。
5-4:無理なく運営できるオペレーションか?
繁盛しても回らない店では意味がありません。人手不足が常態化する飲食業界においては、少人数でも回せる運営設計がますます重要です。
仕込み・調理・提供の流れが特定のスタッフに依存している場合、その人が抜けるだけで営業が成り立たなくなるリスクがあります。また、長時間営業や細かい工程の多いメニュー構成は、体力的にも精神的にも消耗が激しく、長続きしにくい傾向があります。
開業前に、「もしスタッフが減っても運営できるか」「仕組みで再現性のある営業ができるか」といったオペレーションの柔軟性と持続性を検証しておくことが成功の鍵となります。
6:儲かるジャンルの飲食店に共通する3つの戦略とは?

「どのジャンルを選ぶか」も重要ですが、実際に儲かる飲食店にはジャンルを問わず共通する経営戦略があります。業態や立地に差があっても、安定して黒字を維持し続けている店舗には、以下の3つの戦略がしっかりと組み込まれています。これから開業する人はもちろん、既存店の立て直しを考えている方も、ぜひ見直しておきたいポイントです。
6-1:コスト管理力(原価・人件費・在庫)
飲食店経営で最も重要なのが、**「売上 − コスト = 利益」**という基本構造の中で、いかに無駄を省いて利益を確保するかです。特に注視すべきは、**原価・人件費・家賃(FLR比率)**のバランス。この3項目が売上の70%を超えている店舗は、いくら売れても赤字になりやすくなります。
利益率を高めるためには、食材仕入れの見直しや、在庫ロスの削減が有効です。また、人件費についても、少人数で効率的に回せるオペレーションの構築や、ピークタイム以外の人員配置最適化など、固定費全体を見直す意識が必要です。
6-2:集客と再来店率を高める仕組み
売上の安定には**「新規集客×リピート率」**の両立が欠かせません。特に今の時代は、一度来店した顧客をいかに“常連化”できるかが勝負所です。
自社アプリやSNS(InstagramやXなど)を使って来店後もつながりを保ち、誕生日クーポンやポイント制度、クーポンガチャなどの仕掛けで再来店を促す仕組みを持っている店舗は非常に強い傾向があります。
また、商品や接客を通じて**「また来たくなる体験」=感動体験**を提供することが、口コミや紹介といった無料の宣伝につながるため、広告に頼らず自然と集客ができる好循環が生まれます。
6-3:ターゲット分析×改善ループの導入
儲かっている店ほど、**「お客様の声に耳を傾け、改善をやめない」**という姿勢を持っています。POSレジデータやアンケート結果から、来店時間帯、人気メニュー、客層などを数値で把握し、ターゲットが求めているものを定期的に再確認しています。
たとえば、若年層の比率が上がればSNS映えメニューを強化したり、客単価が落ちていればセットメニューや回数券で対策するなど、状況に応じて柔軟に戦略を調整できる店ほど強いのです。
このように、「試す→測る→改善する」のPDCA(改善ループ)を定期的にまわし、時代や地域の変化に対応できる力が、長く儲かり続ける飲食店の必須条件といえるでしょう。
この「3つの戦略」は、単なる流行や業態選びとは別次元の、“経営力そのもの”を高める基本原則です。ジャンル選びと同時に、こうした戦略の土台も意識することで、より確実な成功につなげることができます。
7:飲食店開業の流れと準備【初心者向け】
「飲食店を始めたいけど、何から手を付けていいかわからない」――そんな方に向けて、ここでは開業までの全体像と準備ポイントをわかりやすく解説します。初めての人ほど、計画的にステップを踏むことが成功への近道。自己資金の準備だけでなく、物件選びや許可取得など、“知らないとつまずく”落とし穴も要チェックです。
7-1:飲食店開業までのステップ(7段階)
飲食店開業は思いつきでは進められません。以下の7ステップを順番にこなすことで、リスクを抑えたスタートが切れます。
①コンセプト決定
どんなお店を誰向けにやるのか?立地やターゲットと合ったコンセプトが重要です。
②物件探し
商圏分析を行い、自店のターゲットとニーズが合致するエリアを選定。家賃と売上見込みのバランスも見極めましょう。
③事業計画書作成
開業資金・売上予測・運営計画などをまとめます。融資や補助金申請の際にも必須。
④資金調達
自己資金だけでなく、日本政策金融公庫などからの融資や補助金制度の活用を検討。
⑤各種許可の取得
飲食店営業許可・防火管理者選任・食品衛生責任者資格など、法的な手続きを忘れずに。
⑥内装・仕入・採用
業態と客層に合った内装設計、必要な厨房機器や備品、スタッフの募集・教育を進めます。
⑦プレオープン&改善
オープン前に友人・知人向けにテスト営業を行い、オペレーションやメニューを最終調整します。
7-2:開業資金の目安と調達手段
飲食店の開業費用は、業態や規模によって大きく異なりますが、おおよその目安は以下の通りです。
カフェ:500万円~
居酒屋:800〜1,500万円
ラーメン店:1,000万円~
これに加えて、最低3ヶ月分の運転資金(家賃・人件費・食材費など)も準備が必要です。
資金調達には以下の手段があります:
自己資金:余裕があればリスクが少なく安定
融資:日本政策金融公庫の新規開業融資は審査基準が比較的ゆるやか
補助金・助成金:開業支援制度を活用
クラウドファンディング:店舗コンセプトに共感する支援者を集められれば宣伝効果も
7-3:居抜き物件のメリットと注意点
初期費用を抑える手段として人気なのが**「居抜き物件」**です。以前に飲食店だった物件を活用することで、厨房設備や内装がそのまま使えるため、数百万円単位で初期費用を節約できるケースもあります。
ただし以下の注意点もあります:
設備の状態チェック:老朽化している場合は修繕費がかさむ
契約条件の確認:譲渡金や造作譲渡料の内容を明確にしておく
レイアウトが合わない可能性:業態や動線が自店に合わない場合もあるため、設計の見直しが必要になることも
特に初めての開業では、専門家(不動産業者・内装業者・行政書士など)に相談することがリスク回避の鍵となります。
8:まとめ|儲かるジャンル選定×改善力で、長く続く飲食店をつくろう
飲食店で「儲かるジャンルは何か?」と考えることは、たしかに開業において重要な出発点です。しかし、実際の“ジャンル選び”そのものではなく、選んだ業態をどう磨き、どう育てていくかという継続的な改善と運営の工夫にあります。ここでは本記事のポイントを振り返りつつ、「長く儲かる店」をつくるための最終的な考え方を整理しておきましょう。
8-1:儲かるジャンルの“型”に頼りすぎない
よく「今はラーメンが儲かる」「カフェブームが来ている」といったトレンドに惹かれて業態を決めるケースがあります。たしかに、ジャンルごとの市場性や流行を無視はできませんが、それはあくまで“入口”にすぎないということを忘れてはいけません。
どんな業態であっても、立地、価格帯、コンセプト、オペレーションが噛み合えば、十分に勝ち筋はあります。逆に、流行りのジャンルであっても、それらが不一致だと短命で終わる可能性は高いのです。つまり、「何をやるか」よりも「どうやるか」が成否を分けます。
8-2:継続改善×顧客理解が飲食店の成功を支える
開業時はどんな店でも近隣住民に注目されやすく、ある程度の集客ができてしまうものです。しかし、そこで満足せずに**「次の来店をどうつくるか」「どうリピートにつなげるか」**という発想ができるかが重要です。
成功している店舗ほど、顧客の声を聞き、売上データを分析しながら、継続的な改善を繰り返しています。例えば、再来店の特典を設けたり、アンケートでニーズを探ったり、SNSやアプリで顧客との接点を強化したりといった施策が、日々実行されています。
改善のPDCAを自然に回せる業態・オペレーション設計をしておくことで、「売れ続ける店」に進化しやすくなります。
8-3:3000店舗支援の現場から見えた最終結論
私たちがこれまで会員証アプリを通じて販促を支援してきた3000店舗以上の飲食店を振り返ると、儲かっている店にはジャンルを問わず**いくつかの“共通する習慣”**があることが分かってきました。
それはたとえば、
・売上の波を放置せず、定期的に販促を実行している
・感覚に頼らず、数字やアンケート結果を見て改善している
・現場のスタッフと密に連携し、サービス品質を保ち続けている
といった地道な取り組みの積み重ねです。どれも派手な手法ではありませんが、**一時的なブームや偶然に頼らず、長く安定して利益を出すための“土台”**となっています。
「一発当てる」ではなく、「続けて勝つ」。これが、儲かる飲食店の本質であり、持続可能な経営のゴールでもあります。
以上が「儲かる飲食店ジャンル」を考えるうえで知っておくべきポイントと、そこから導かれる成功の法則です。ジャンル選びに悩んでいる方は、ぜひ本記事を何度も読み返しながら、「自分ならどの業態を、どう磨いていけるか」を具体的にイメージしてみてください。持続する力こそが、あなたの飲食店を“儲かる店”へと導いてくれるはずです。
それではこの記事は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。