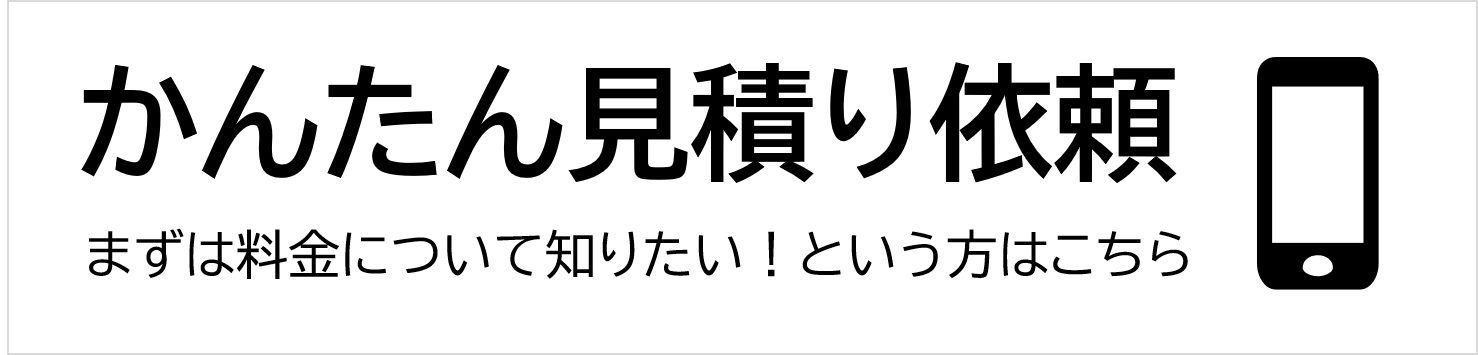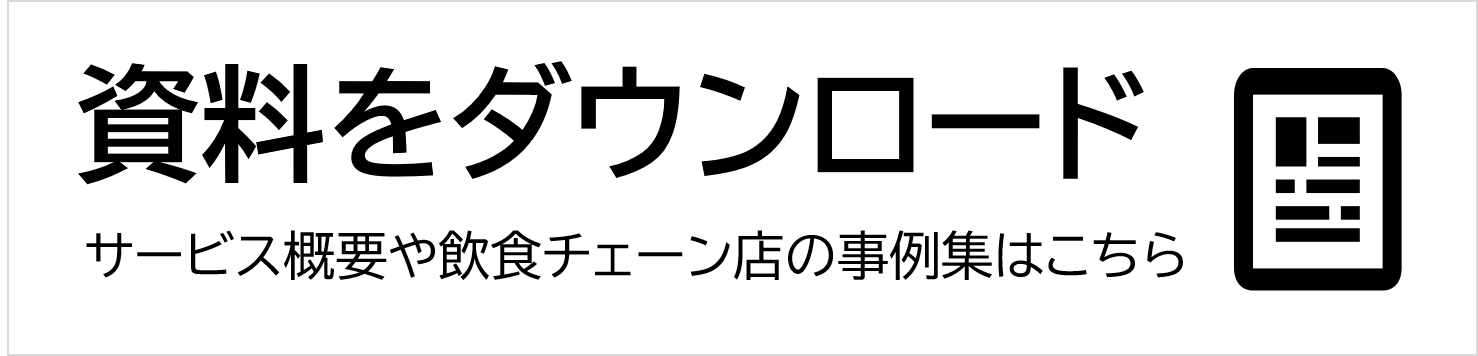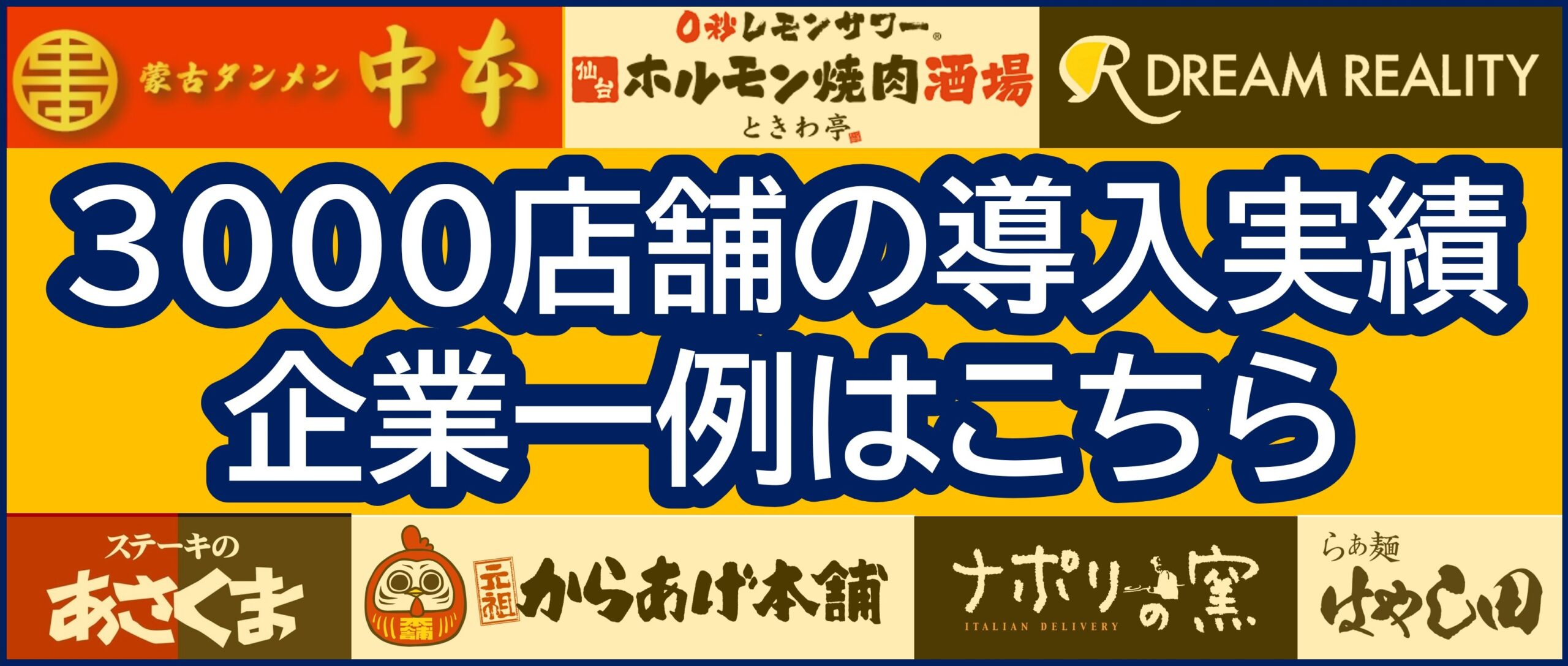飲食店の店長育成マニュアル|優秀な店長を育てる仕組みと具体的ステップ
飲食店の成功は、優秀な店長の存在に大きく依存しています。
しかし、店長育成の重要性を理解しつつも、具体的な育成方法が分からず悩んでいませんか?
人材不足が叫ばれる中、効果的な店長育成は飲食店経営の鍵です。
本記事では、店長育成の目的やゴールを明確にし、現場で結果を出すために必要なスキルセットを解説します。さらに、5ステップで構築する育成プログラムの仕組みや、成長を感じさせる実践的な事例を紹介し、飲食店の店長育成を成功へと導くための具体的な解決策を提供します。
あなたの飲食店が持続的に成長するための店長育成の秘訣を知り、経営課題を解決しましょう。
目次
1. 飲食店で店長育成が重要な理由【人材不足時代の経営課題】
近年、飲食業界では慢性的な人材不足が続いており、特に「任せられる店長が育たない」ことが多くの店舗の共通課題となっています。
人が足りない状況では、店長自身が現場プレイヤーとして動き続けざるを得ず、スタッフ教育や数値管理まで手が回らない。結果として“人が育たず、定着しない”という悪循環に陥りやすいのです。
こうした時代だからこそ、「店長育成」は単なる教育ではなく“経営の根幹”と捉える必要があります。
店長がしっかり育てば、スタッフ教育・売上管理・顧客満足すべてが安定し、経営者の負担も大きく軽減します。教育は「コスト」ではなく「未来への投資」。人材を育てることで、長期的には採用コストの削減、離職率の低下、顧客ロイヤルティの向上といった成果につながります。
特に注目すべきは、ティーチングとコーチングの併用が離職防止に効果的だという点です。
新人スタッフには“教える”ティーチング、中堅以上には“考えさせる”コーチングを使い分けることで、成長実感を得やすくなり、職場への定着率が高まります。実際に、教育制度を整備した店舗では、平均より離職率が5〜10ポイント改善したというデータもあります。
2. 店長育成の目的とゴールを明確にする
店長育成のゴールは単に「業務ができる人」を増やすことではありません。
真の目的は、「理念やミッションを現場に浸透させ、チームを動かせる人」を育てることです。経営者の想いをスタッフ一人ひとりが理解し、日々の接客や業務で体現できるようになる。その中心に立つのが店長です。
店長に求められるのは、以下の7つの資質・スキルです。
・教育力:スタッフの成長を促し、育てる力
・マインド:前向きで学び続ける姿勢
・コミュニケーション力:信頼関係を築き、誤解を防ぐ
・リーダーシップ:目標に向かってチームを導く
・計画力:課題を分解し、行動計画を立てる
・問題解決力:トラブルに柔軟かつ冷静に対応する
・財務管理能力:売上・コスト・利益を意識した店舗運営を行う
さらに、育成において重要なのが理念・ミッションの浸透です。
店長自身が理念を理解し、日常の会話や朝礼で“自分の言葉で語る”ことで、スタッフに自然と伝わります。理念を体現する店長が増えれば、店舗ごとのばらつきが減り、企業全体で一貫したブランド体験を提供できるようになります。
3. 店長に求められる役割とスキルセット【現場で結果を出す力】

店長は単なる現場責任者ではなく、日々のオペレーションから人材育成、売上・コストの管理まで、幅広い業務を担っています。
3-1:店長の主な役割
店舗運営の管理:衛生・品質・スピード・接客のすべてをバランスよくコントロールし、現場が安定して回る仕組みをつくる。
スタッフ育成とチームづくり:アルバイトを含めた全スタッフのモチベーションを維持し、チームとして成果を出せる環境を整える。
顧客満足とクレーム対応:お客様の声を迅速に拾い、再来店につなげる。クレームは「チャンス」と捉え、改善へつなげる。
本部・エリアとの情報連携:現場からの改善提案を上げ、本部方針を現場に落とし込む。
3-2:店長に求められるスキル・マインド
・リーダーシップと影響力
・コミュニケーション力と傾聴力
・問題解決力と冷静な判断力
・計数管理力と経営感覚
・DXリテラシー(勤怠・売上分析などのITツール活用)
3-3:部下育成が難しい理由とその解決策
飲食店では、部下育成が難しいと感じる店長が非常に多いです。
その主な理由は以下の通りです。
・業務量が多く、教育の時間が取れない
・アルバイト比率が高く、シフトが安定しない
・スタッフの入れ替わりが激しく、教育が継続しない
・“教えること”より“自分でやる方が早い”という意識
こうした課題を解決するには、スモールステップ教育が効果的です。
一度にすべてを教えようとせず、「今日はレジ操作」「次はドリンク準備」など、段階的に習得させることで成長を実感させます。
また、週1回の短い振り返り面談を設けるだけでも、定着率が大きく変わります。
4. 店長育成プログラムの作り方【5ステップで仕組み化】
店長育成を属人的な「現場の努力」に任せるのではなく、体系的なプログラムとして仕組み化することが重要です。
ここでは5つのステップで育成の流れを整理します。
STEP1:現状分析と理想の店長像の定義
まず、自社・自店舗の現状を正確に把握します。
離職率、店長経験年数、売上変動などのデータを基に、理想の店長像を明確化しましょう。
「理念を体現できる人」「チームを任せられる人」といった“行動基準”を言語化することがスタートラインです。
STEP2:育成計画の策定(期間・目標・評価軸)
次に、育成を短期・中期・長期に分けて設計します。
1年単位での教育テーマを定め、3か月ごとに中間評価を行うのが理想です。
KPIの目安としては、
・1on1面談実施率:90%以上
・教育プラン達成率:85%以上
など、数値目標を明示すると行動に落とし込みやすくなります。
※あくまでも目安ですので貴社のご状況にあった数値を設定するようにしてください。
STEP3:教育内容の設計(OJT・OFF-JT・eラーニング)
効果的な育成のためには、3つの学びのバランスが大切です。
| スタッフ層 | Teaching | Coaching | 主な目的 |
| 新人スタッフ | 80% | 20% | 基礎知識・業務ルールの習得 |
| 中堅スタッフ | 50% | 50% | 自律行動・改善提案の促進 |
| リーダー候補 | 20% | 80% | チームマネジメント・育成力強化 |
教育テーマ例:
✓理念・ミッション研修
✓リーダーシップ・コミュニケーション研修
✓問題解決研修/接客研修
✓DX・データ活用研修(売上分析・在庫管理など)
STEP4:評価とフィードバックの仕組み
教育の効果を高めるには「評価」と「振り返り」が欠かせません。
月2回の1on1面談(15分程度)を実施し、「行動→結果→学び→次の行動」を明確にします。
また、指導時にはIメッセージを意識しましょう。
「あなたが悪い」ではなく、「私はこの点が気になった」「こうしてもらえると助かる」と自分主体で伝えることで、相手の防衛反応を避け、信頼関係を保てます。
STEP5:仕組みの定着と改善(PDCA運用)
最後に、育成の仕組みを定着させるためにPDCAを回します。
「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)」を繰り返し、教育制度を“育てる”意識を持ちましょう。
成功事例の共有や、育成担当者同士の交流もモチベーション維持に有効です。
5. 優秀な店長を育てるポイントと実践事例
店長育成を成功させるには、単に研修を行うだけでなく、**「現場で成長を実感できる仕組み」**を整えることが欠かせません。
人は“できた”という実感が得られると自己効力感が高まり、やる気と定着率が上がります。
5-1:成長を感じさせる仕組みづくり
効果的な方法の一つがスモールステップ教育です。
大きなゴールをいきなり目指すのではなく、「まずはレジ対応を任せる」「次は発注補助を担当する」など、小さな達成体験を積ませていきます。
このステップを店長がきちんと設計し、クリアするたびに承認と称賛を与えることで、スタッフは「成長している自分」に気づき、さらに学ぼうとする姿勢が生まれます。
たとえば、「発注→在庫→教育→数字管理」という順で段階を設け、各段階ごとに「到達したら○○の権限を与える」と明確にしておくと効果的です。
このプロセスを通じて、店長自身も“育てる喜び”を体験できます。
5-2:ダメ店長を生まない教育のコツ
店長が育たない最大の原因は、「任せきり」「放任」「属人化」にあります。
「自分で考えろ」「背中を見て覚えろ」だけでは、学びが属人的になり、再現性が生まれません。
優秀な店長を育てるためには、成果ではなく“プロセス”を褒める文化が重要です。
「なぜうまくいったのか」「どう工夫したのか」を具体的に言語化して称賛することで、スタッフの行動が定着します。
こうした文化を広げることで、失敗を恐れず挑戦できる職場風土が育ちます。
5-3:コーチング質問レパートリー(実践例)
店長がコーチングを活用する際は、問いかけの質が鍵になります。
質問は“正解を導くため”ではなく、“相手に考えさせるため”に使うものです。
すぐに現場で使える質問例は以下の通りです。
↓
・「今日一番うまくいったことは何?」
・「次に改善できそうな点はどこ?」
・「お客様の立場で見たら、どう感じると思う?」
・「A案とB案なら、数字的にどちらが効果的だろう?」
・「明日もう一度やるとしたら、どんな工夫をする?」
こうした質問を通じて、部下が自分で考え、自分の答えを出すようになります。
この積み重ねが“自走できるスタッフ”を育てる第一歩です。
5-4:Iメッセージの活用
指導時にもう一つ意識したいのが、I(私)メッセージです。
「あなたが間違っている」と伝えるのではなく、「私はこう感じた」「こうなると困る」と主語を自分にする伝え方です。
例:
×「あなたの接客は雑だ」
○「私は接客時にお客様が不安そうにしているのを見て、少し声のトーンを変えた方が良いと感じた」
相手を責めずに“事実+感情+期待”をセットで伝えると、指導が受け入れられやすくなります。
信頼関係を損なわずに改善を促せるため、特に若手スタッフとの面談やクレーム対応の振り返りで有効です。
6. 店長育成を成功させるマネジメント体制

どれほど優れた育成プログラムを作っても、それを支えるマネジメント体制がなければ定着しません。
店長育成を仕組み化するうえで大切なのは、「店長を教育する店長を支える構造」を整えることです。
6-1:組織全体での支援体制を構築
本部は「理念・方針・評価軸」を明確にし、店長教育を戦略テーマとして位置づける。
エリアマネージャーは店長育成の伴走者として、現場での課題や進捗をフォロー。
店長自身は「教育するリーダー」として、スタッフ育成の時間を確保する。
この三位一体の体制ができると、教育が継続しやすくなり、人材が循環し始めます。
6-2:理念浸透の仕組みを持つ
理念やミッションを「掲げるだけ」で終わらせず、日常に落とし込む工夫が必要です。
たとえば次のような仕組みを取り入れると効果的です。
・月1回の“理念ミニトーク”を朝礼で実施(1〜2分で十分)
・月1回のワークショップで理念をテーマに事例共有
・理念を基にした「行動チェックリスト」を作り、評価にも反映
これにより、店長自身が理念を語り、スタッフの行動にも浸透していきます。
6-3:KPI管理と評価制度の整備
教育施策を成果に結びつけるには、数値指標の設定が不可欠です。
| 指標 | 推奨目標値 | 補足 |
| 1on1面談実施率 | 90%以上 | 月2回×15分を基本 |
| OJT計画達成率 | 85%以上 | 指導内容を可視化 |
| 理念ミーティング実施率 | 100% | 月1回の実施をルール化 |
数字で管理することで、教育の進捗が明確になり、現場の自律性も高まります。
※あくまでも目安ですので貴社のご状況にあった数値を設定するようにしてください。
7. 店長候補・若手スタッフへの育成展開
店長育成を“店長だけの教育”にとどめず、将来のリーダー候補にも拡大することが大切です。
若手スタッフが早い段階で“教える立場”を経験することで、主体性と責任感が育ちます。
7-1:キャリアパスを明確にする
スタッフが「この会社でどう成長できるか」をイメージできるように、キャリアパスを可視化します。
例:新人 → サブリーダー → 副店長 → 店長 → エリアマネージャー
各段階で求められるスキルや判断基準を明示し、「次に何を学べば良いか」を明確にすることで、モチベーションが継続します。
7-2:モチベーションを高める仕組み
・称号やバッジ制度:達成ステップごとに称号を与える(例:「接客マスター」「新人育成リーダー」など)
・評価の“見える化”:成長ポイントを表彰・共有する
・教育担当者へのインセンティブ:教える側にも評価を与える
こうした「承認」と「報酬」が連動すると、組織の学びが自走するようになります。
ちなみに私たちのアプリをご利用中の飲食チェーン店様で「スタッフを賞賛する仕組み」を作っている成功事例を無料公開しておりますので、もしよろしければダウンロードしてご覧ください。
必要事項をご記入ください。
すぐに下記の詳細資料がダウンロードできます。
プライバシーポリシーをご確認、ご同意の上、「同意して送信」ボタンを押してください。
※アクティブ・メディア株式会社から最新のお知らせなどお送りすることがあります。
![]() システム概要の資料:飲食店公式アプリ作成サービス
システム概要の資料:飲食店公式アプリ作成サービス
レストラン★スター

ダウンロード
- 内容
-
- 機能①事前販売・決済の機能
- 機能②ポイントカードをDX
- 機能③リピート販促を自動化
- 機能④アンケートでQSC改善
- 機能⑤投げ銭でES向上
- 運用サポートが私たちの強み etc.
![]() 販促事例の資料:アプリのQSCアンケートを活用した販促
販促事例の資料:アプリのQSCアンケートを活用した販促

ダウンロード
- 内容
-
- QSCアンケート機能の特徴
- 紙のアンケート・覆面調査との比較
- 成功事例(日本酒原価酒蔵様)
- アンケート機能の活用例
- 分析データの活用例 etc.
![]() アプリ導入インタビュー・事例集
アプリ導入インタビュー・事例集
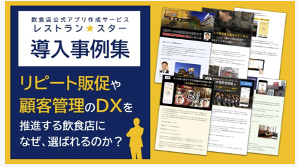
ダウンロード
- 内容
-
- 屋台屋 博多劇場 様
- INGS(CONA、焼売のジョー) 様
- ステーキのあさくま様
- 0秒レモンサワーⓇときわ亭様
- 日本酒原価酒蔵 様
- スター食堂 様
- 金剛園 様 etc.
8. まとめ|店長育成は“仕組み化”がすべて
店長育成の最終目的は、“教育が回り続ける仕組み”をつくることです。
ティーチングで基礎を最速で固め、コーチングで自走力を引き出す。
そのバランスが取れたとき、店舗は「人が辞めない」「数字が安定する」「雰囲気が良くなる」状態へと変わります。
店長育成を属人的な努力で終わらせず、計画・教育・評価を体系的に仕組み化する。
それが、持続的に成長する飲食店の共通点です。
教育文化が根づけば、店長もスタッフも“育てる喜び”を感じるようになり、店舗は自然と強くなっていきます。
今日からできる一歩として、「1on1面談を始める」「理念を語る」「スモールステップを設計する」。
小さな行動が、やがて大きな成果を生むのです。