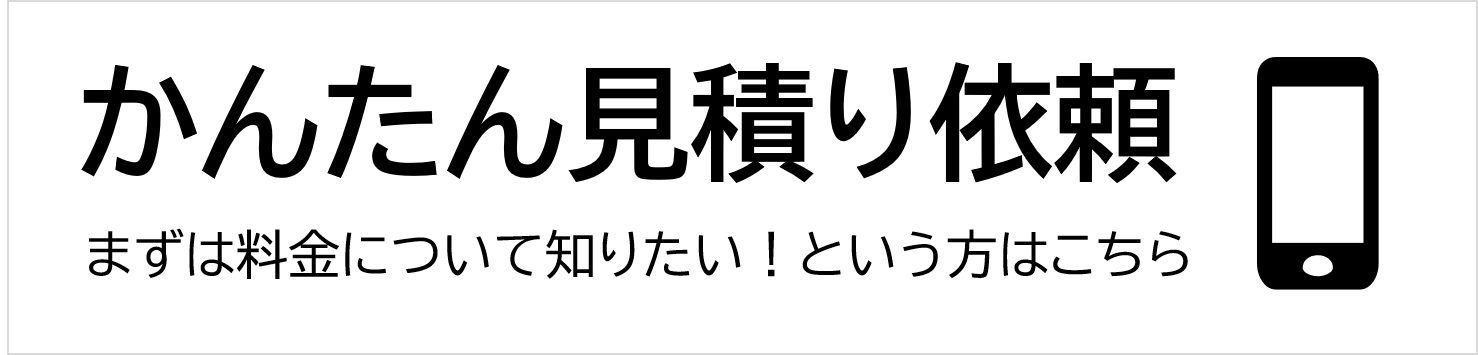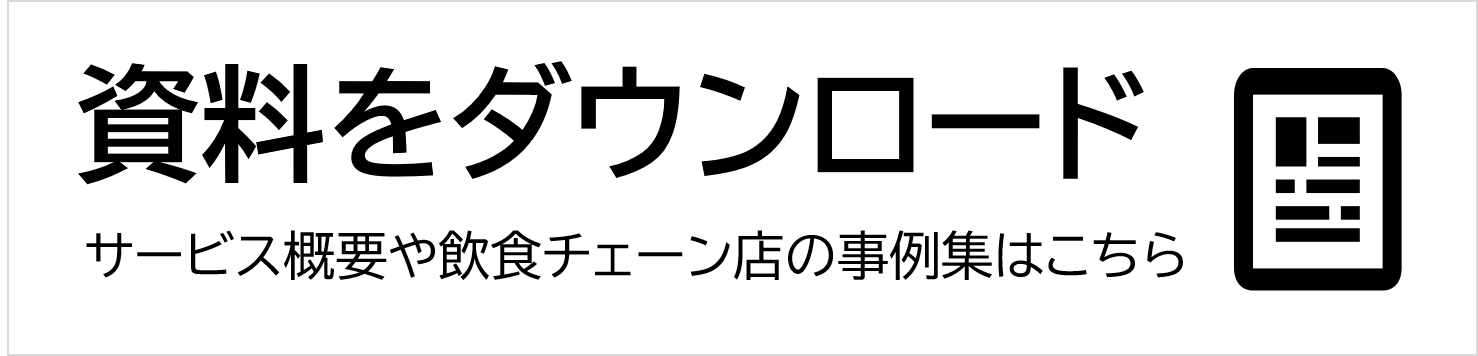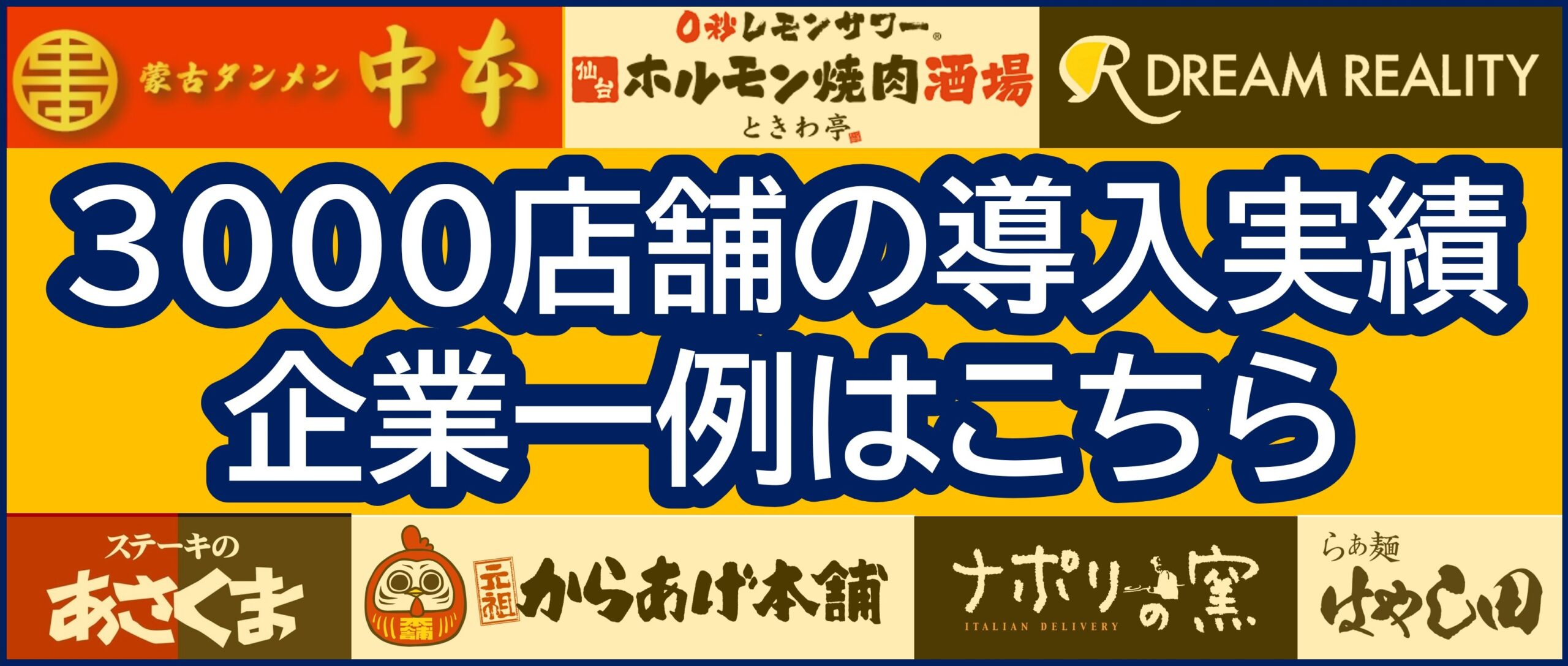あなたの飲食店は大丈夫?お店が潰れる前兆チェックして対策しよう
自分の飲食店経営に不安がある方は必見!飲食店が潰れる前兆を「現場」「経営」「客層」「経営者の姿勢」と視点を分けて体系的に解説します。
日々の運営に追われていると、潰れる前兆を見逃してしまうこともあります。しかし、これらの兆候に気づき、適切な対策を講じることで経営の安定を図ることができます。
そこで当記事では、飲食店が潰れる前兆を現場の共通点や経営の乱れ、集客の変化などから詳しく解説し、具体的な対策方法を提案します。
この記事を読むことで、あなたの飲食店を守るための具体的なアクションプランを見つけることができ、潰れる前兆を未然に防ぐためのヒントを得ることができます。
経営者の思考と行動が変われば、飲食店の未来も大きく変わります。今すぐチェックして、潰れない飲食店を築きましょう。
目次
1:飲食店が潰れる前兆とは?【現場で見られる共通点】

飲食店が閉店に向かうとき、必ずといっていいほど“現場”にそのサインが現れます。
一見すると些細なことでも、それが積み重なることでお客様の評価を下げ、再来店につながらなくなっていくのです。ここでは、日々の営業のなかで見逃しがちな5つの前兆を解説します。
1-1:提供時間が長くなっている
お客様に料理を提供するまでの時間が長くなっていませんか?
提供時間の遅れは、顧客満足度を大きく損なう要因のひとつです。特にランチタイムなどの忙しい時間帯では、1分の遅れが「もう行かない」という判断につながることもあります。
オペレーションの乱れが原因であれば、厨房とホールの連携が取れていない可能性があります。また、慢性的な人手不足や、未熟なスタッフへの教育が行き届いていないケースも少なくありません。
「最近、料理が遅いと言われるようになった」と感じたら、現場の動線や人員配置を見直すタイミングです。
1-2:店内の清掃が不十分
清潔感のない店内は、お客様に強い不快感を与えます。
トイレの汚れ、テーブルの拭き残し、床のゴミなど、どれかひとつでも目につけば、「この店は衛生管理ができていない」と思われてしまいます。
実際には、忙しさから掃除の時間が確保できなかったり、清掃の優先順位が下がってしまう現場も多いのが実情です。しかし、こうした状況は“経営に余裕がない”ことの現れでもあります。
清掃が行き届いている店は、それだけで信頼され、リピート率も高くなる傾向にあります。
1-3:看板メニューの注文が減っている
店の顔ともいえる看板メニューの注文数が減ってきたと感じたら、危機感を持つべきです。
「味が落ちた」「飽きられている」「他に魅力がない」といった理由が隠れている可能性があります。
看板メニューは、お客様が来店動機として期待するメニューであると同時に、店舗の強みを象徴する存在です。注文が減るということは、その強みが失われているサインともいえるのです。
必要であればレシピを見直したり、写真や盛り付け、紹介文なども再検討しましょう。
1-4:スタッフの離職が続いている
スタッフの入れ替わりが激しい店舗は、接客や提供スピードなどサービス全体の質が安定しません。
新人の教育にも時間と労力がかかり、現場は常にバタバタしてしまいがちです。
離職の原因には、職場環境・人間関係・将来性への不安など、さまざまな要素が絡みます。経営者として「スタッフが続かない理由」を真摯に受け止め、改善する姿勢が問われます。
スタッフの定着率が高い店舗は、現場の雰囲気がよく、結果としてお客様からの信頼にもつながります。
1-5:小さなクレームやトラブルが増えている
「料理がぬるかった」「注文と違うものが来た」など、小さなクレームが増えてきたと感じたら、それはサービス低下のサインかもしれません。
多くの場合、こうしたトラブルは現場の疲弊やコミュニケーション不足が原因で起こります。
見過ごされがちですが、小さなクレームの積み重ねが、悪い口コミやレビューに直結します。
重要なのは、クレームを受けたときに真摯に対応するだけでなく、根本原因を突き止めて改善する体制を作ること。クレームは「お客様が離れる前の最後の声」ともいえる、貴重なヒントです。
次章では、「数字と仕組み」から見えてくる運営・経営上の前兆について解説していきます。現場に異変が出ているなら、裏側の経営にもサインが出ているかもしれません。
2:運営・経営の視点で見る前兆【数字と仕組みの乱れ】

飲食店経営では、現場だけでなく“経営の土台”である数字や仕組みも重要なチェックポイントです。
目に見えない部分でのほころびは、気づかないうちに資金繰りを圧迫し、立て直しが困難になるケースもあります。ここでは、運営面から読み取れる潰れる前兆を5つ紹介します。
2-1:原価率や売上管理ができていない
「今日いくら売れたか」「今月の利益はどのくらいか」といった基本的な数字を把握していますか?
原価率や売上の管理が曖昧だと、利益が出ているのか赤字なのかすら判断できず、対策も立てようがありません。
例えば、人気メニューが実は利益をほとんど生まない“儲からない料理”になっているケースもあります。
「忙しい=儲かっている」と錯覚して、実際は赤字というのはよくある話です。
エクセルやPOSレジ、売上管理アプリなどを使って、日次・週次で数字を見直す仕組みを整えることが急務です。
2-2:SNSやホームページが放置されている
今や集客の入り口は「ネット検索」や「SNS経由」が当たり前の時代です。
にもかかわらず、InstagramやX(旧Twitter)、Googleマップ、ホームページなどの更新が止まっていれば、「この店はやる気がないのかな」と思われてしまいます。
特に新規客は、ネット上の情報を頼りに来店を判断します。
最新メニューや営業時間が出ていない、投稿が1年以上前で止まっていると、機会損失がどんどん積み重なります。
お金をかけなくてもできる情報発信は、集客の基本です。まずは「最低月1回の更新」を意識してみましょう。
2-3:割引やキャンペーンに頼りすぎている
「集客が落ちてきたから、値引きで呼び戻そう」
そんな考えで繰り返される割引キャンペーンは、一時的にお客様を集めることができても、長期的には経営を圧迫します。
値引きに慣れたお客様は、通常価格での来店を敬遠しやすく、利益率も下がります。
また、頻繁な割引はお店のブランド価値や信頼感を損なう原因にもなりかねません。
値引き以外で価値を提供する——例えば、限定メニューや接客体験の強化など、差別化戦略が求められます。
2-4:テナントの入れ替わりが激しい場所に出店している
自店の立地を見直してみてください。そのエリアで以前に何店舗も閉店していませんか?
テナントの入れ替わりが激しい場所は、もともと人通りが少ない、駐車場がない、家賃が高い、競合が強すぎるなど、構造的な問題を抱えている場合があります。
「条件がよかったから」「空いていたから」と安易に選んでしまうと、苦戦するのは時間の問題です。
集客に困っている場合は、立地そのものがネックになっていないか再評価してみることをおすすめします。
2-5:責任転嫁や決断の先送りが増えている
売上が下がったとき、「スタッフのせい」「周辺環境の変化のせい」と外部に責任を求めていませんか?
もちろん外的要因の影響もありますが、それを放置しているのは経営者自身です。
また、「今は忙しいから」と意思決定を先延ばしにしてしまうことも、危機を招く大きな要因です。
店舗経営では、変化への対応スピードが生死を分けます。「見て見ぬふり」をせず、数字と現場を正面から見つめる姿勢が、潰れないお店をつくる第一歩です。
次章では、お客様の変化から読み取れる潰れる前兆について紹介します。日々の営業の中で、顧客の“見えないサイン”に気づけているでしょうか?
3:客層・集客の変化からわかる前兆【お客様の異変】

飲食店は「お客様ありき」のビジネスです。
そのため、来店客の様子や動きに変化が見られたとき、それは経営上の大きなサインになり得ます。
ここでは、集客や顧客動向の観点から見えてくる“見落とされがちな前兆”を4つ解説します。
3-1:来店客数が減っている
最もわかりやすい異変は、「客数の減少」です。
しかし、ただ「最近お客さんが少ないな」と感じているだけでは不十分です。
時間帯・曜日・客層など、細かく分析して原因を探ることが大切です。
例えば、同じ来店数の減少でも「平日ランチの会社員が減っている」のか、「週末の家族連れが減っている」のかで、取るべき対策は変わります。
また、「競合が増えた」「地域の人の流れが変わった」など、外部環境の変化も見逃せません。
数字で追い、傾向を掴み、打ち手を見つけることが求められます。
3-2:客層が想定とズレてきている
「うちのターゲットはファミリー層だったはずなのに、最近は学生ばかり来る」
「単価の高い料理を出しているのに、安さを求める客が増えた」
こうした“客層のズレ”は、店舗とお客様の関係性に歪みが生じている証拠です。
理由としては、周辺環境の変化、競合店の影響、SNSでの誤認拡散などが挙げられます。
ズレに気づかず放置すると、ターゲットとのミスマッチが深刻化し、満足度もリピート率も下がってしまいます。
まずは、現在の客層を可視化し、当初の理想像と照らし合わせて再設計しましょう。
3-3:顔ぶれが固定化している(新規客が少ない)
常連のお客様に支えられているのはありがたいことですが、新規客がほとんど来なくなっている場合は要注意です。
店舗の未来を担うのは、新たに入ってくるお客様であり、常連だけに依存した経営は危うさをはらんでいます。
特にリピーターが高齢化していたり、生活スタイルの変化で通えなくなる場合など、将来的な売上の先細りが懸念されます。
新規来店の導線があるか、入口となる発信・施策があるかを今一度確認する必要があります。
3-4:グルメサイト・口コミ評価が落ちてきた
食べログ、Googleマップ、Instagramなど、飲食店は多くの「口コミメディア」で評価される時代です。
最近、星の数が下がったり、低評価の投稿が増えていたりしませんか?
悪い評価をもらってしまうのは仕方のないことですが、それに反応せず放置していると「改善の姿勢がない店」と見なされ、印象がどんどん悪化します。
また、口コミの数自体が少ない場合も、検索上の露出が減り、見つけてもらいにくくなります。
定期的に自店の口コミをチェックし、返信や改善で信頼を積み上げていくことが重要です。
次章では、こうした前兆が現れる店舗に共通する「経営者の考え方や姿勢」について掘り下げていきます。
経営者の“心の状態”こそ、店舗の未来を左右する最大の要因かもしれません。
4:潰れる前兆が出る飲食店に共通する【経営者の思考】

飲食店が潰れる原因は、立地や景気といった外的要因だけではありません。
実は、経営者の考え方や判断力が、経営の命運を大きく左右していることが非常に多いのです。
ここでは、業績不振の飲食店に共通する「思考の落とし穴」を3つ解説します。もし心当たりがあれば、すぐに思考の修正を試みましょう。
4-1:現場の課題をスタッフ任せにする
「自分は経営者だから、現場のことは現場に任せればいい」
このようなスタンスを取っていませんか?
もちろん経営者がすべてを抱えるべきではありませんが、現場の問題を把握せず、スタッフ任せにする状態は危険です。
売上の低迷やクレームの増加、離職率の上昇など、現場の異変に気づかず、対処が遅れるケースが多発します。
経営者が現場のリアルな声を知ることは、改善のスピードにも直結します。
ときには厨房に立つ、接客に入る、スタッフと面談するなど、“現場を感じる姿勢”が求められます。
4-2:新しいチャレンジや改善を避けている
売上が下がっているのに、「今は我慢のときだから」と現状維持を選んでいませんか?
変化を恐れて、これまでと同じことを続けていても、お客様の期待や時代のニーズとはどんどんズレていきます。
・新メニューを出すのが面倒
・SNSの更新が続かない
・スタッフ教育の見直しに腰が重い
こうした“行動しない理由”を並べている間に、競合店はどんどん改善を進めています。
小さくてもいいので、一歩踏み出すチャレンジを積み重ねていく姿勢が、飲食店の生存力を高めます。
4-3:「とりあえず続ける」で赤字経営を続けてしまう
「ここまでやってきたから」「今やめたらもったいない」と、赤字経営を続けていませんか?
感情的な執着が判断を曇らせ、撤退や業態変更といった“必要な決断”を先延ばしにしてしまう経営者は少なくありません。
赤字が続けば、資金は減り、スタッフも疲弊し、最終的に再起のチャンスすら奪われてしまいます。
むしろ、**早めの判断と撤退は「損切り」ではなく「次の成長への投資」**とも言えます。
大事なのは、利益を出すこと。そして、その手段や形は柔軟に変えていいという考えを持つことです。
次章では、ここまでで挙げてきた前兆に対して「では、どうすれば潰れずに済むのか?」という具体的な対策を紹介します。
現実を直視した上で、前向きに未来を描くヒントをお届けします。
5:潰れないために飲食店経営者ができる対策とは?
ここまで解説してきたように、潰れる前兆は“予兆”であり、“確定”ではありません。
つまり、今の状況を正しく認識し、適切な対策を打てば、逆転の可能性は十分にあるということです。
本章では、経営者が明日から実践できる5つの具体的な対策を紹介します。
5-1:原価・人件費・家賃のコスト管理を徹底する
まず見直すべきは「お金の使い方」です。
原価率が高すぎる、ピークタイム以外も人件費がかかりすぎている、高すぎる家賃を見直せていない…こうした積み重ねが、赤字経営の原因となっている可能性があります。
最低限、以下の数字を毎月チェックする習慣をつけましょう:
・売上総利益(売上−原価)
・営業利益(売上−原価−人件費−家賃等)
・メニューごとの原価率
利益を残す構造になっているかどうかを数値で把握できれば、「売れてるのに儲からない」状態を解消できます。
5-2:コンセプトやターゲットを再確認・再設計する
「誰の、どんなニーズに応える店なのか」が曖昧になっていると、店の軸がブレてしまいます。
特に、開業当初と地域の状況やお客様の層が変わっている場合、コンセプトの見直しは不可欠です。
ターゲットが明確になれば、
・メニューの価格帯や内容
・店内の雰囲気・接客スタイル
・発信するSNSのトーンやキャンペーン内容
などすべてに一貫性が生まれ、集客の効率が劇的に上がります。
原点に立ち返り、「このお店は、どんな人に選ばれるべきか?」をもう一度考えてみましょう。
5-3:SNS・HP・口コミ対応で集客基盤を整える
現代の飲食店にとって、情報発信とオンラインでの存在感は「看板」と同じくらい重要です。
InstagramやGoogleマップ、LINE公式アカウント、グルメサイトなどは、無料または低コストで始められる強力な集客ツールです。
・写真付きの投稿で看板メニューをアピール
・ストーリーズで本日のおすすめを紹介
・Googleの口コミに丁寧に返信する
・ホームページに最新情報を掲載
こうした積み重ねが、「なんとなく気になる店」から「行ってみたい店」へと変えてくれます。
5-4:看板メニューや体験価値を強化する
店舗に「これを食べに来たくなる」ような主力商品はありますか?
もし看板メニューが弱くなっていると感じたら、商品のブラッシュアップや“魅せ方”の工夫が必要です。
また、現代の飲食店では、味だけでなく「体験」も評価されます。
・写真映えする盛り付け
・接客時のワンフレーズ(「今日は特別な〇〇仕入れてます!」など)
・スタンプカードやクーポンガチャなどの“楽しさ”の設計
こうした体験価値を意識することで、リピーターづくりにもつながります。
5-5:人材育成と現場オペレーションの改善に取り組む
飲食店の品質は、結局「人」によって決まります。
スタッフの育成ができていなければ、接客の質は上がらず、クレームや離職にもつながります。
改善のためには、以下のような取り組みが効果的です:
・接客マニュアルをつくる(動画でも可)
・定期的なフィードバックの機会を設ける
・「ありがとう」が飛び交うチームづくりを目指す
人材が定着し、戦力化できる環境を整えることは、長期的に見て最大の経営改善とも言えます。
次章では、ここまでの前兆と対策を踏まえて、飲食店が生き残るために必要な考え方を改めて整理します。
現実を直視したうえで、「では、どう進めばいいのか?」を再確認しましょう。
6:まとめ|前兆を見逃さず、潰れない飲食店をつくろう
飲食店が潰れるとき、突然ではなく“必ず前兆がある”ことをお伝えしてきました。
それは現場の些細な変化から始まり、数字や仕組みの乱れ、客層のズレ、そして経営者自身の思考のクセにまで及びます。
しかし、前兆はあくまで「兆し」であり、今ならまだ間に合うサインでもあります。
大切なのは、それを見逃さないこと。そして、見つけたらすぐに動くことです。
本記事の振り返り
・現場の異常(提供の遅れ・掃除不足・クレーム増加など)は顧客離れのきっかけになる
・経営の乱れ(原価管理・情報発信・安易な値引き)は利益を圧迫し続ける
・客層の変化(来店減・新規客の不足・口コミ低下)は集客力の劣化を示す
・経営者の思考(任せきり・現状維持・撤退の遅れ)は改善を遅らせる最大の要因
・対策は必ずある。数字を見直し、ターゲットを再設定し、強みを磨き、チームを育てることで再起は可能
飲食業界は、トレンドも環境も変化が激しく、常に「挑戦と改善」が求められる業種です。
ですが、それと同時に、人の心を動かし、地域に愛され、長く続けていける“可能性のあるビジネス”でもあります。
「うちは大丈夫」と思っている今こそ、見直しのチャンス
今回ご紹介した前兆に、少しでも心当たりがあった方は、ぜひ今このタイミングで、自店を客観的に見直す機会を持ってください。
現実を直視することは勇気が要ることですが、その一歩こそが“潰れない店づくり”の第一歩です。
あなたのお店が、地域に長く愛される存在であり続けられるよう、今こそ手を打ちましょう。
それではこの記事は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。